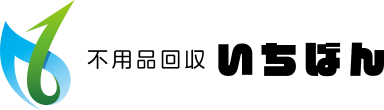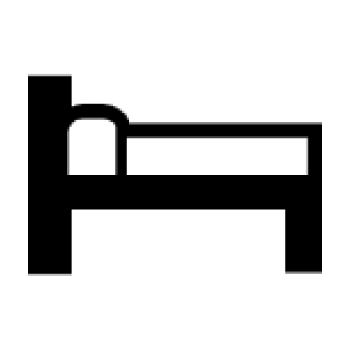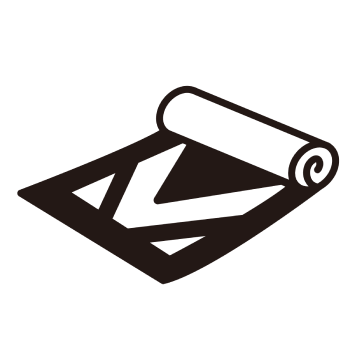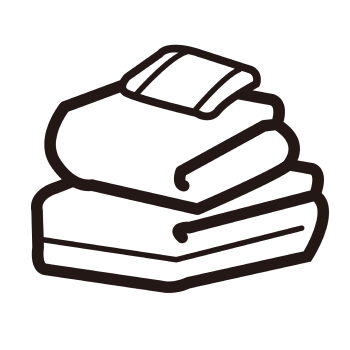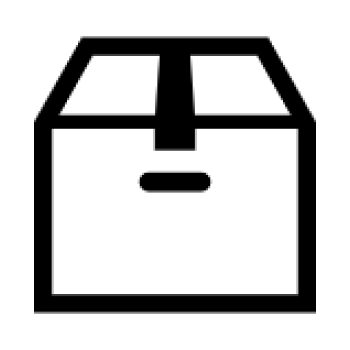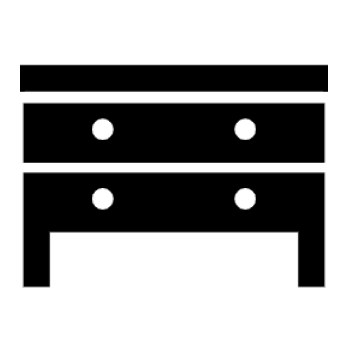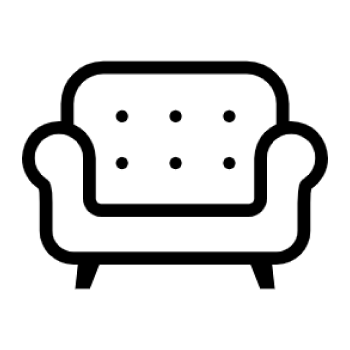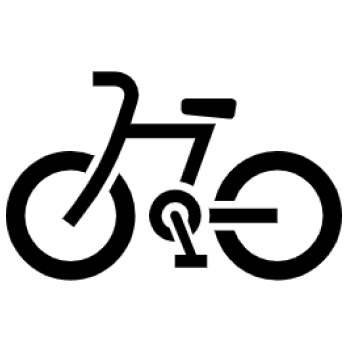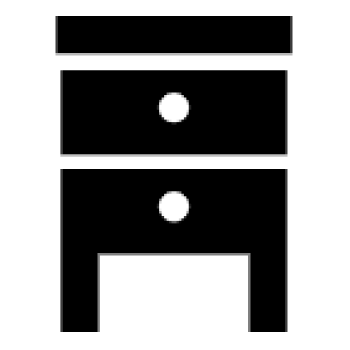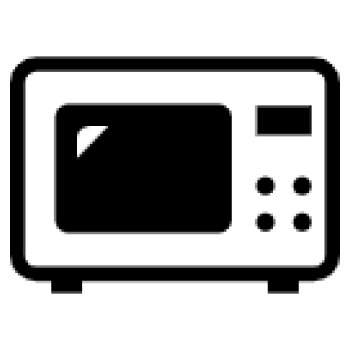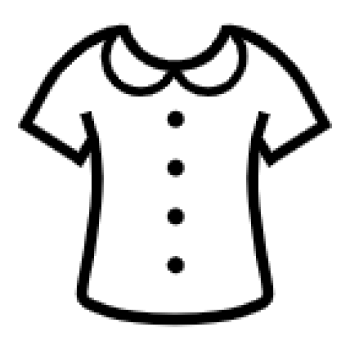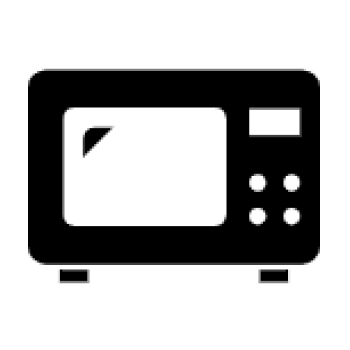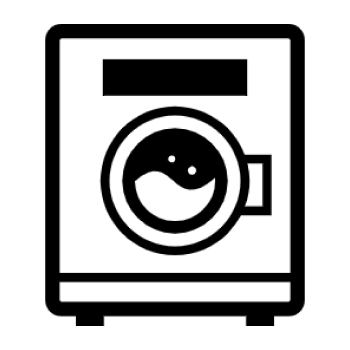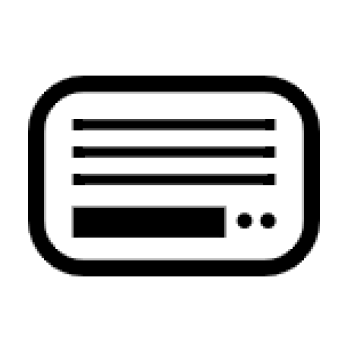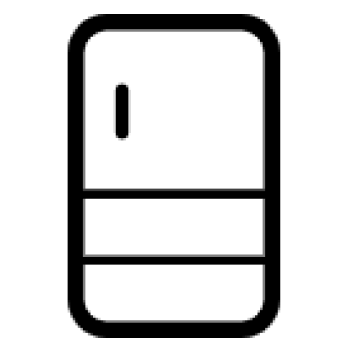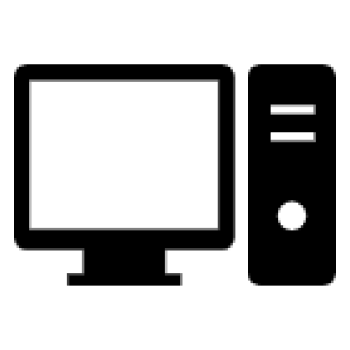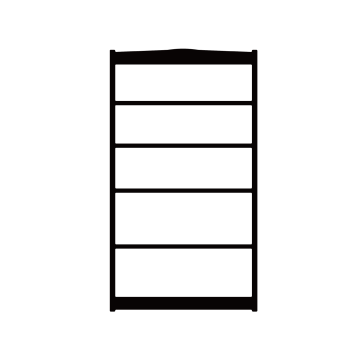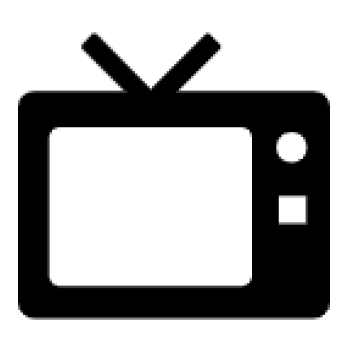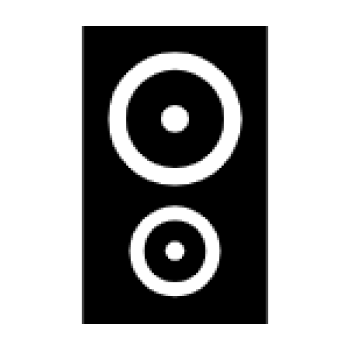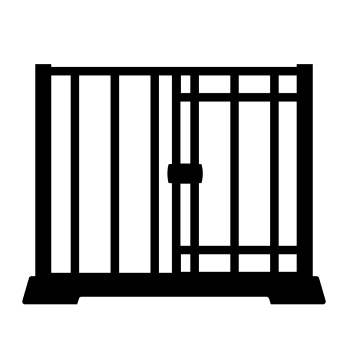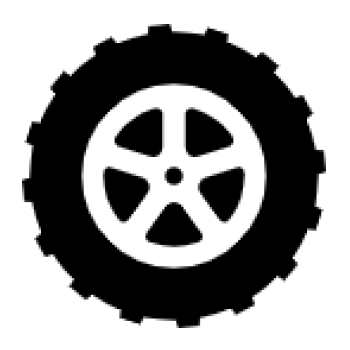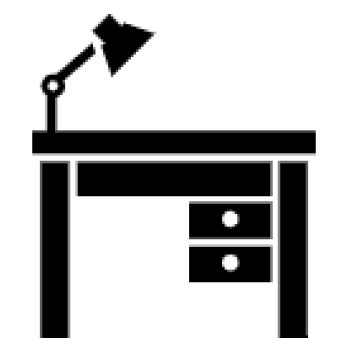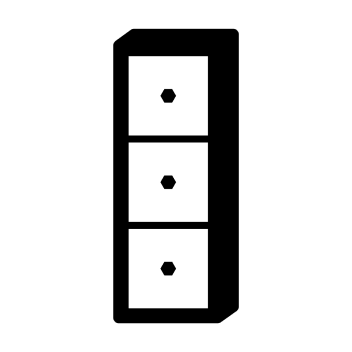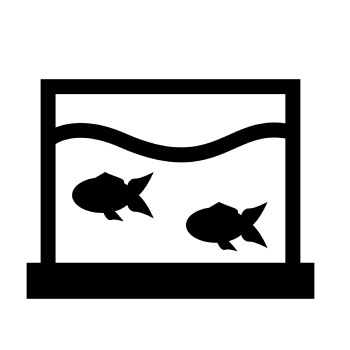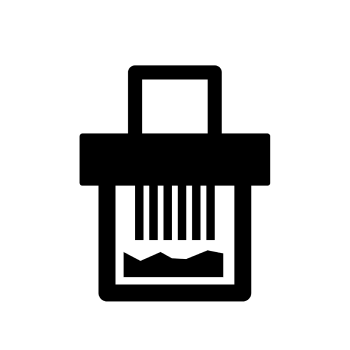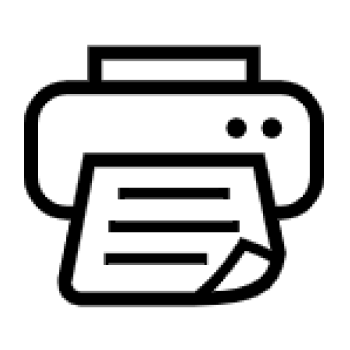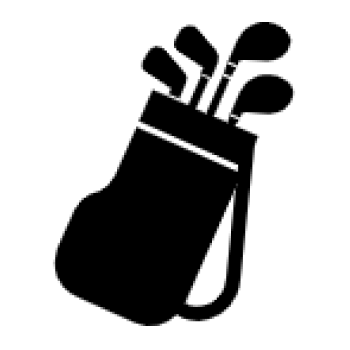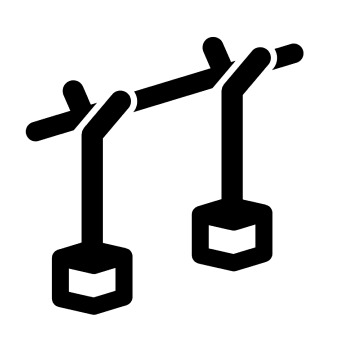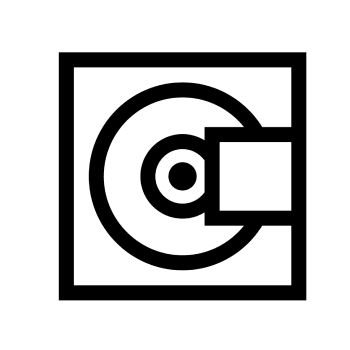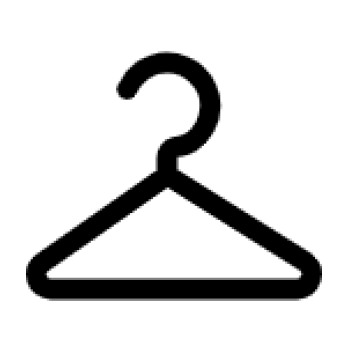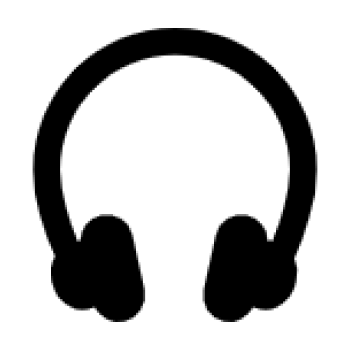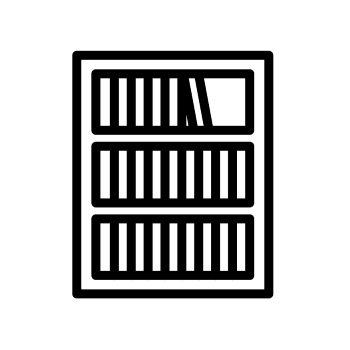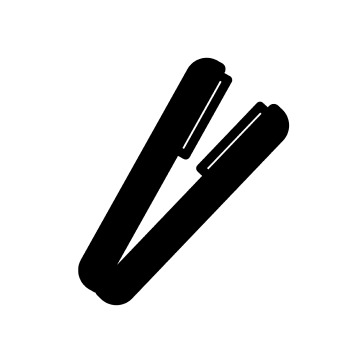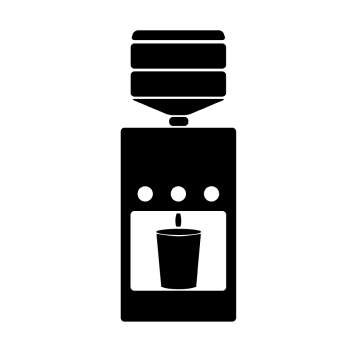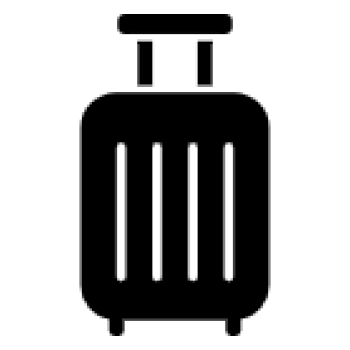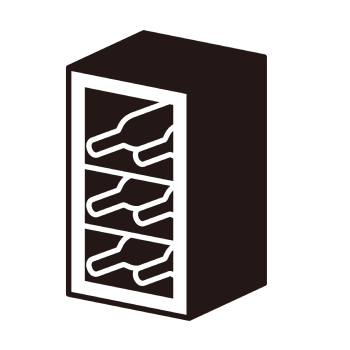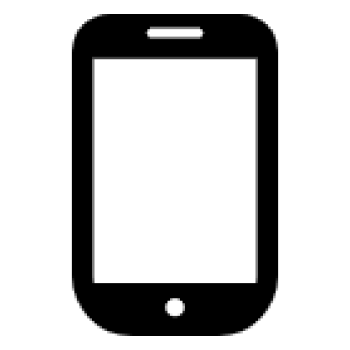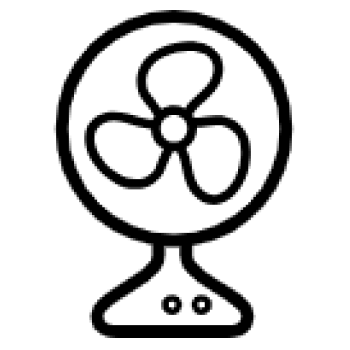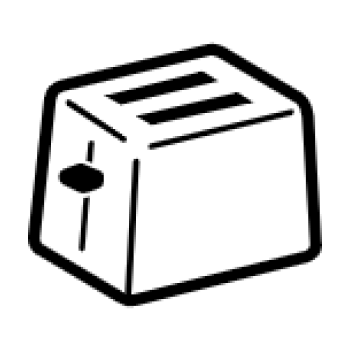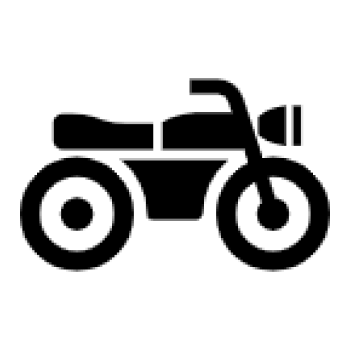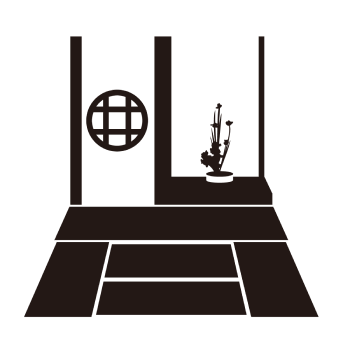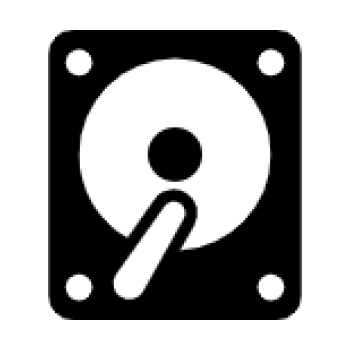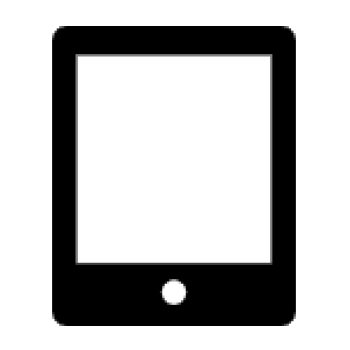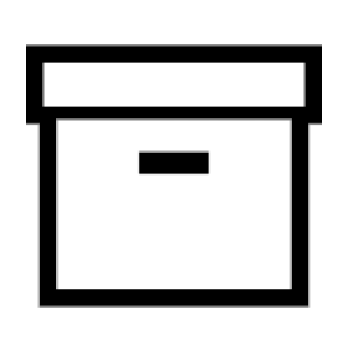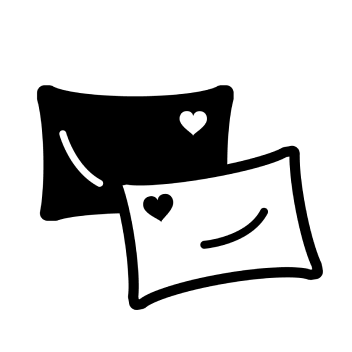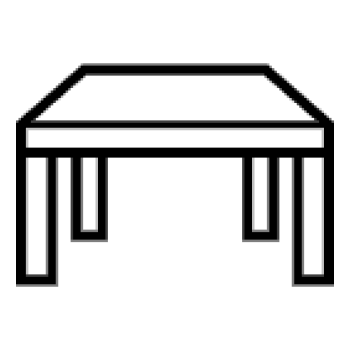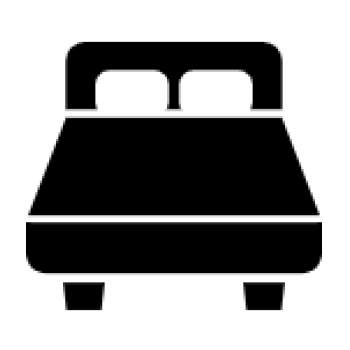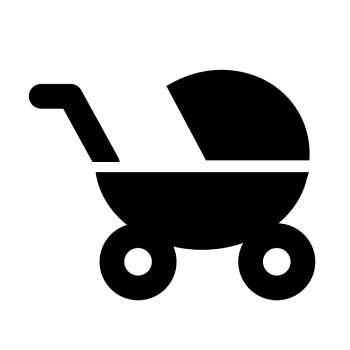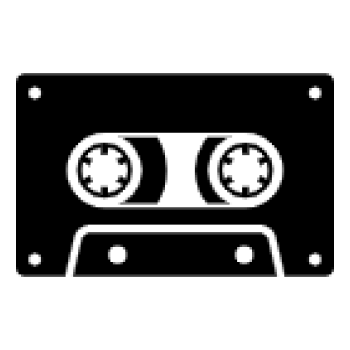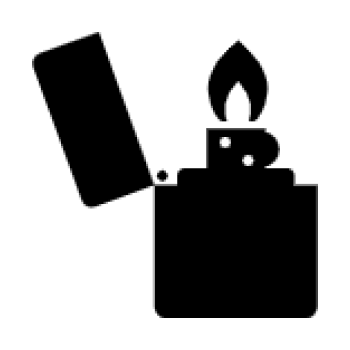寒い季節に欠かせない暖房器具のひとつに、石油ストーブやファンヒーターがありますが、それに欠かせないのが灯油です。冬の間は重宝される灯油ですが、季節の終わりや引っ越し、機器の買い替えなどで余ってしまうことも少なくありません。そうした時、どのように処分すればよいのか悩んでしまう方も多いでしょう。灯油はガソリンと同様に揮発性が高く、誤った方法で処分すると火災や環境汚染のリスクがあるため、正しい手順で安全に処理することが大切です。この記事では、灯油を処分する最適なタイミングや残量による処分方法の違い、注意点や緊急時の対処法、そして具体的な処分方法まで詳しくご紹介します。
灯油を処分するタイミング
灯油の処分を考えるタイミングとして最も適しているのは、冬の寒さが和らぎ、暖房器具の出番がなくなる春先です。特に3月から4月にかけては、気温の上昇とともに暖房の使用頻度が大きく減少するため、余った灯油の取り扱いを見直す絶好のタイミングといえるでしょう。この時期に灯油を見直しておくことで、安全面・経済面の両方でトラブルを未然に防ぐことができます。
時間の経過
一見すると、灯油は密閉容器に入れておけば翌年まで保存できると思われがちですが、実際には時間の経過とともに徐々に酸化し、品質が劣化していきます。特にポリタンクなどのプラスチック容器は完全な密閉ではなく、わずかに空気を通す性質があるため、どうしても酸化の影響を受けやすくなります。劣化が進んだ灯油は、見た目に変化がなくても、特有の酸っぱいような臭いが出たり、ストーブ使用時にススが発生したりと、さまざまなトラブルを引き起こします。機器の燃焼効率も落ち、最悪の場合は故障につながるケースもあります。
水分の混入
また、灯油を保管する際に見落とされがちなのが「水分の混入」です。ポリタンクの内部では気温差によって結露が発生し、これがタンクの内壁に水滴となって付着します。時間が経てばそれが灯油の中に混ざり、ストーブの不完全燃焼の原因となることがあります。灯油は基本的に水と混ざらないため、燃料タンクの底に水がたまり、配管を詰まらせる原因にもなり得るのです。
このような劣化やリスクを防ぐためには、灯油は「シーズン中に使い切る」ことを基本ルールとすべきです。購入量をあらかじめ調整し、余らせないよう計画的に使用するのが理想的ですが、どうしても余ってしまう場合には早めに処分を検討することが重要です。「もったいないから取っておく」といった発想が、結果的に機器の故障や火災リスクを高める要因となることを忘れてはいけません。
さらに、ガソリンスタンドや回収業者に依頼する場合でも、春や夏は比較的スムーズに対応してもらえる傾向があります。寒い時期には灯油の供給が優先されるため、回収サービスに時間がかかることもあるからです。このような点を踏まえても、灯油の処分は「冬の終わりから春先」に行うのが最も賢明な選択と言えるでしょう。
残量別の処分方法の違い
灯油の処分方法は、残っている量によって大きく異なります。少量か大量かで適切な処分手段が変わり、また使用する容器や保存状態によっても注意点が異なります。適切な処分方法を選ばなければ、火災や環境汚染などのリスクを引き起こすおそれがあるため、それぞれの状況に応じて正しい方法を選びましょう。
少量の場合(ほんのわずかに残っている場合)
まず、容器の底にほんの少しだけ残ってしまった場合や、古い灯油が数十ミリリットルほど残っている場合は、新聞紙やボロ布、オイル吸収材などに染み込ませたうえで、可燃ごみとして処分する方法があります。ただし、この方法はあくまで「少量」の灯油に限ったものであり、処理後の新聞紙や布も密閉して廃棄するなど、二次的な引火リスクを避ける工夫が必要です。加えて、自治体によってはこのような処分を禁止している地域もあるため、必ず地域のごみ分別ルールや自治体の清掃センターに確認してから行うことが重要です。
また、量が少なくても長期間保管されていた灯油はすでに劣化している可能性が高く、燃焼機器への再使用は推奨されません。無理に使用するとストーブやファンヒーターの故障や異臭、黒煙の発生といったトラブルに直結します。そうした古い灯油は、仮に少量でも処分を優先すべきです。
中量(数リットル程度)の場合
ポリタンクにある程度残っている、たとえば5リットル前後の灯油がある場合は、ガソリンスタンドや灯油を販売しているホームセンター、燃料販売業者などで引き取ってもらえるかどうかを確認しましょう。引き取りを行っている店舗であれば、安全に処理してくれるだけでなく、適正な処分方法でリサイクルや廃棄処理を行ってくれます。
ただし、すべての店舗が灯油の引き取りを行っているわけではありません。特に個人経営の小規模スタンドや、セルフ式のガソリンスタンドでは対応していないことが多く、事前の確認は必須です。電話や公式ホームページで確認するか、実際に足を運んで問い合わせるのが確実です。また、引き取りには無料と有料のケースがあり、持ち込みには購入証明書の提示が必要な場合もありますので、条件をよく確認しておきましょう。
大量(10リットル以上)の場合
引っ越しや施設の閉鎖、法人の備蓄分の処分などで、10リットルを超える灯油が残ってしまっている場合、自力で処理するのは非常に危険であり、現実的ではありません。大量の灯油は揮発性が高く、密閉された空間ではわずかな火花でも引火する危険があります。そのため、専門の不用品回収業者や産業廃棄物処理業者に依頼するのが最も安全で現実的な選択肢です。
これらの業者は灯油の性質や法令を理解しており、専門の処理ルートを通じて適切に処分してくれます。特に灯油は「危険物第4類第2石油類」に分類されるため、一般廃棄物とは異なり、専門的な取り扱いが求められます。産業廃棄物処理業者に依頼する場合は、処理証明書を発行してくれる業者を選ぶと安心です。また、処分費用については量や地域によって異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、信頼できる業者を見極めることも大切です。
灯油を処分する際の注意点や禁止事項
灯油の処分を行う際には、安全性と法令順守の観点から、いくつかの重要な注意点と、絶対にしてはならない禁止事項があります。灯油は非常に引火性が高い液体であり、わずかな火種でも爆発的に燃え広がる性質を持っています。そのため、不適切な処分や取り扱いが思わぬ火災・爆発事故につながる可能性があり、取り扱いには細心の注意が必要です。
排水口やトイレ、河川、側溝などに流してはいけない
まず最も重要な点として、「灯油を排水口やトイレ、河川、側溝などに流してはいけない」というルールがあります。これらの行為は、単にマナー違反というレベルではなく、廃棄物処理法や水質汚濁防止法などの法律に違反する明確な違法行為にあたります。実際に、誤って灯油を下水に流したことで近隣の飲料水に混入してしまい、大規模な環境被害を引き起こしたという事例も報告されています。たとえ数百ミリリットル程度の少量でも、川や土壌に染み込んだ場合、魚類や植物に深刻なダメージを与える可能性があり、自然環境全体への影響は決して無視できません。罰金や懲役などの厳しい罰則が科せられるケースもあるため、灯油の不法投棄は絶対に避けるべき行為です。
可燃ごみとして捨てる
また、「紙や布に灯油を染み込ませて可燃ごみとして捨てる」という方法は、一部の自治体では少量に限って認められているものの、非常に慎重な取り扱いが必要です。この方法を誤って大量に行った場合、保管中やごみ収集時に自然発火する恐れがあり、実際に火災に至った事故例もあります。特に、使用済みの新聞紙や布類は酸素を多く含んでおり、油分とともに熱を蓄積すると引火点に達しやすくなります。そのため、この方法で灯油を処分する場合には、「ごく少量」であること、「火気のない場所で作業すること」、「直ちに密閉容器に入れて廃棄すること」が最低限の条件となります。
保管容器は市販の灯油専用ポリタンク
灯油を一時的に保管する場合にも、いくつかの注意点があります。まず、保管容器は市販の灯油専用ポリタンクを使用し、フタをしっかりと閉めて密閉状態を保ちましょう。蓋が緩んでいると、空気中の酸素と触れることで酸化が進むだけでなく、万が一倒れた場合に漏れ出す危険性があります。保管場所についても、高温多湿の場所や直射日光が当たる場所、暖房機器の近く、火花が出る機械のそばなどは絶対に避け、風通しの良い冷暗所で保管することが推奨されます。また、タンクに亀裂や変形、変色が見られる場合は、即座に中身を安全に処分し、新しい容器に交換する必要があります。
なお、不要な灯油を人に譲渡する場合にも慎重になるべきです。誰かに譲る際には「劣化していない新しい灯油か」「保管状況は適切だったか」を確認する必要があります。古い灯油を譲ってトラブルが発生した場合、思わぬ責任問題に発展するおそれもありますので、基本的には「自分で最後まで責任を持って処分する」ことを意識すべきです。
このように、灯油の処分には多くのルールと注意点が存在し、すべてを守ることが自分自身や周囲の安全を守ることにつながります。「少しぐらいなら大丈夫」という油断が、大きな事故の火種になることを常に意識して、冷静に対応しましょう。
灯油をこぼしてしまった場合や手についた時の対処法
灯油を家庭で扱っていると、給油作業中や移し替えの際にうっかりこぼしてしまうことがあります。わずかな量でも独特のにおいが強く、床材や衣類に染み込みやすいため、適切に対処しなければ長期間にわたって臭気が残ったり、健康被害や火災リスクにつながる恐れもあります。ここでは灯油が床や衣類、肌に付着してしまったときの具体的な対処法を詳しく解説します。
灯油を床にこぼしてしまった場合の対処法
まず、灯油をこぼしてしまったら慌てず、最初に行うべきは換気です。灯油は揮発性の高い液体であり、揮発した成分は空気中に拡散して室内に強いにおいを充満させるだけでなく、長時間吸い込むことで頭痛や吐き気、めまいといった体調不良の原因になることもあります。また、空気中の蒸気に引火するリスクもあるため、窓やドアを開けて空気の通り道を確保しましょう。可能であれば換気扇も回して、空気を早く入れ替えることが理想です。
換気が済んだら、次にこぼれた灯油を新聞紙や吸水性の高い布、キッチンペーパーなどで丁寧に吸い取ります。このとき、手袋を着用して直接手に灯油が触れないようにしましょう。広い範囲に広がっている場合は、紙や布を押し当てるようにしてゆっくり吸い込ませると、広がりを最小限に抑えられます。吸い取った紙や布はそのままにしておくと発火の危険があるため、必ず密閉できるビニール袋や専用の処分容器に入れ、各自治体の定める方法に従って処分してください。
灯油を拭き取った後でも、床ににおいが残っている場合があります。その際は中性洗剤を薄めた水や、重曹・酢水(酢:水=1:1)を使って何度か拭き取りましょう。床材によっては変色の恐れがあるため、まず目立たない場所でテストしてから使用することをおすすめします。特に木材のフローリングの場合、灯油が染み込んで取れにくいケースもあるため、においが取れない場合はリフォームや張り替えが必要になることもあります。
灯油が手や肌についてしまった場合の対処法
灯油が手や皮膚に付着した場合も、できるだけ早く対処することが大切です。灯油は皮膚への刺激が強く、長時間放置すると皮膚が乾燥し、かゆみやかぶれ、炎症を引き起こす可能性があります。まずは流水で洗い流しながら、中性のハンドソープや石けんで丁寧に洗浄してください。爪の間や手首のシワなどに灯油が入り込んでいることもあるため、しっかり洗いましょう。
洗浄後もにおいが残る場合は、重曹を少量手に取ってこすり洗いをすると、脱臭効果が期待できます。皮膚が弱い方は、洗浄後に保湿クリームなどを塗って保護すると、肌荒れを防ぐことができます。かゆみや赤み、ヒリつきが出た場合は、なるべく早く皮膚科を受診しましょう。
灯油が衣類に付着した場合の対処法
灯油が衣類に付着した場合、まずはすぐにその衣服を脱ぎ、他の衣類や布ににおいが移らないように隔離しておくことが重要です。灯油のにおいは繊維に深く染み込むため、通常の洗濯ではなかなか落ちません。洗濯前に重曹やセスキ炭酸ソーダを溶かしたぬるま湯に浸け置きしたり、中性洗剤を直接塗ってから洗うことで、ある程度においを軽減することができます。
しかし、においが取れない場合や何度洗っても揮発性の成分が残っていると感じるときは、処分する選択も検討すべきです。特に下着やタオル類、寝具など、肌に直接触れるものに灯油が付着した場合には、衛生面・安全面の観点からも潔く処分するのが安心です。
誤って目に入った・誤飲してしまった場合
非常に稀ではありますが、灯油が誤って目に入った場合や、誤飲してしまった場合には、自己判断での対処は禁物です。目に入った場合は直ちに流水で15分以上洗い流し、速やかに眼科または救急病院を受診してください。
誤飲した場合は、絶対に吐かせてはいけません。灯油を吐く際に気道に入り込むと、化学性肺炎を引き起こす可能性があり、命に関わる重篤な症状となることがあります。誤飲後は何も口にせず、すぐに救急車を呼ぶか、最寄りの中毒センターや病院に連絡して指示を仰ぎましょう。
灯油の処分方法4選
灯油は正しく保管していればある程度の期間は使用可能ですが、長期間放置したり、劣化して変質してしまった場合には、安全性の観点からも速やかに処分する必要があります。ただし、灯油は可燃性が高く、取り扱いを誤ると火災や健康被害のリスクを伴うため、家庭で安易に処分することは避けなければなりません。確実に安全に処理するためには、信頼できる専門施設やサービスを活用することがもっとも適切な選択肢となります。
自治体での処分は原則不可
多くの自治体では、灯油を家庭ゴミとして出すことを禁止しています。液体であり、引火性が高く、環境や衛生に与える影響が大きいためです。そのため、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」として出すことはできませんし、排水口や土に流すことも法律違反となります。処分方法に困った場合には、自治体の環境課などに相談して、地域で利用できる回収業者や対応施設を紹介してもらうのもひとつの方法です。
ガソリンスタンドや販売業者に引き取りを依頼する
灯油の購入先として最も一般的なのがガソリンスタンドです。こうした販売業者の多くでは、使い切れなかった灯油の回収や処分を有料・無料で対応している場合があります。まずは灯油を購入したガソリンスタンドに連絡し、引き取り対応が可能かどうかを確認しましょう。店舗によっては、灯油を入れていたポリタンクごと持ち込む必要がある場合や、特定の曜日・時間にしか受け付けていないこともありますので、事前の問い合わせが重要です。
回収費用は量や状況によって異なり、数百円~数千円程度が一般的です。多少の費用がかかるとしても、自宅で無理に処理しようとして火災や環境汚染につながるリスクを考えると、専門施設で適正に処分してもらう方がはるかに安心・安全です。
ホームセンターや灯油販売所のサービスを利用する
一部のホームセンターや地域の灯油販売店でも、不要になった灯油の回収を行っているケースがあります。特に寒冷地や灯油使用率の高い地域では、冬季を中心に灯油の供給・販売だけでなく、回収のニーズにも対応している店舗が多い傾向にあります。こうした店舗の多くでは、劣化した灯油の処分方法についても相談に乗ってもらえるため、初心者でも安心して利用できます。
また、リフォームや機器交換時に、給湯器やストーブ内に残っている灯油を処分してもらいたい場合には、提携しているサービス会社が一括で対応してくれることもあります。大型のホームセンターでは専用の処分窓口やサービスカウンターが設置されていることもあるため、店舗のホームページやサービス案内を事前にチェックしておくとスムーズです。
不用品回収業者・産業廃棄物処理業者に依頼する
家庭でどうしても処分が難しい場合や、残っている灯油の量が多く、自力で運べないといったケースでは、不用品回収業者や産業廃棄物処理の専門業者に依頼するという選択肢もあります。特に引っ越しや遺品整理、大掃除などで大量の不用品が発生する際には、灯油だけでなくポリタンクやストーブ、古い灯油器具一式をまとめて処分してもらえる点もメリットです。
ただし、灯油は「危険物」に分類されるため、すべての不用品回収業者が対応しているわけではありません。依頼する前に、「灯油の回収が可能かどうか」「回収後の処分方法はどのようになっているか」などをしっかり確認し、信頼できる許可業者かどうかを見極めることが大切です。料金についても、見積もりを出してもらい、不明瞭な点がないかをチェックすることがトラブル回避につながります。
また、業者によってはポリタンクのみの回収や、灯油入りのタンクは対応不可としているところもあるため、具体的な内容を説明し、引き受けてもらえるか事前に打ち合わせることが必要です。
灯油の処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は灯油の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
灯油を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!