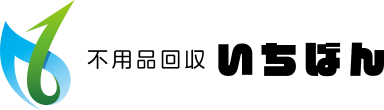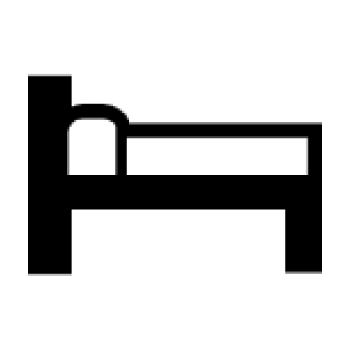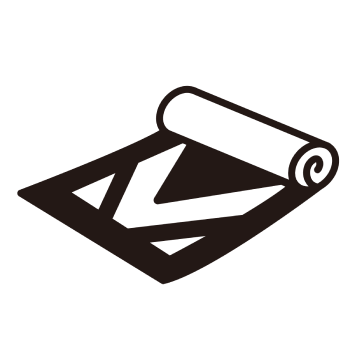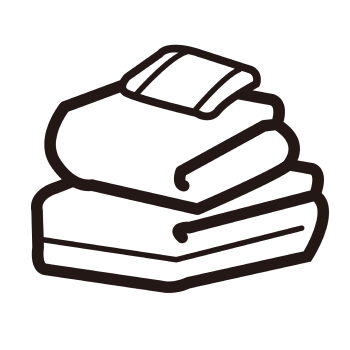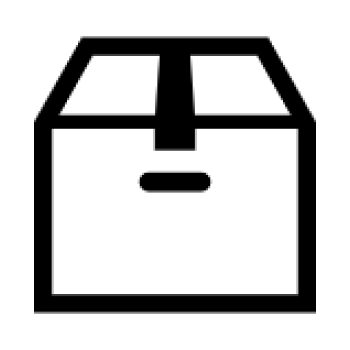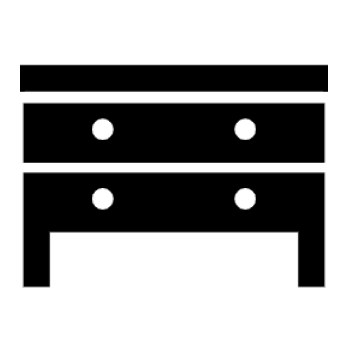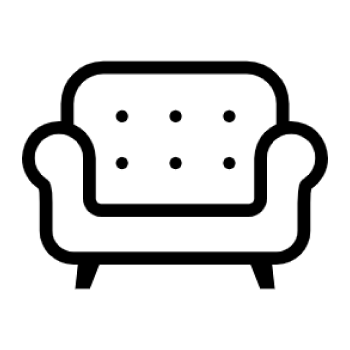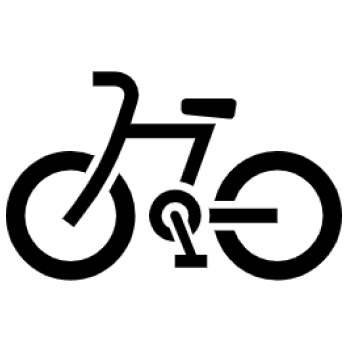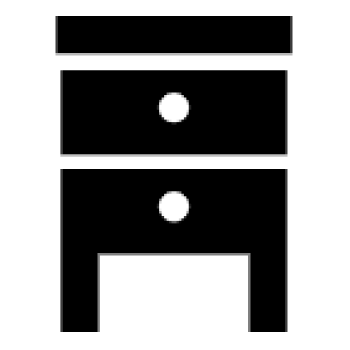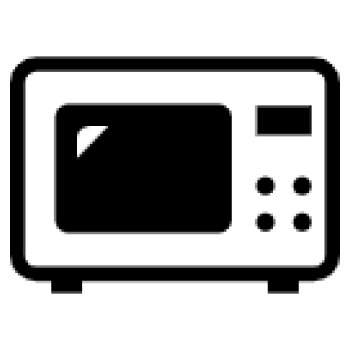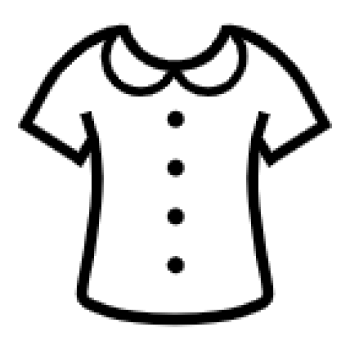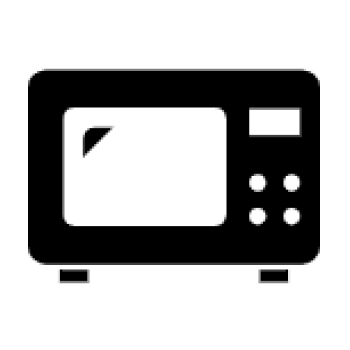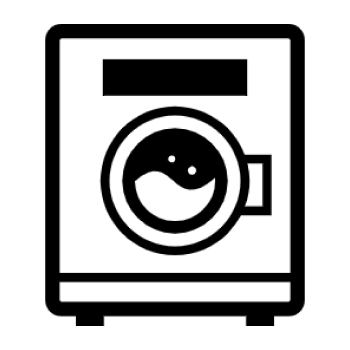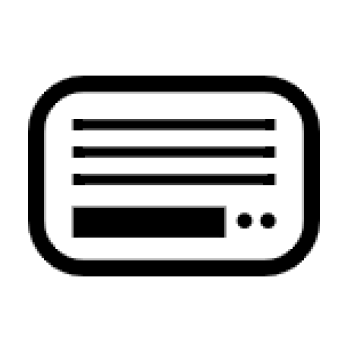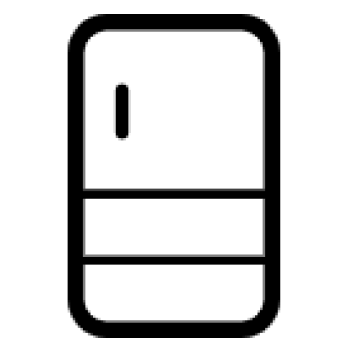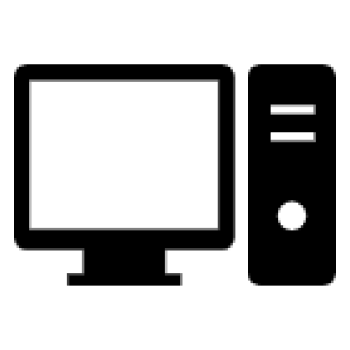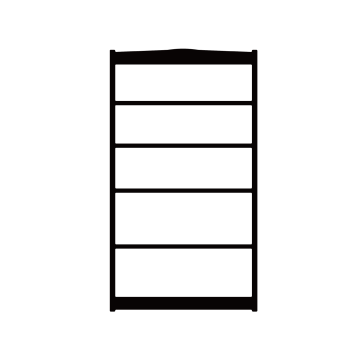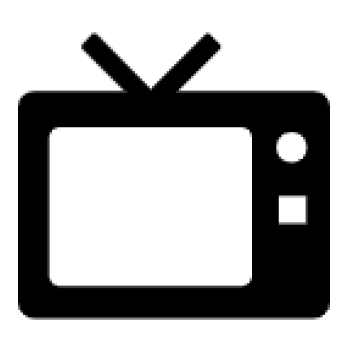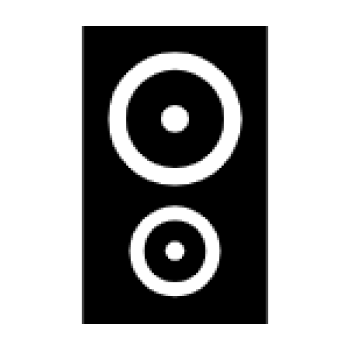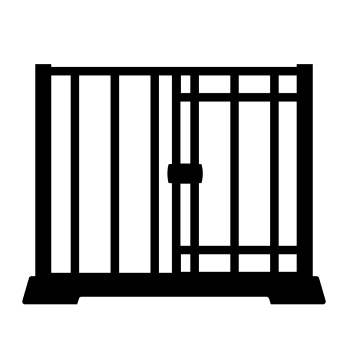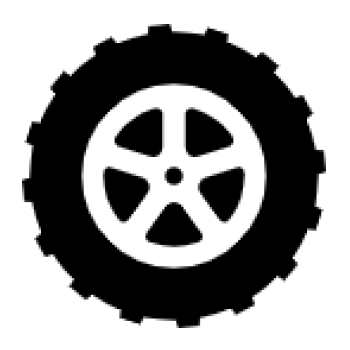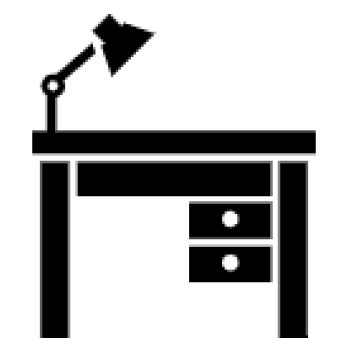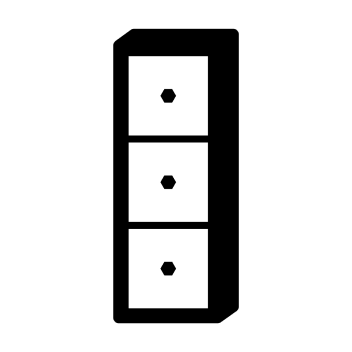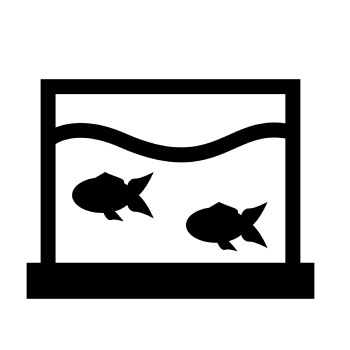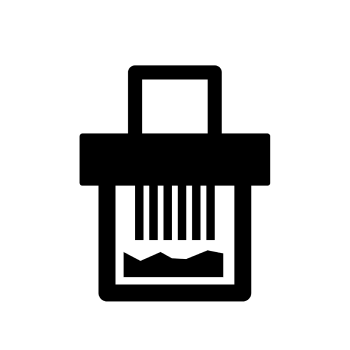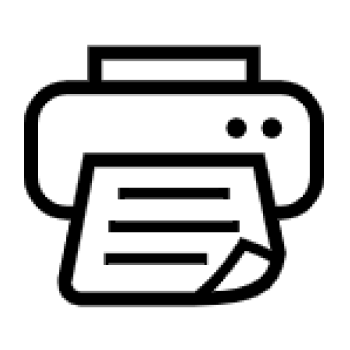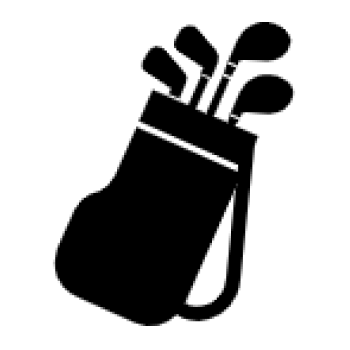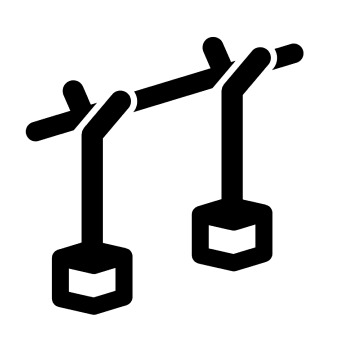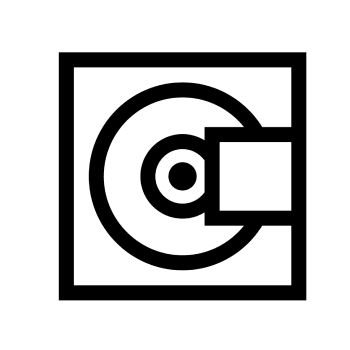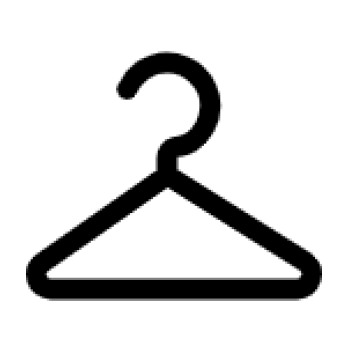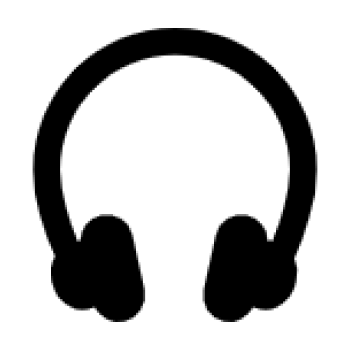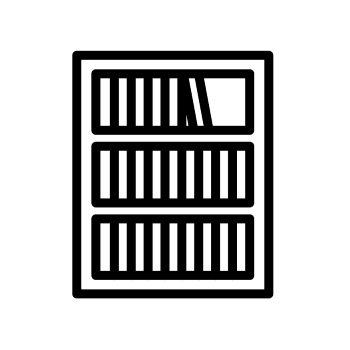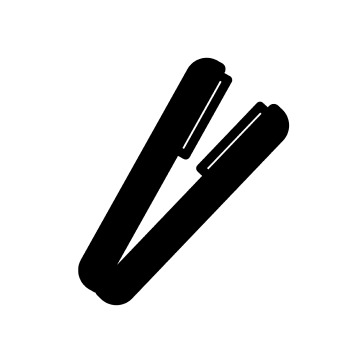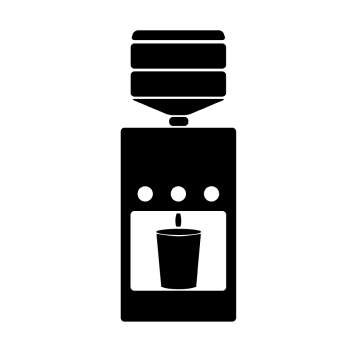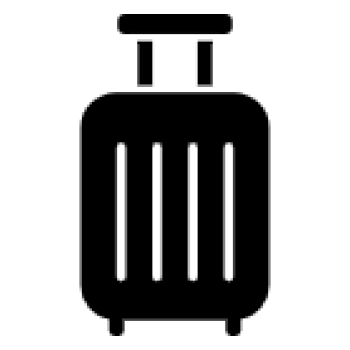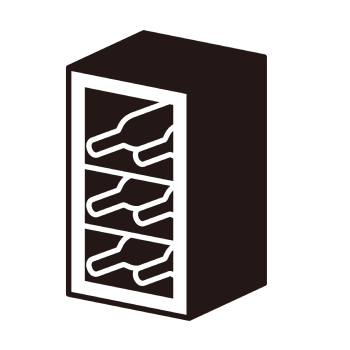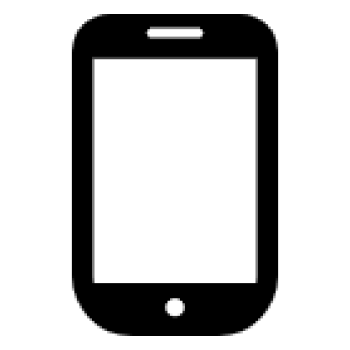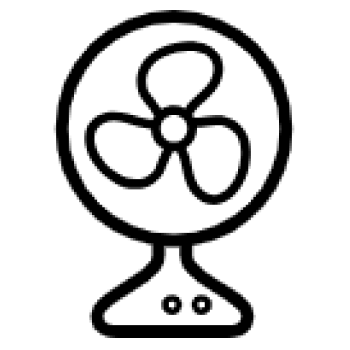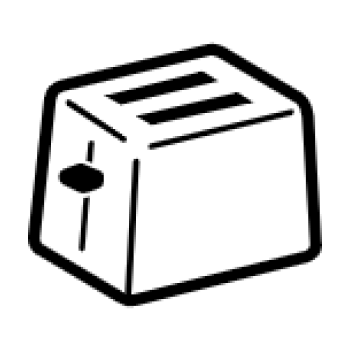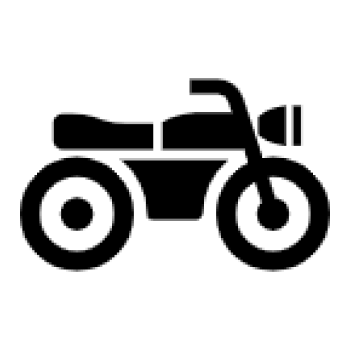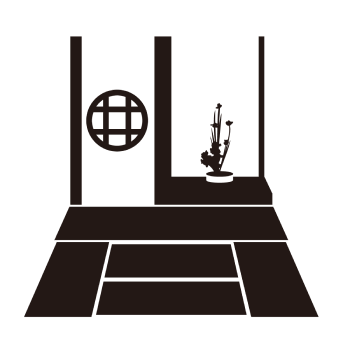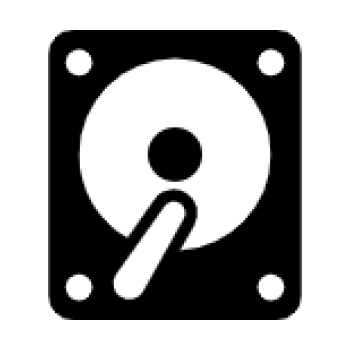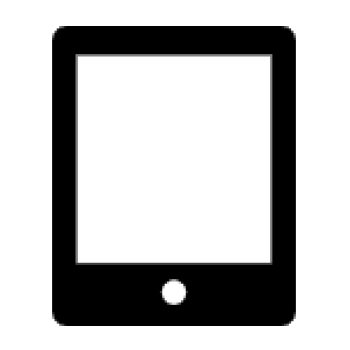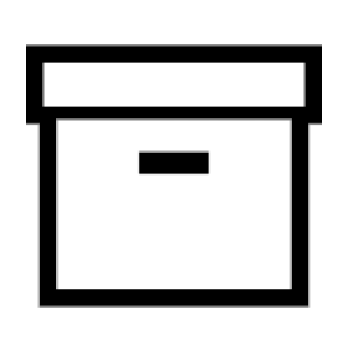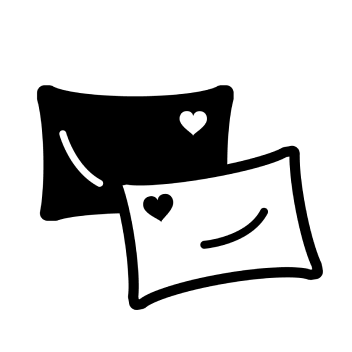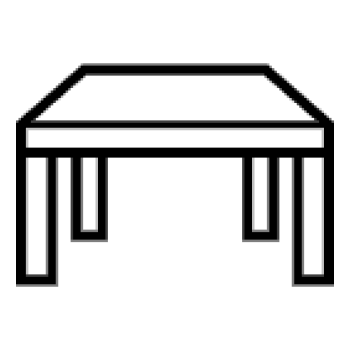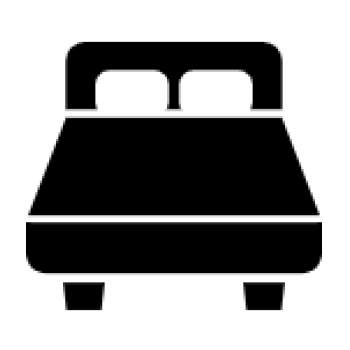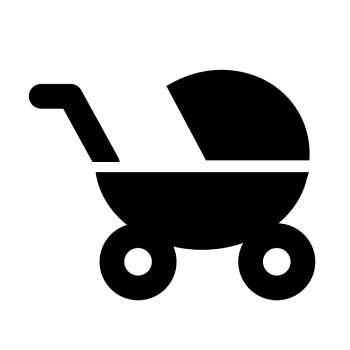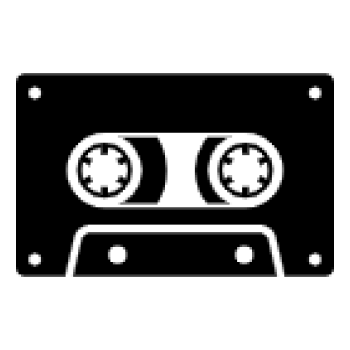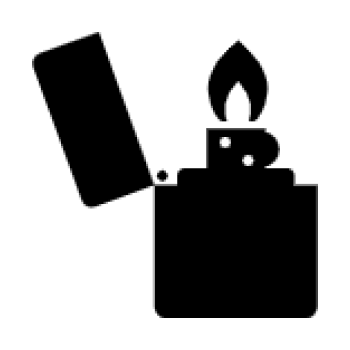「片付けなきゃと思っているのに、どうしても手がつけられない」「いつか使うかもしれないと思って、物が捨てられない」。こうした思いに心当たりがある方は、もしかすると“ためこみ症(ホーディング障害)”という状態に陥っているかもしれません。ただ散らかっている、だらしないといった一般的なイメージとは異なり、ためこみ症はれっきとした心の病の一つです。「物が多すぎて部屋に入れない」「ゴミの山に囲まれて生活している」といった状態に悩んでいても、それを誰にも打ち明けられず、一人で抱え込んでしまっている人も少なくありません。
ためこみ症の根底には、過去の喪失体験や不安、強い執着心、あるいは自己肯定感の低さが関係していることが多いと言われています。誰にでも起こりうる心の問題であり、「頑張れない自分が悪い」と責める必要はまったくありません。このような状態を放置してしまうと、日常生活や健康に支障をきたす可能性もあるため、早めに対処することが大切です。
本記事では、ためこみ症の人が片付けに取り組むための考え方や、実際に効果的だったサポート方法、小さな一歩を踏み出すための工夫などを、やさしく丁寧にご紹介します。あなたが無理なく前に進むためのきっかけになれば幸いです。
ためこみ症とは?
ためこみ症とは、本人にとって不要であるにもかかわらず、物を捨てることができず過剰に物をため込んでしまう精神疾患です。単なる「物好き」や「片付けが苦手」とは異なり、精神医学の世界ではアメリカ精神医学会の『精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)』において「強迫性障害スペクトラム」の一部として正式に認められています。ためこみ症は、自分の意思だけで物を処分できない状態が続き、生活空間が物で埋まってしまうことで日常生活に支障をきたします。心理的な葛藤が根深く、本人は物を手放したい気持ちがあっても、不安や恐怖感がそれを阻みます。そのため、ためこみ症は本人の努力や気合だけでは改善が難しく、専門的な治療や支援が必要となる病気です。
ためこみ症の特徴と原因
ためこみ症の特徴は、「いつか使うかもしれない」「思い出が詰まっている」「捨てると何か悪いことが起きそう」という思考に支配され、物を手放せなくなることです。こうした思考パターンは、単なる「物好き」や「収集癖」とは明確に異なり、本人の感情的な不安や執着に深く結びついています。ためこみ症の原因には、遺伝的な要素や脳の機能異常、ストレスやトラウマなどの環境的要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
また、他の精神疾患、例えばうつ病や不安障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)との関連性も指摘されています。結果として、本人は物をため込む行為に安心感や安心材料を見出すことも多く、捨てることへの恐怖心や不安感が強まるため、行動がエスカレートしていきます。
ためこみ症がもたらす生活への影響
ためこみ症は生活空間の著しい乱れを引き起こすだけでなく、衛生面や安全面でのリスクも高まります。物が積み重なり動線が塞がれることで、掃除や調理、入浴といった基本的な生活行為が困難になり、生活の質が著しく低下します。特に、ゴミや不要物が溜まることで、カビや害虫の発生リスクが増加し、アレルギーや感染症の原因となる場合も少なくありません。
また、避難経路が物で塞がれていると火災時や災害時の危険が増大し、本人や家族の命にかかわる問題にもなります。さらに、家族関係や近隣住民とのトラブルが起こりやすく、社会的孤立や精神的ストレスの悪循環に陥ることも多いのが特徴です。こうした影響は本人だけでなく周囲にも大きな負担を与えるため、ためこみ症の理解と対応が重要視されています。
ためこみ症と「片付けられない性格」との違い
ためこみ症とよく混同されがちな「片付けられない性格」や「単なる整理整頓の苦手さ」との違いは、本人の心理的な葛藤の深さと行動の制御困難さにあります。
片付けが苦手な人は、単に習慣や性格の問題であり、本人の意志次第で改善が見込めることが多いです。しかし、ためこみ症の場合は、本人が物を捨てたいと強く思っても、不安感や恐怖感がそれを阻み、実際の行動に移すことができません。これは精神的な病気であり、単なる性格の問題ではないため、専門的な診断と治療が必要になります。ためこみ症では、心理療法や認知行動療法が効果的とされ、場合によっては薬物療法も併用されます。周囲の理解や支援も不可欠で、単なる「怠け」や「性格の問題」として片付けてしまうのは誤りです。
ためこみ症の人が整理できない理由とは?
「捨てる」ことへの強い不安
ためこみ症の大きな特徴のひとつは、「物を捨てることに対する過度な不安」です。たとえその物が明らかに不要であっても、「いつか使うかもしれない」「捨ててしまったら後悔するかもしれない」「失ったら自分の一部がなくなるような気がする」といった強い感情が湧き上がります。これは単なる性格的な傾向ではなく、脳の中で「捨てる=危険」という認識が形成されているためです。その結果として、物を手放す行為が極度にストレスとなり、避けようとする反応が出てしまいます。
また、「捨てる決断」に伴う不安は、時間が経っても薄れにくく、繰り返し同じ葛藤を感じることがあります。そのため、ためこみ症の人にとっては、「物を捨てる」という行為そのものが心理的なハードルとなり、整理整頓が困難になるのです。
思考の偏りと感情的な結びつき
ためこみ症の人は、物に対する「認知の歪み」や「感情的な結びつき」が非常に強い傾向があります。たとえば、古いチラシや使いかけのペンなど、他人から見れば明らかに不要なものにも「思い出が詰まっている」「自分の一部のように感じる」などの意味づけをしてしまうことがあります。このように、物に対して過剰に個人的な価値を見出してしまうと、合理的な判断ができなくなり、整理しようとしても感情的なブレーキがかかります。
また、「完璧に片付けなければ意味がない」「一度失った物は二度と取り戻せない」といった極端な思考パターンが働くこともあり、結果的に行動を起こせなくなります。これらの思考の偏りは、本人にとっては「当たり前」に感じられるため、外部から指摘されても納得できず、改善が難しいという特徴があります。
他の精神疾患との関係性
ためこみ症は、単独で存在することもありますが、多くの場合、他の精神疾患との併発が見られます。特に注意欠如・多動症(ADHD)やうつ病、強迫性障害(OCD)などとの関連が深いです。ADHDの人は注意力の欠如や計画性の弱さから、物の整理が極めて苦手です。何をどこにしまうべきか、どれを残してどれを捨てるべきかという判断ができず、気がついたら物が積み重なっているという状態に陥ります。
また、うつ病の人は意欲の低下により、そもそも片付けの行動を始める気力すらわかないことが多く、物が溜まる一方になります。強迫性障害の傾向を持つ人は、捨てることによる不安や罪悪感が強く、それを回避するために「捨てない」という選択を繰り返してしまいます。つまり、ためこみ症の背景には、思考力・判断力・感情コントロールの問題が複雑に絡み合っているのです。
強迫性障害(OCD)との関係
ためこみ症は、強迫性障害(OCD)と深い関連があります。OCDでは、本人が不合理と理解していても、不安や恐怖を打ち消すために、手洗いや確認行為などの反復的な行動を取る傾向があります。ためこみ症も同様に、「物を捨てたら何か悪いことが起こるかもしれない」「捨てたことで後悔するのではないか」といった強迫的な思考が現れます。その結果、物が不要とわかっていても手放すことができず、生活空間が次第に物であふれてしまいます。
DSM-5では、ためこみ症はOCDとは別の診断カテゴリとされていますが、臨床的には両者が併存している例は少なくありません。また、OCDを治療中にためこみ行動が顕在化することもあり、正確な診断と柔軟な治療方針が求められます。
ADHD(注意欠如・多動症)との関係
ADHD(注意欠如・多動症)とためこみ症の関係も、近年の研究で注目されています。ADHDの人は、注意の持続が難しく、計画的に行動することが苦手な傾向にあります。このため、物の整理整頓がうまくできず、「あとで使うかも」「今は片付けられない」といった理由で物を放置しやすくなります。結果的に、意図せず物が増えてしまい、ためこみ症に近い状態に陥ることがあります。
また、ADHD特有の衝動性により、不要な物を衝動買いしてしまうこともあり、それが物の蓄積を加速させる要因になります。ためこみ行動の背景に、OCDのような「不安回避」ではなく、「整理ができない」という実行機能の弱さがある点がADHD由来の特徴です。ADHDの診断と支援が的確に行われないまま、単に「だらしない性格」などと誤解されるケースも多く、周囲の理解も不可欠です。
うつ病との併発
ためこみ症は、うつ病と併発するケースもよく見られます。うつ病になると、気分の落ち込み、無気力、思考力や判断力の低下が生じ、日常的なタスクをこなすことが困難になります。掃除や片付けといった行為もその例外ではなく、「やらなければ」と思っていても実行できず、結果的に物がたまり、部屋が散らかっていきます。また、ため込んだ状態そのものが自己評価の低下や罪悪感をさらに悪化させ、うつ状態を悪循環的に深めてしまうことも少なくありません。
特に高齢者では、加齢にともなう身体機能の低下や孤立、認知機能の衰えなどが影響し、うつ病とともにためこみ症の傾向が進行することもあります。こうした場合、片付けや整理の支援と同時に、うつ病への治療的アプローチが必要になります。
他の併発例(不安障害・統合失調症・認知症など)
ためこみ症は、OCDやADHD、うつ病以外にも、さまざまな精神疾患と併存することがあります。たとえば、不安障害の一種である全般性不安障害(GAD)では、「いつか必要になるかもしれない」「捨てた後で困るかもしれない」という過度の心配から物を手放せない傾向が強まります。また、統合失調症では、妄想的な思考や現実認識の歪みにより、ゴミや使い道のない物であっても特別な意味があると感じ、ため込むことがあります。
認知症が進行している高齢者においても、過去の記憶や感情が強く結びついた物を処分できずにため込むケースが見られます。これらの背景には、物への執着や不安、混乱といった複雑な心理的要素が関係しており、単なる「習慣」や「性格」で説明できるものではありません。精神疾患の症状としてのためこみ行動は、それぞれに応じた専門的なアプローチが必要です。
具体的な改善方法
1日1か所、スモールステップで進める
ためこみ症の人にとって、いきなり「部屋全体を片付けよう」とするのは現実的ではありません。大切なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。たとえば、「今日は机の上の左端だけ」「引き出し1段目だけ」など、明確に限定された範囲から始めることで、心理的な負担を大きく軽減できます。また、小さな範囲でも実際に片付いた状態を見ることで、達成感や満足感が得られ、それが次の行動の原動力になります。
人によっては、タイマーを使って「10分だけ片付ける」など時間を決めて取り組む方法も効果的です。大切なのは、「今日は少しでもできた」という実感を持つこと。目標を低めに設定して取り組むことで、継続しやすくなり、やがて習慣化することが可能です。
「捨てられない理由」を紙に書き出して整理
物を捨てられないときは、頭の中で不安や葛藤が渦巻いている状態です。それを整理するためには、思考を「見える化」するのが有効です。具体的には、「なぜこの物を捨てられないのか?」を紙に書き出してみましょう。たとえば「高かったから」「もらい物だから罪悪感がある」「使えるかもしれない」といった理由が出てくるはずです。
書き出すことで、自分がどういう心理的背景で物を手放せないのかが見えてきます。そして、「本当に今の自分に必要か?」「この先使う可能性はどのくらいあるか?」といった問いかけを通して、自分の中で物との関係を客観的に見直すきっかけにもなります。感情に左右されすぎないためにも、「書いて整理する」という作業は非常に効果的です。
仕分けルール(キープ/保留/処分)を設定する
いざ片付けを始めようと思っても、ひとつひとつの物に迷ってしまってなかなか進まない、ということはよくあります。そこで役立つのが「仕分けの3分類ルール」です。これは、手に取った物を「キープ(保管)」「保留」「処分」の3つに分けるシンプルな方法です。「キープ」は絶対に必要な物、「処分」は明らかに不要な物、そして「保留」は捨てるか迷っている物です。
保留にした物は一時的に箱にまとめ、一定期間(例:1か月)使わなければ処分するといったルールを設けることで、判断を先送りしすぎず、かつ急激な不安を回避できます。また、この3分類法は視覚的にも進捗がわかりやすく、モチベーション維持にもつながります。ためこみ症の人にとって、明確な「ルール」があることは安心材料となり、片付けのハードルを下げる効果があります。
視覚的な成果を残す:写真で「ビフォー・アフター」
片付けを進めていく過程で、成果を「見える形」で記録しておくことは非常に大切です。おすすめなのが、片付け前と片付け後の写真を撮ることです。写真で比較すると、「こんなに変わったんだ」という実感が明確になり、自信や達成感が生まれます。また、片付けた状態を維持しようという意欲も高まります。
ためこみ症の人は、「変化に対する不安」を抱えていることが多いため、写真という記録は安心材料にもなります。「片付けてもまた散らかるのでは」といった不安があるときも、写真を見ることで「自分にもできた」という証拠になり、次の行動への後押しとなります。スマートフォンなどで気軽に記録できるので、習慣化するとモチベーション維持にも役立ちます。
第三者の手を借りる:専門家や信頼できる人と一緒に取り組む
ためこみ症の人にとって、片付けは単なる家事や整理整頓ではなく、強い不安や葛藤を伴う「精神的な戦い」です。そのため、一人で乗り越えようとすると挫折しやすく、むしろ事態を悪化させてしまうことさえあります。そこで有効なのが、第三者の手を借りることです。たとえば、家族や信頼できる友人に一緒に片付けを手伝ってもらうだけでも、心理的な負担は大きく軽減されます。外からの視点で「これは本当に必要?」と問いかけてもらうことで、物に対する客観的な判断がしやすくなります。
また、専門的な知識と経験を持つ「片付けコンサルタント」や「整理収納アドバイザー」、そして「不用品回収業者」や「心理カウンセラー」に依頼するのも効果的です。彼らは、ためこみ症特有の心理に理解を持ったうえで対応してくれるため、安心して任せることができます。特に、心の問題が深く関係している場合は、カウンセラーと連携しながら片付けを進めるのが望ましいでしょう。
重要なのは、「自力でなんとかしなければならない」と思い詰めないことです。第三者の存在は、否定や強制ではなく「伴走者」として、自分のペースで整理を進める手助けをしてくれる存在です。誰かと一緒に進めることで、片付けに対する抵抗感が和らぎ、一歩を踏み出す勇気にもつながります。
部屋の片付けでお悩みの方、不用品回収いちばんがお手伝いいたします!
部屋の片付けを行うにあたり、なにをどうすればいいかわからない、誰かに手伝ってほしいという状況になった際は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収いちばんは、あなたに寄り添った片付け方の提案をさせていただきます。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!