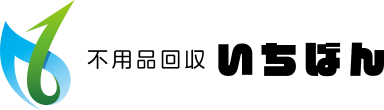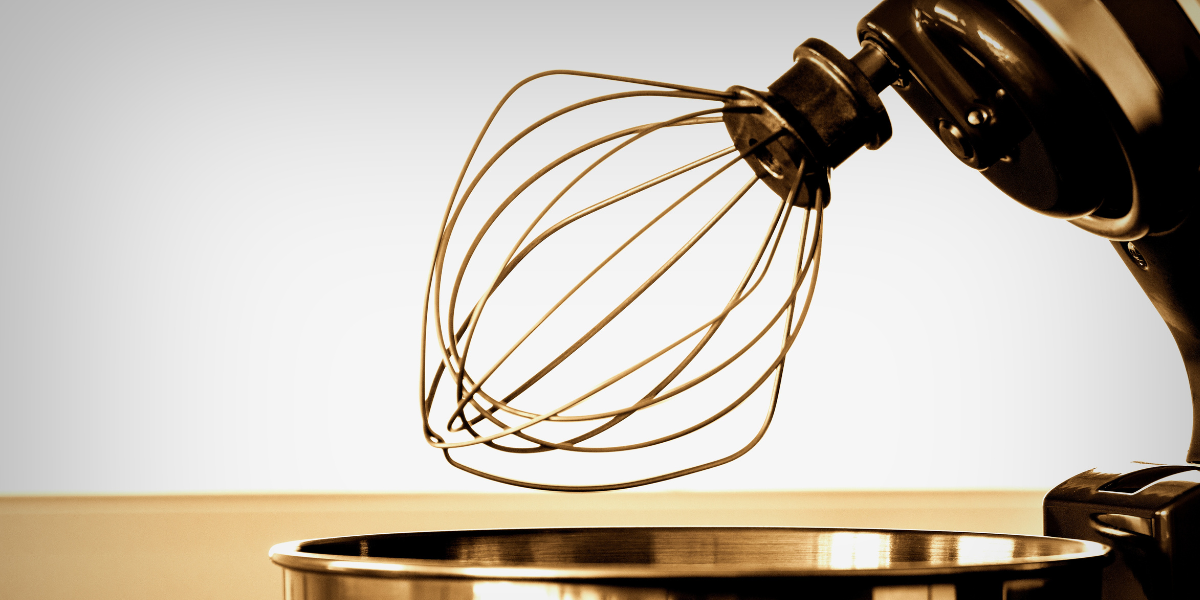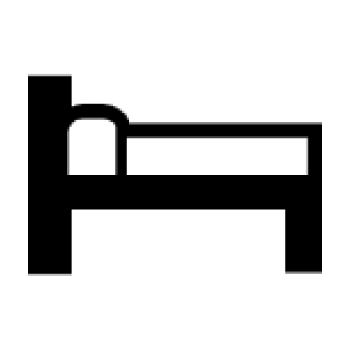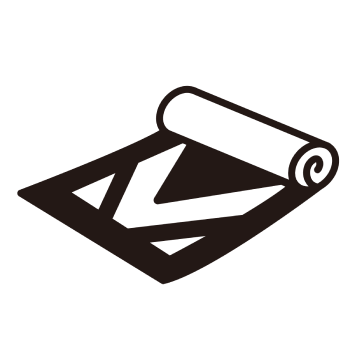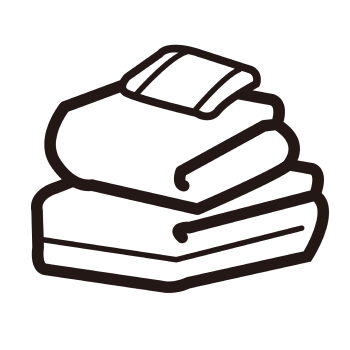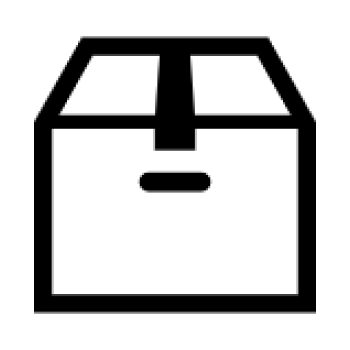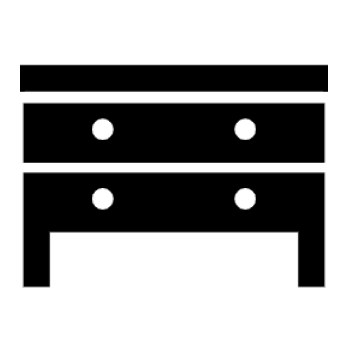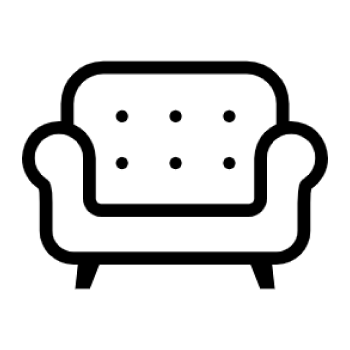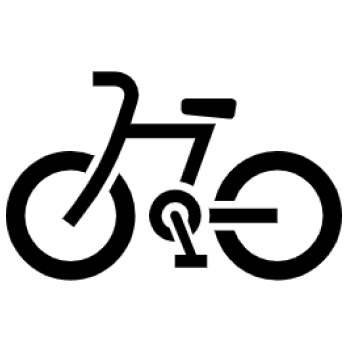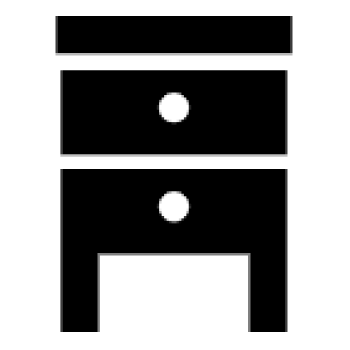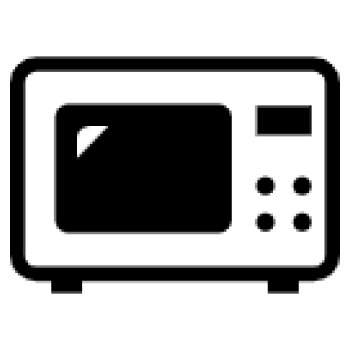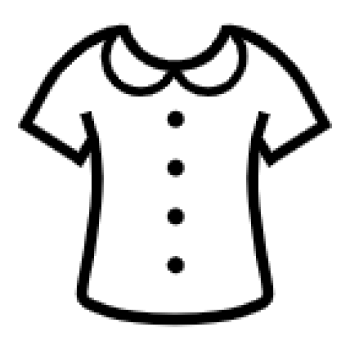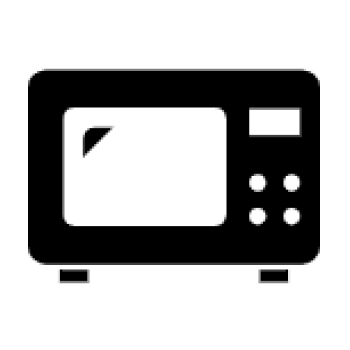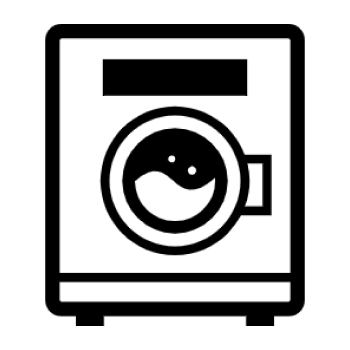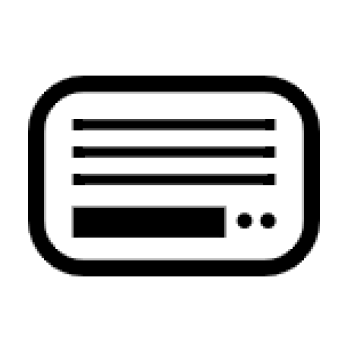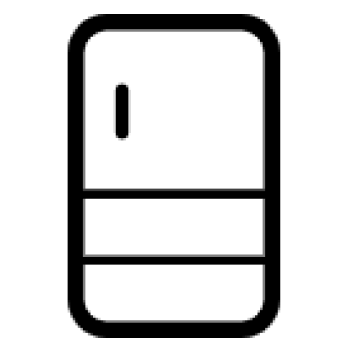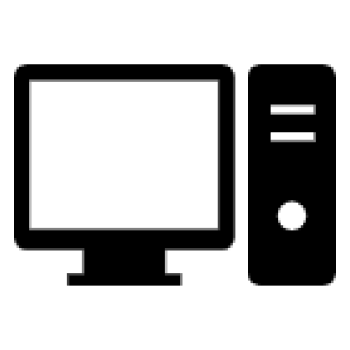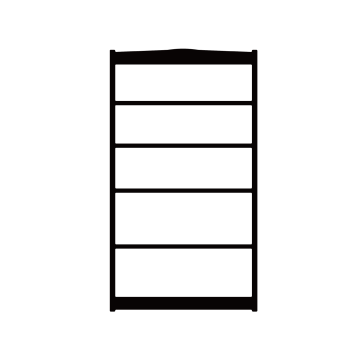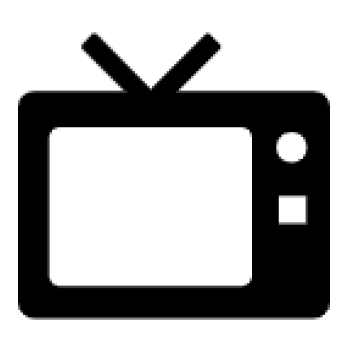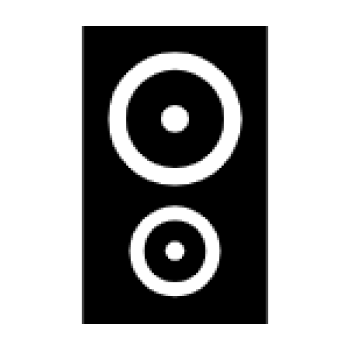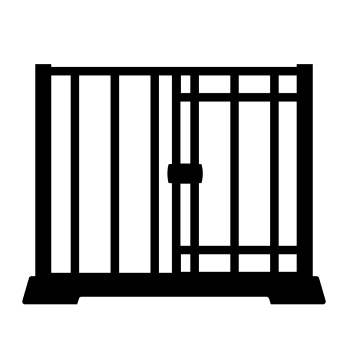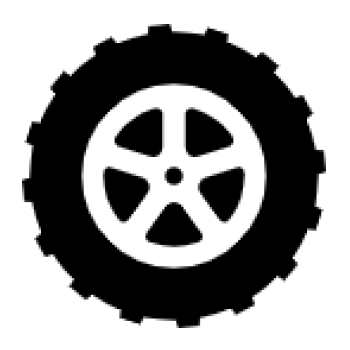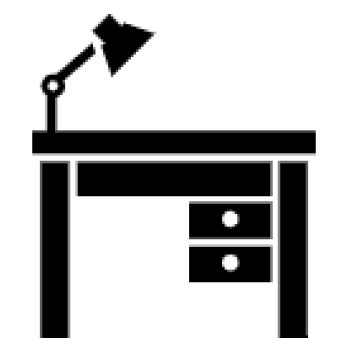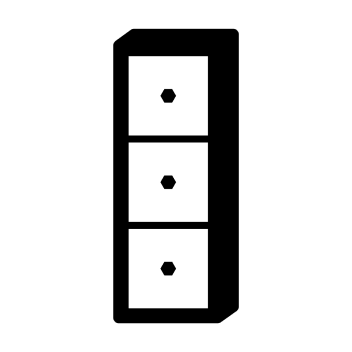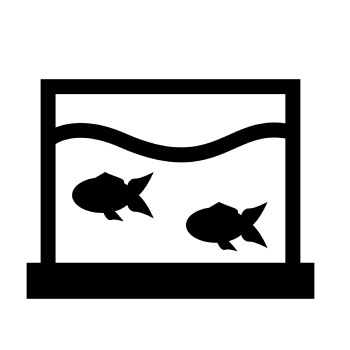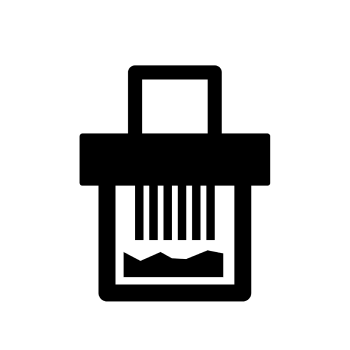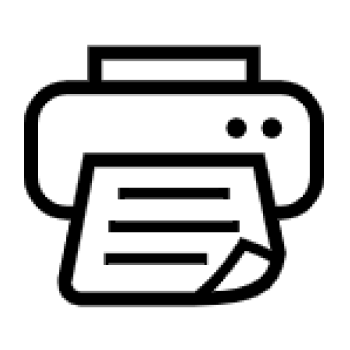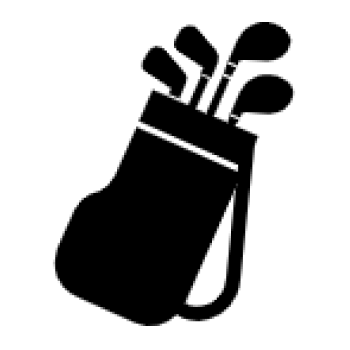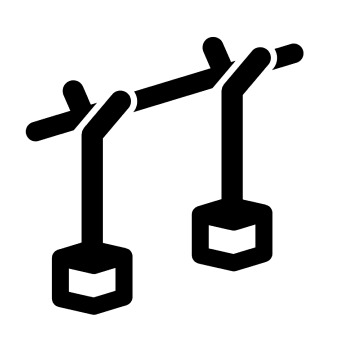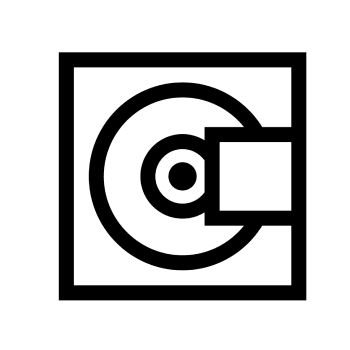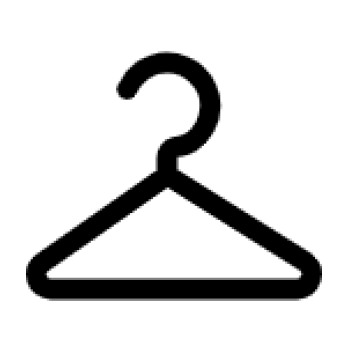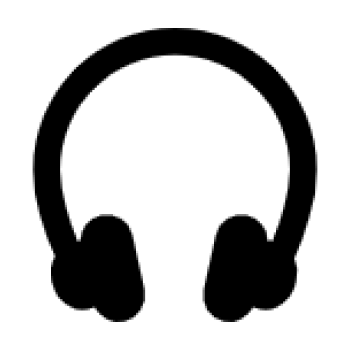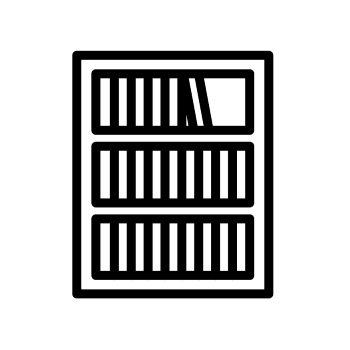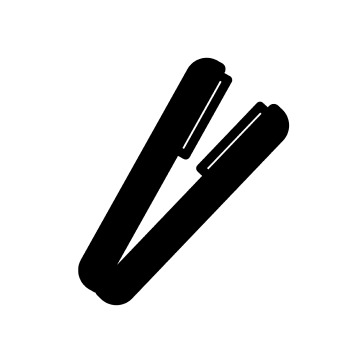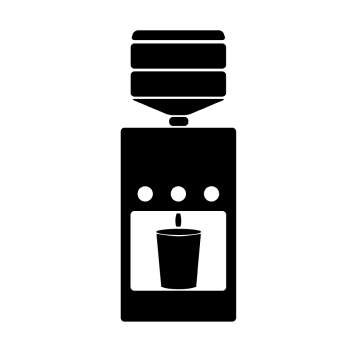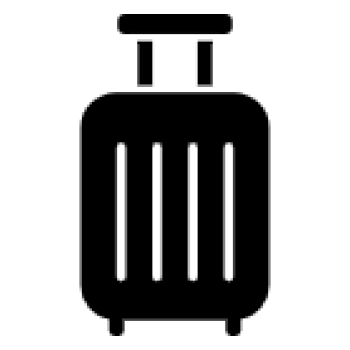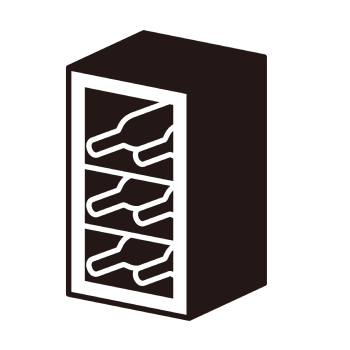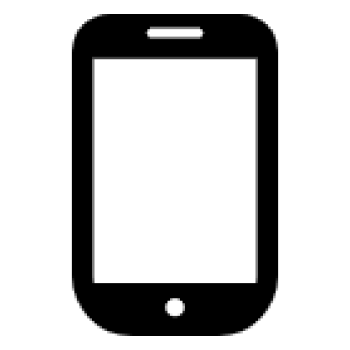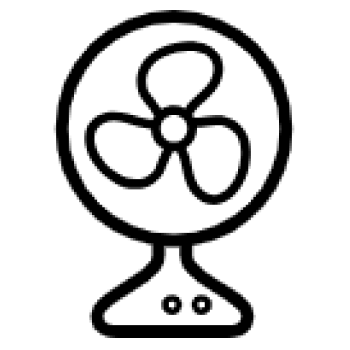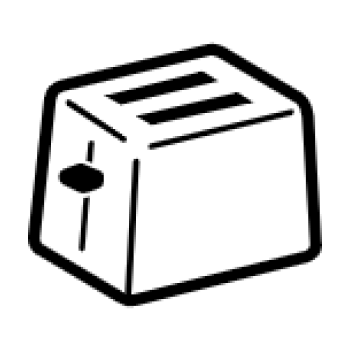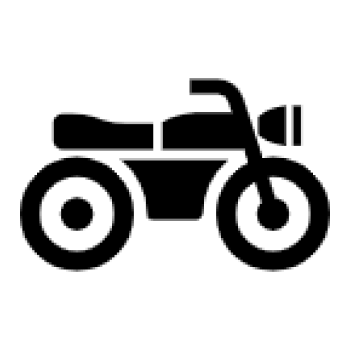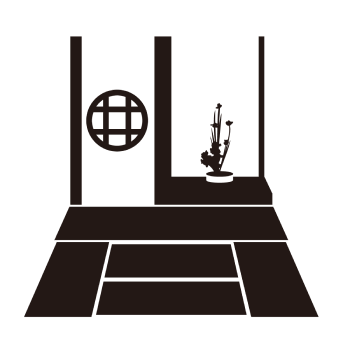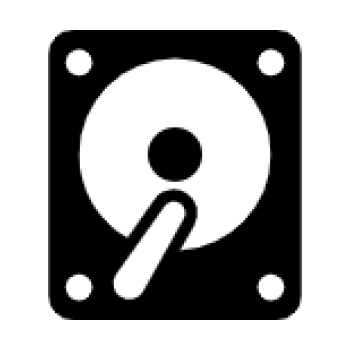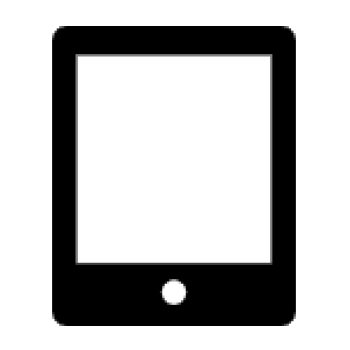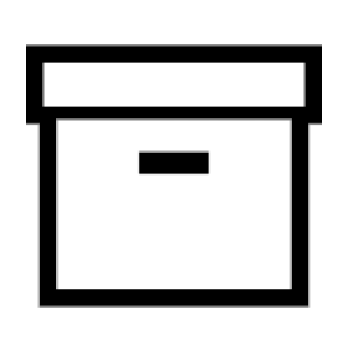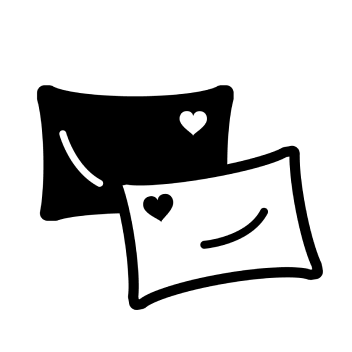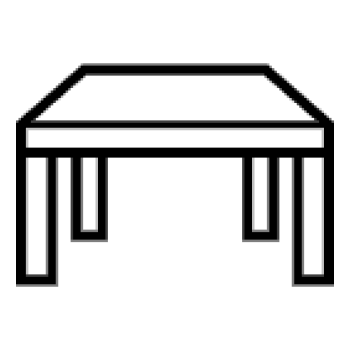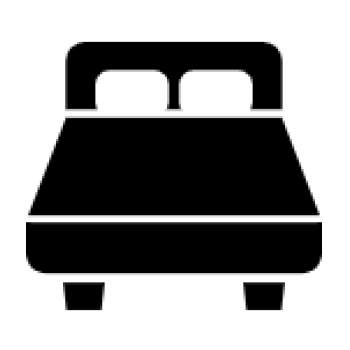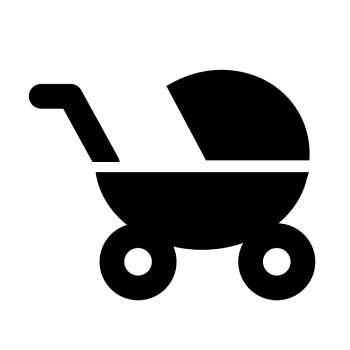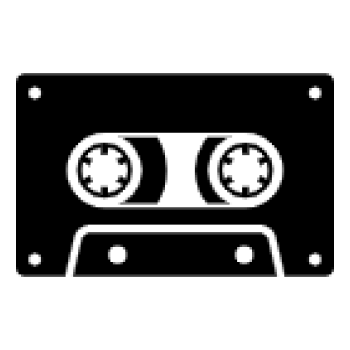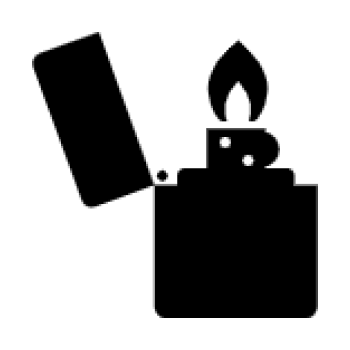キッチン家電の中でも手軽に使える調理器具として、多くの家庭で活躍しているのが「ハンドミキサー」です。ホイップクリーム作りやメレンゲの泡立て、パンやお菓子作りの生地づくりなど、手作業では時間のかかる工程をスピーディーに仕上げられるため、料理初心者からベテランの方まで幅広く支持されています。しかし、毎日のように使うものではないからこそ、久しぶりに出して使おうとした際に「動かない」「異音がする」「コードが裂けている」などのトラブルに気づくことも少なくありません。
そうしたとき、ふと頭をよぎるのが「これ、どうやって処分すればいいの?」という疑問です。小さな電化製品であるハンドミキサーは、燃えないごみなのか、それとも粗大ごみか、あるいはリサイクルできるのか判断に迷うこともあります。また、処分するにしても費用がかかるのか、どこに持っていけばよいのか、実は正しい情報を知らないまま適当に処分してしまうケースも少なくありません。
本記事では、そんな疑問や不安を解消するために、ハンドミキサーの正しい処分方法を分かりやすくご紹介します。また、できるだけ長く快適に使い続けるためのコツについても併せて解説します。キッチン家電を安全に、そして効率よく使いこなすために、ぜひ最後までご覧ください。
ハンドミキサーを処分するタイミングは?
ハンドミキサーは長く使えるキッチン家電ですが、使用環境や頻度によって劣化のスピードは異なります。安全に使い続けるためには、故障や劣化の兆候を見逃さず、適切なタイミングで処分することが大切です。以下に具体的な判断基準を解説します。
モーター音が異常に大きくなったとき
通常運転時と比べて、モーター音が「ゴーッ」「ウィーン」といった大きな異音を発するようになった場合は、内部の摩耗や潤滑不足が原因であることが考えられます。特に異音が断続的に続く場合や、音の変化が急に起こった場合は、モーターそのものの劣化や電気系統のトラブルが起きている可能性が高いです。
無理に使用を続けると、内部部品が破損して本体の発煙やショートにつながる危険もあります。音の違和感は早期の劣化サインとして見逃せないポイントです。修理対応ができない古いモデルであれば、買い替え・処分を検討しましょう。
ビーター(金属部分)のがたつきや欠けがあるとき
ビーター部分にがたつきが生じたり、接続部の金属に欠けや変形が見られる場合も、処分を検討するサインです。がたつきがあると混ぜる際の回転にムラが出て、十分な泡立てができなかったり、使用中に外れて飛び出す危険があります。
また、金属の欠けは衛生面の問題にもつながります。料理中に小さな破片が混入してしまうと、思わぬ事故や体調不良の原因にもなりかねません。特に長年使用した製品では、摩耗や腐食による劣化が進行している場合があるため、安全を最優先に考え、劣化が目立つ場合は潔く処分を選びましょう。
電源が入らない、すぐ止まるとき
スイッチを入れてもまったく反応しない、または動いてもすぐに止まってしまうといった症状は、内部の電気配線の断線やモーターの故障が疑われます。コンセントや電源コードに問題がある場合もありますが、それを確認してもなお改善しない場合は、本体内部の不具合と判断できます。
電源トラブルは感電や火花などの危険を伴うため、むやみに分解して自己修理を試みるのは避けましょう。修理保証期間外であれば、修理コストより新品の購入が現実的なケースも多いため、安全性と費用対効果を天秤にかけて、処分を選ぶのが賢明です。
本体が熱を持ちすぎるとき
ハンドミキサー使用中に本体が極端に熱くなる場合、内部の冷却が不十分になっている可能性があります。これはモーターの劣化や異常な摩擦、通気孔の詰まりが原因で、製品本来の設計を超えた負荷がかかっている証拠です。
長時間連続使用したわけでもないのに本体が熱を持つ場合は、故障のサインとして見逃せません。そのまま使用を続けると、過熱によって発煙や発火を引き起こすリスクがあるため、使用を中止して処分を検討しましょう。特に古い製品ほど放熱性能が落ちていることもあるため、定期的に本体の温度に注意を払いましょう。
使用から7年以上経過しているとき
電気製品には「設計上の標準使用期間」という考え方があり、多くの家庭用家電では5〜10年がひとつの目安となっています。ハンドミキサーも例外ではなく、製品によっては7〜8年を超えると内部部品の摩耗や絶縁の劣化が進み、発火やショートといった事故のリスクが高まります。
見た目がきれいで問題なさそうでも、内部では経年劣化が進んでいる可能性があります。製品本体や取扱説明書に「標準使用期間」の記載がある場合は、それを基準に買い替えを検討するのが望ましいです。家電は長く使うほどコストパフォーマンスが高いように見えますが、安全性には代えられません。
ハンドミキサーを処分する前に確認すべきポイント
ハンドミキサーを処分する前に、確認しておくべき重要なポイントがあります。無駄な出費や手間を省くだけでなく、思わぬ価値を見出すきっかけになるかもしれません。以下の項目を一つずつチェックしてみましょう。
保証期間が残っていないか確認する
まず最初に確認したいのは、購入日と保証期間です。多くのハンドミキサーには1年間程度のメーカー保証がついています。購入から1年以内であれば、故障していても無料で修理や交換をしてもらえる可能性があります。
保証書やレシート、購入記録(ネット注文の場合はメールやマイページ)を確認し、保証期間内かどうかをチェックしましょう。保証対象内であれば、処分せずにまずはメーカーに相談するのが賢明です。
修理可能かメーカーや販売店に問い合わせる
使用年数が長く保証が切れている場合でも、メーカーや販売店が修理対応を行っていることがあります。軽微な故障やパーツの劣化であれば、有償修理で使い続けられるケースも多くあります。
特に、高機能モデルや海外ブランドの製品は、修理して使う方が長期的に見て経済的な場合もあります。修理が可能かどうかは、メーカーのカスタマーセンターや公式サイトから確認できるので、処分を決断する前に一度問い合わせてみましょう。
リコール対象製品でないか調べる
意外と見落としがちなのが、製品がリコール対象になっていないかの確認です。特定のロットで発煙・発火などの不具合が確認され、メーカーが自主回収している可能性があります。リコール対象であれば、無償で修理や交換、場合によっては返金対応してもらえることもあるため、処分するのは非常にもったいないことです。製品の型番・製造年を控えたうえで、メーカーの公式サイトや消費者庁のリコール情報を調べてみましょう。
付属品の有無をチェックする
ハンドミキサーをフリマアプリやリサイクルショップで売却しようと考えている場合は、元箱、取扱説明書、ビーターなどの付属品がそろっているかも確認ポイントです。これらがそろっていることで、買い手が見つかりやすくなり、販売価格も上がる傾向があります。特に人気ブランドや使用年数の浅いモデルであれば、再販価値が高まり、処分せずに「資源として再活用」できる可能性があります。状態が良い製品であれば、環境にも財布にも優しい選択肢です。
ハンドミキサーを長持ちさせるためのコツ
せっかく購入したハンドミキサー、できるだけ長く愛用したいものです。日々の使い方やお手入れの工夫次第で、寿命をぐっと延ばすことができます。以下のポイントを意識して、故障リスクを抑え、快適なキッチンライフを維持しましょう。
無理な連続運転を避ける
家庭用のハンドミキサーはコンパクトで手軽な反面、連続使用には限界があります。特にモーター部分は熱に弱く、長時間の連続運転により過熱しやすくなります。一般的には「10分以内の使用」を目安とし、それ以上使用したい場合は途中で休憩を挟み、冷却時間を確保することが大切です。
無理に連続稼働させるとモーターの焼き付きや内部パーツの摩耗が進み、結果として故障や性能低下を招いてしまいます。取扱説明書に記載された使用時間の上限を守り、丁寧に扱うことが長持ちの第一歩です。
使用後すぐに洗浄・乾燥する
調理後、ハンドミキサーのビーターやアタッチメント部分には、食品の残りが付着しています。これを放置してしまうと、腐敗やカビ、金属部分のサビの原因になります。特に、卵白や生クリームなどのたんぱく質は乾くと落ちにくくなり、雑菌の温床にもなりかねません。
使用後はすぐにぬるま湯で洗い、しっかり水分を拭き取ったあと、風通しの良い場所で完全に乾燥させてから収納しましょう。本体部分は濡れた布で軽く拭く程度にとどめ、内部に水分が入らないよう注意が必要です。
保管は湿気の少ない場所に
ハンドミキサーは電化製品であるため、湿気に非常に弱いという特性があります。特に日本のような高湿度の気候では、収納場所によってはカビやサビの原因になります。キッチンのシンク下や冷蔵庫の横など、水回りに近い場所に保管するのは避け、できるだけ湿気の少ない乾燥した場所で保管しましょう。
また、収納の際は本体とアタッチメントを分けて保管し、通気性のあるケースや布袋などに入れておくと、ホコリや湿気からも守ることができます。保管環境の見直しは、製品寿命を大きく左右します。
コードの巻き方にも注意する
収納時に多くの人がやりがちなのが、電源コードをきつく巻いてしまうことです。これは断線や接触不良の大きな原因となります。コードは内部に細い導線が何本も束ねられており、強く引っ張ったり折り曲げたりすることで少しずつダメージが蓄積していきます。
収納の際は、コードをゆったりと自然なカーブでまとめるようにし、ねじれや強い折り目がつかないよう配慮しましょう。また、コードを本体に巻き付けるタイプの製品であっても、無理に巻かず、適度な余裕をもたせるのが長持ちの秘訣です。
ハンドミキサーの処分方法5選
ハンドミキサーは小型で家庭的な電化製品であるため、処分方法は意外に選択肢が多くあります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に応じて最適な手段を選ぶことが大切です。以下に主な5つの方法を解説します。
自治体のごみ回収に出す
多くの自治体では、ハンドミキサーは「不燃ごみ」または「小型家電」として回収対象になっています。ただし、自治体によってはサイズや材質に応じて「粗大ごみ」に分類されることもあるため、注意が必要です。
不燃ごみとして出せる場合は、指定のごみ袋に入れて、決められた曜日に出すだけで済むため、最も手軽な方法と言えるでしょう。一方で、粗大ごみの場合は事前の申し込みや、処分シール(ごみ処理券)の購入が必要となり、回収日も限定されているため、ある程度の計画が必要です。
お住まいの地域の公式ホームページやごみ分別アプリを活用すれば、最新の分類と回収スケジュールが確認できます。手間を最小限にしたい方にとっては、この方法が最も現実的かつコストも抑えられる選択肢です。
家電量販店の回収ボックスを利用する
環境保護の観点から、家電量販店では使用済み小型家電の回収に積極的に取り組んでいます。店舗によっては、店頭に「小型家電リサイクル回収ボックス」が設置されており、ここにハンドミキサーを投函することで無料で処分できます。ただし、この回収ボックスには「入口サイズに入ること」が前提となっているため、特別に大きなハンドミキサーやコードがかさばるタイプは入らない可能性があります。
事前に設置店舗やサイズ制限を確認すると安心です。また、電池式のハンドミキサーなどは電池を抜いてから出す必要があります。こうしたボックスは回収後に適切なリサイクル処理が行われるため、環境にも配慮した方法としておすすめです。
フリマアプリやリサイクルショップで売却する
もしハンドミキサーがまだ動作可能で外見にも目立った傷がない場合は、処分ではなく「売却」を選ぶことで、資源の有効活用が可能です。特に人気メーカーの製品や、デザイン性の高いモデル、使用期間が短いものであれば、中古市場でも需要があります。
フリマアプリを使えば、スマートフォン一つで出品・販売まで完結でき、手軽に始められます。送料や梱包の手間はかかりますが、処分費用をかけずにお金が戻ってくるのは魅力的です。
一方で、リサイクルショップでは買取価格は低めになるものの、すぐに現金化できる利点があります。いずれにしても、取扱説明書や外箱、アタッチメントなどの付属品がそろっていれば、評価が上がり売却成功率も高まります。
購入先の引取サービスを利用する
家電を買い替える際に便利なのが、購入時の「旧製品引取サービス」です。大手家電量販店やネットショップでは、新しい製品を購入すると、不要になった旧モデルを同時に引き取ってくれるサービスを提供していることがあります。
このサービスは、持ち帰り時の回収や、宅配便による回収などが選べる場合もあり、非常に手軽です。引取は無料のこともありますが、中には数百円〜千円程度の手数料がかかる場合もあるため、購入時にオプションとして確認しておくと安心です。
特に大型家電をまとめて処分したいときや、引っ越しのタイミングには非常に便利な方法です。ハンドミキサーのような小型家電でも、買い替え時に不要品を引き取ってもらえるかは、店舗やサービスの内容により異なるため、事前確認が重要です。
不用品回収業者に依頼する
複数の不用品を一度に処分したい場合や、自宅まで回収に来てほしい場合には、不用品回収業者への依頼も選択肢の一つです。業者によっては、ハンドミキサー1点から回収してくれるところもあり、特に家具や大型家電と一緒にまとめて処分する際には効率的です。
料金は、回収品の量や距離、時間帯によって変動しますが、見積もりが明瞭な業者を選ぶことでトラブルを回避できます。悪質な業者による不当請求や不法投棄などの問題もあるため、口コミや実績を確認し、自治体からの認可を受けた業者を選ぶことが大切です。また、引越しシーズンや年末年始は混雑する傾向があるため、早めの予約もポイントです。
ハンドミキサーの処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回はハンドミキサーの処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
ハンドミキサーを処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!