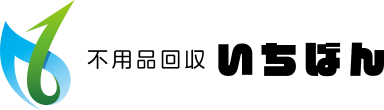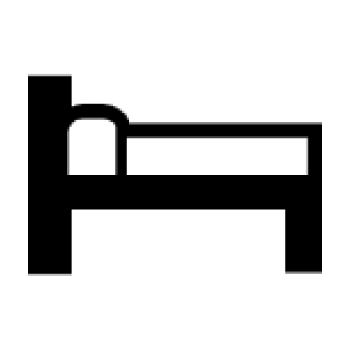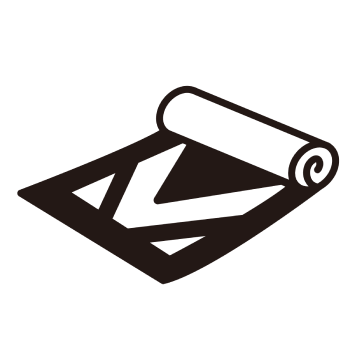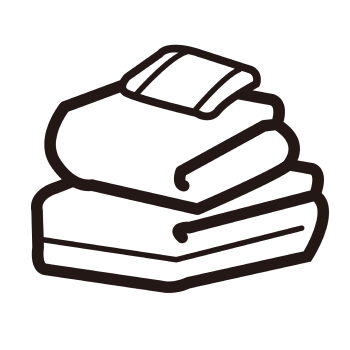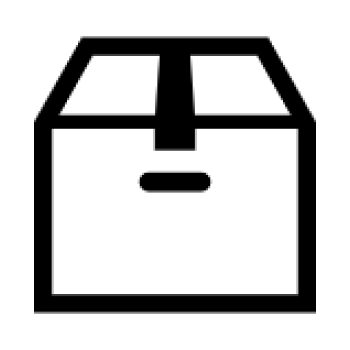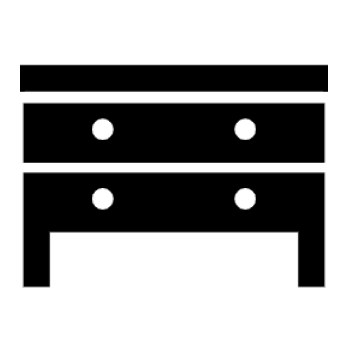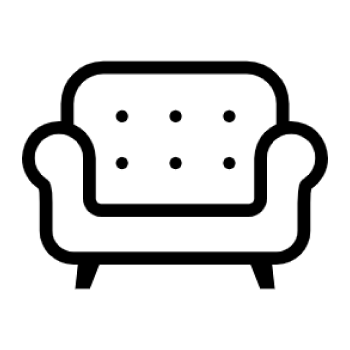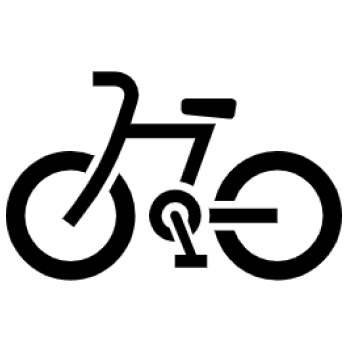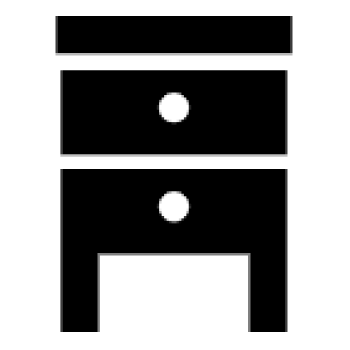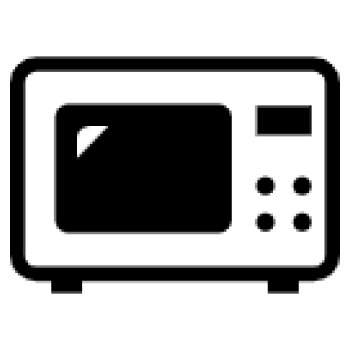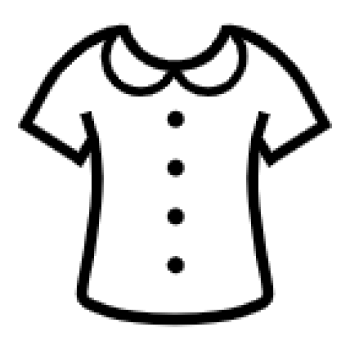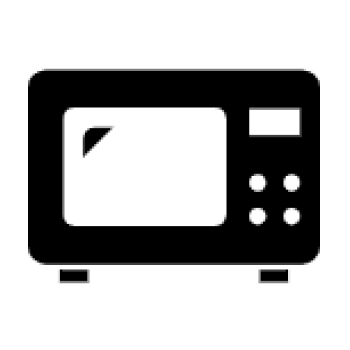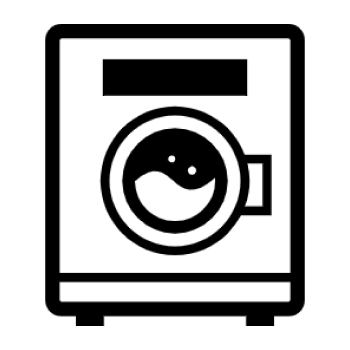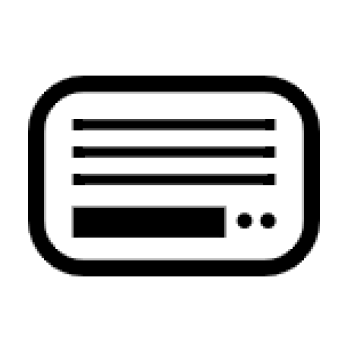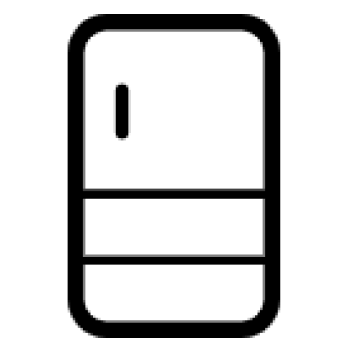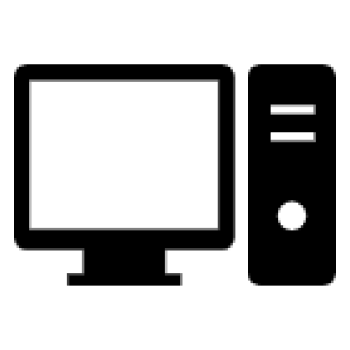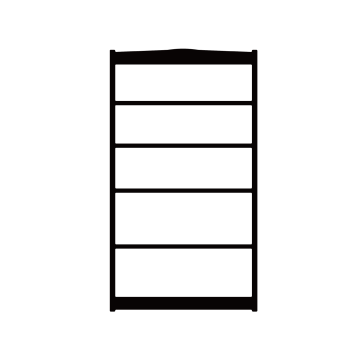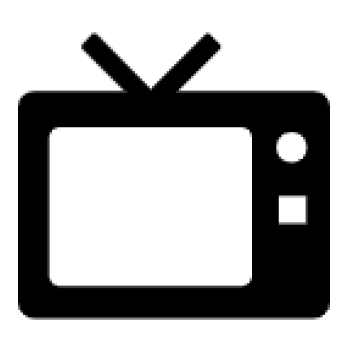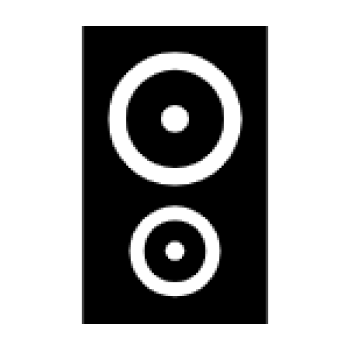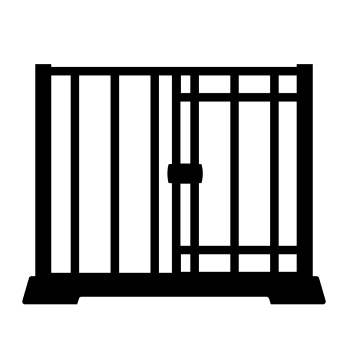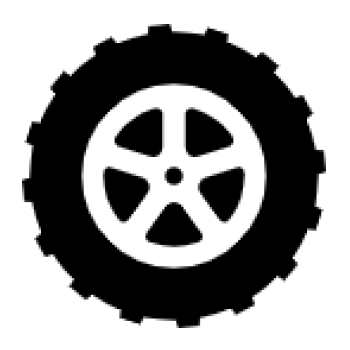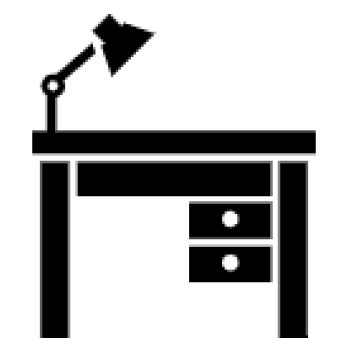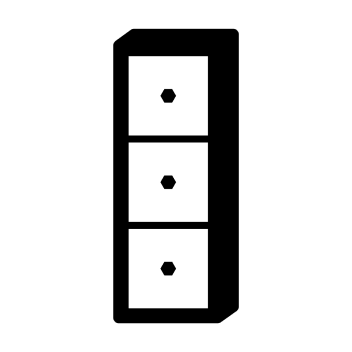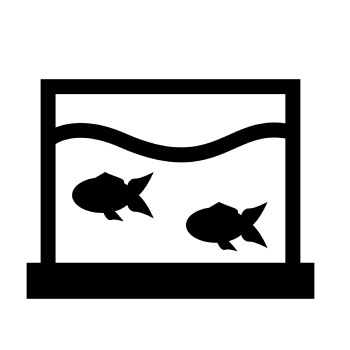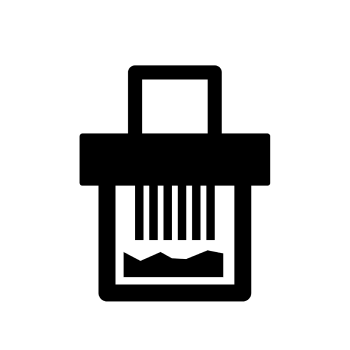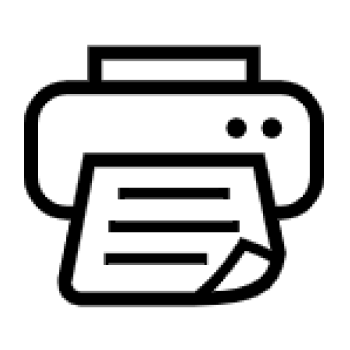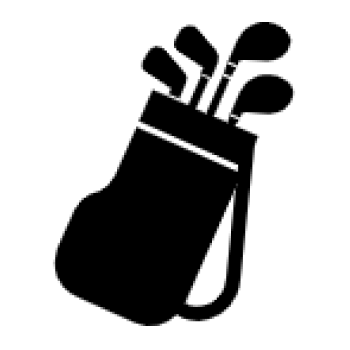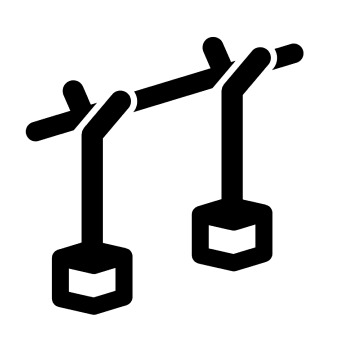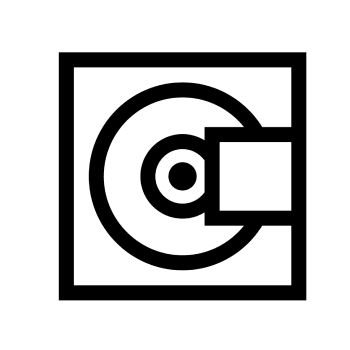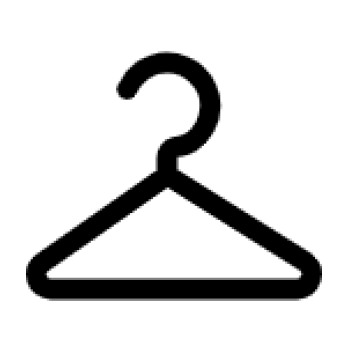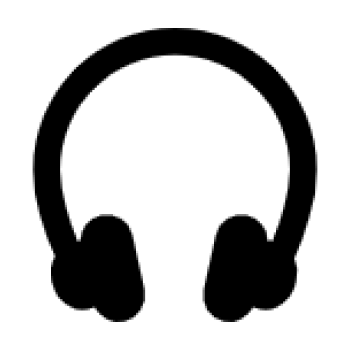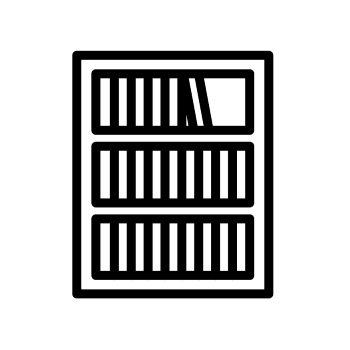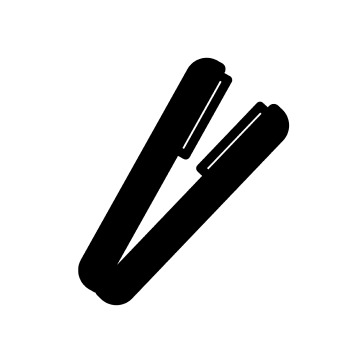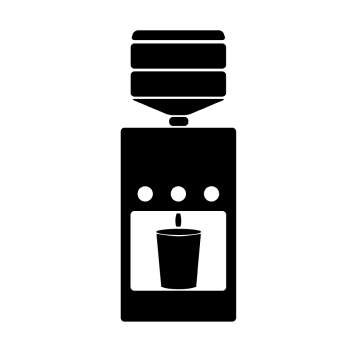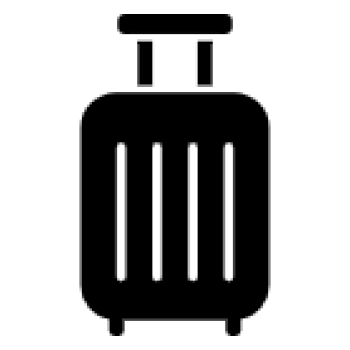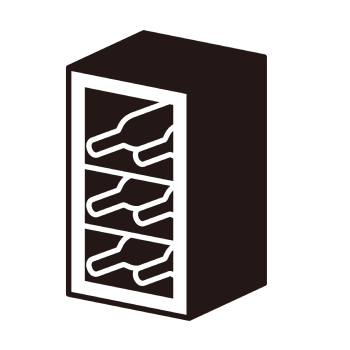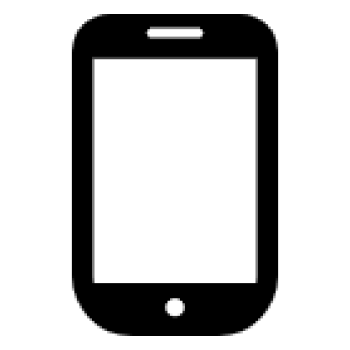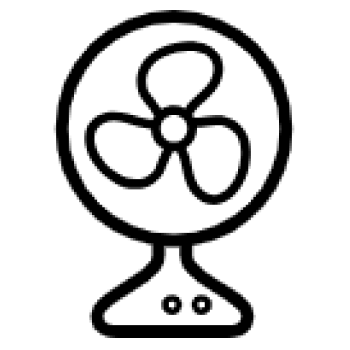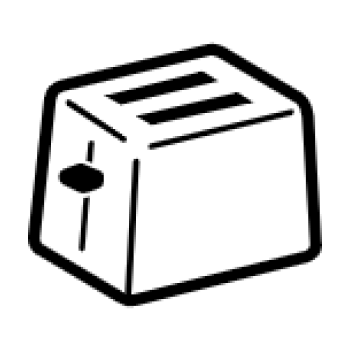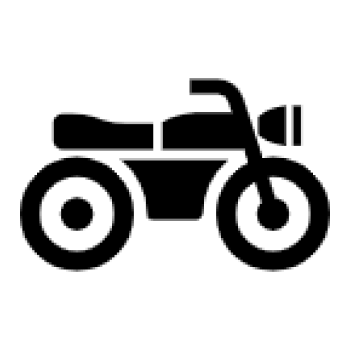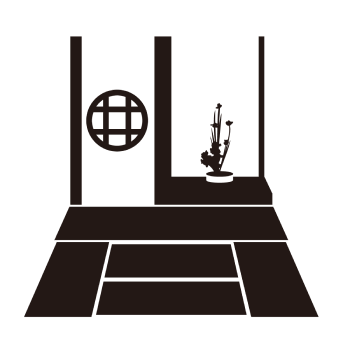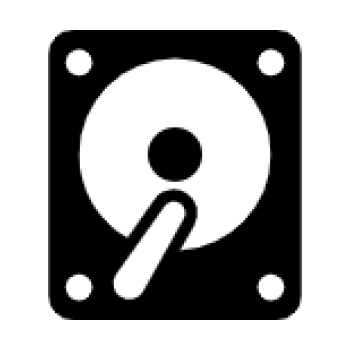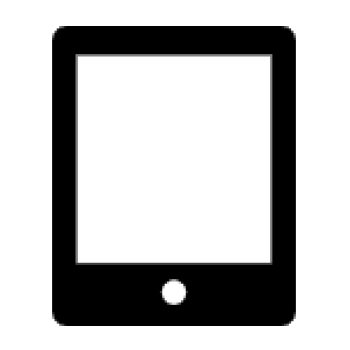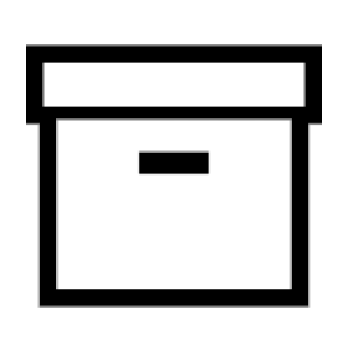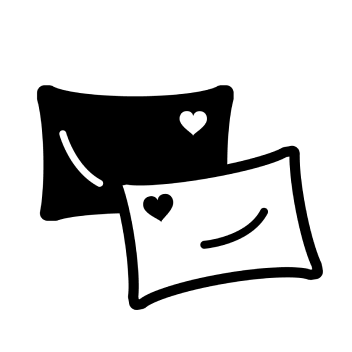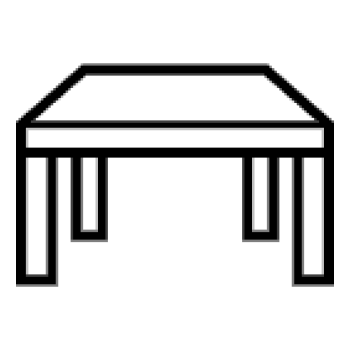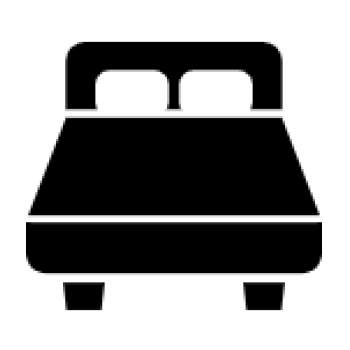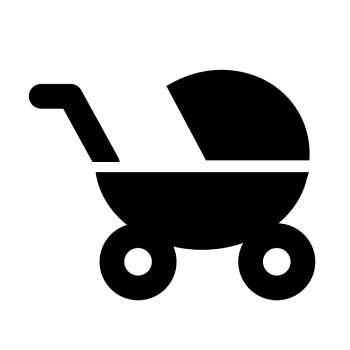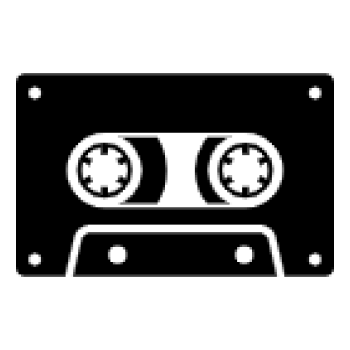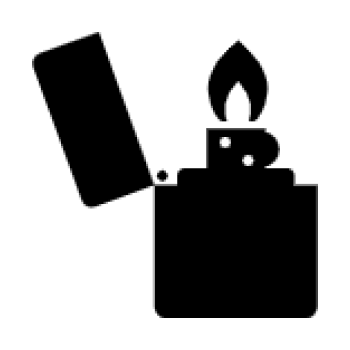ペンキは、家の壁や家具の塗り替え、DIYなどでとても身近に使われる材料ですよね。でも、作業が終わった後に余ってしまったペンキの処分に困っている方は意外と多いのではないでしょうか。捨て方を間違えると環境に悪影響を与えたり、場合によっては法律違反になってしまうこともあるため、不安に感じる方も多いと思います。
特にペンキは種類によって成分や扱い方が異なり、油性や水性、また缶の素材によっても処分の方法が変わってきます。さらに、液体のままだと運搬や保管が難しく、周囲にこぼれてしまうリスクもあります。だからこそ、ペンキを安全に処分するためには、正しい知識と手順を知っておくことが大切です。
本記事では、ペンキの処分に関する法律や自治体のルールを踏まえながら、固まったペンキと液体のペンキの違い、容器別の扱い方、さらに再利用や不用品回収業者の利用法まで、わかりやすく丁寧に解説します。ペンキ処分に不安を感じている方が安心して適切に処理できるよう、しっかりサポートしますので、ぜひ参考にしてくださいね。
ペンキを処分する際の注意点
有害物質の取り扱いに関する注意
ペンキには、揮発性有機化合物(VOC)をはじめとする有害物質が含まれている場合があり、特に油性ペンキは溶剤が多く使われているため、取り扱いに細心の注意が必要です。VOCは揮発して空気中に放出されることで、大気汚染の原因となり、人体の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、頭痛、めまい、呼吸器の炎症、長期間の曝露で慢性的な健康被害が出るリスクもあるため、室内での保管や処分時には換気を十分に行うことが重要です。
また、油性ペンキの溶剤は引火性が高く、火気の近くで作業すると火災の危険が高まります。処分作業の際は必ず火気厳禁の環境で行い、喫煙や電気スパークにも注意を払わなければなりません。加えて、ペンキの残り液が排水口に流れると水質汚染につながり、生態系に深刻な影響を及ぼします。したがって、使い残しのペンキを不用意に処理せず、専門の処分方法に従うことが環境保護の観点からも不可欠です。さらに、直接手で触れたり長時間吸い込んだりすることを避けるため、処分作業中は手袋やマスクなどの保護具を着用することが望ましいです。適切な保護対策と環境配慮を徹底することで、有害物質によるリスクを最小限に抑えることができます。
法律や自治体ルールの確認
ペンキの処分に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や各自治体が定める条例に基づいて厳密に規制されています。特にペンキの空き缶であっても、内部に塗料の残留があれば「有害廃棄物」として扱われることがあり、一般ごみとして出すことが禁止されている場合がほとんどです。
そのため、処分を行う前に必ず自治体の公式ホームページや最寄りの市役所で最新のルールを確認する必要があります。自治体ごとに収集方法や分別の仕方、持ち込み可能な処理施設などが異なり、誤った処分は法令違反となるだけでなく、環境汚染や罰則の対象にもなりかねません。例えば、一部の自治体ではペンキの種類(油性・水性)によって分別回収が行われていたり、指定された専門の回収日や持ち込み先が限定されていたりします。
さらに、大量のペンキを処分する場合は産業廃棄物扱いとなることもあり、許可を持つ業者に依頼する必要があるケースもあります。したがって、自己判断で処分することは避け、必ず自治体の指示に従うことが大切です。また、リサイクル可能な場合は回収施設や販売店での引き取りサービスを利用する方法もあります。これらの情報を把握し、法律を遵守した正しい処分方法を選ぶことが、環境保護と安全確保のために欠かせません。
処分前に確認すべきポイント
ペンキを安全かつ適切に処分するためには、まず処分前にペンキの種類、残量、容器の素材をしっかり確認することが重要です。まず、ペンキの種類として主に「油性ペンキ」と「水性ペンキ」があります。油性ペンキは揮発性溶剤が多く含まれているため取り扱いが難しく、専用の処分方法が必要です。一方で水性ペンキは比較的扱いやすく、乾燥させて固めてから廃棄する方法が認められている自治体もあります。
次に、ペンキの残量を確認しましょう。液体のまま残っている場合は、そのまま廃棄することが難しいため、まずはしっかりと乾燥・固化させる作業が必要です。乾燥せずに廃棄すると液漏れや揮発による環境被害を招く恐れがあります。乾燥には、自然乾燥や吸収剤(新聞紙、オイルキャッチャーなど)を使う方法があります。
また、容器の素材も処分方法を決める上で重要です。金属製やプラスチック製の缶はリサイクル可能な場合もありますが、塗料が残っているとリサイクル不可となることもあるため、完全に空にするか自治体の指示に従う必要があります。さらに、ペンキの成分表示や取扱説明書も確認し、処分に関する注意事項を事前に把握しておくと安心です。これらのポイントをしっかり押さえて処分準備を整えることで、トラブルを避け、法律や環境保護の観点からも適正な処分が可能となります。
固まった中身の処分方法
ペンキが固まる仕組みとは?
ペンキが固まる仕組みは、その成分や性質によって異なりますが、基本的には空気中の成分と化学反応や物理的な変化を起こすことで硬化・乾燥していきます。水性ペンキの場合は、水分が蒸発し、空気中の酸素や水分と反応して徐々に硬化します。これは自然乾燥の一種で、時間が経つほどにペンキの液体成分が蒸発し、塗膜として固まっていくのが特徴です。
一方、油性ペンキは揮発性の溶剤が蒸発することで硬化します。油性ペンキに含まれる溶剤は空気中に揮発しやすく、溶剤が蒸発した後に残った樹脂成分が硬化し、固まるのです。これらの性質を利用し、ペンキを廃棄する際は「固める」工程を設けることが一般的です。固まる過程で揮発性の有害成分の放出も徐々に抑えられ、液体のまま廃棄するよりも安全に処理が可能になります。こうした固まる仕組みを理解しておくことは、処分時の安全確保と環境保護に役立ちます。
固まったペンキの安全な処理方法
固まったペンキは中身が硬化しているため、液体が漏れ出す心配がなく、運搬や処分時の安全性が高まります。多くの自治体では、完全に乾燥し固まったペンキの缶であれば、一般ごみや粗大ごみとして回収可能なケースがあります。ただし、完全に固まっていないペンキをそのまま出すと、液漏れや揮発性有害物質の放出が問題となり、処分が拒否されることもあるため注意が必要です。
ペンキを効率よく固めるためには、新聞紙やおがくず、砂、吸収材などを混ぜてかき混ぜる方法が有効です。これにより乾燥が早まり、短時間で安全に処分できる状態に持っていけます。また、ペンキ専用の固化剤を使用する方法もあります。処分前には、完全に乾燥・硬化していることを確認するために、缶の中のペンキが指で触って固くなっているかどうかを確かめるとよいでしょう。固まったペンキは自治体の回収ルールに従って出すことが基本であり、回収日時や分別方法を守ることでトラブルを避けられます。適切に固めてから処分することが、環境や周囲の安全を守るために非常に重要です。
固まらないペンキとの違い
液体のままのペンキは、非常に扱いが難しく、有害性が高いため、多くの自治体では直接の回収や廃棄を禁止しています。液体のペンキは缶の中で漏れやすく、揮発性有機化合物(VOC)などの有害物質が空気中に放出されやすいため、環境汚染や健康被害のリスクが高いのです。そのため、液体のペンキをそのまま一般ごみとして出すことは法律で禁止されている場合が多く、専用の処理施設に持ち込むか、業者に依頼して処分する必要があります。これに対して、固まったペンキは物理的に硬化しているため、液体の漏れや揮発がなく、安全に運搬・処分が可能です。
処分時の安全性が格段に高まるため、多くの自治体で固まったペンキの扱いは許容されています。つまり、ペンキを処分する際は、必ず液体状態のまま出すのではなく、しっかりと固めてから処分することが必須であり、この違いを理解して正しい処分方法を実践することが環境保全にもつながります。
ペンキの容器別の処分方法
金属缶の場合の処分手順
ペンキが入っている金属缶は、多くの自治体でリサイクル資源として扱われていますが、重要なのは中身を完全に使い切り、空の状態にすることです。缶の中にペンキが残っていると、有害物質が漏れるリスクがあるため、燃えないゴミとして処分されることが多いです。
また、缶の表面にペンキが付着している場合も処理方法が異なる場合があります。空缶としてリサイクル回収に出す際は、自治体の回収ルールを事前に必ず確認しましょう。例えば、缶の洗浄が必要な場合や、蓋を外して分別する指示があるケースもあります。正しく分別して出すことで、リサイクル効率が上がり環境負荷の軽減につながります。
プラスチック容器の場合の処分方法
プラスチック容器入りのペンキは、自治体によって「燃えるゴミ」または「プラスチック資源ごみ」として分別されています。いずれの場合も、中身が完全に空か、またはしっかり固まっていることが処分の前提条件です。
液体のペンキが残っていると、漏れや悪臭の原因となり、回収が拒否される場合が多いので注意が必要です。容器の表面についたペンキも、自治体のルールによっては洗浄を求められることがあります。特にプラスチックはリサイクル効率の面でも重要な資源なので、正しく処理することが求められます。廃棄前に自治体の公式サイトや案内を確認し、処理方法に従うことが大切です。
小容量ペンキの扱い方
家庭で使うことの多い小容量のペンキは、比較的処理がしやすいですが、少量だからといって安易にそのまま廃棄するのは危険です。使用済みのペンキは新聞紙や布などに染み込ませて乾燥させる方法が一般的で、しっかり固めることで安全に処分できます。少量であっても揮発性の有害成分が含まれることがあるため、屋外の風通しの良い場所で乾燥させるのが望ましいです。
また、自治体によっては少量ペンキ専用の回収方法や処理施設を設けていることもあるので、自治体の指示に従うことが重要です。無理に液体のまま廃棄すると環境汚染の原因になるため、必ず固めてから処分しましょう。
ペンキの処分方法4選
ペンキを再利用・リサイクルする選択肢
使い残したペンキがまだ十分に使用可能な場合は、単に廃棄するのではなく、再利用やリサイクルを検討することが環境負荷の軽減につながります。地域のリサイクルショップやDIY愛好家に譲ることで、ペンキを無駄なく活用できます。
また、多くの自治体や環境団体では、ペンキのリサイクルプログラムを実施しています。これらのプログラムでは、集められたペンキを専門的に再生処理し、再び販売用や公共施設の補修などに利用されることがあります。リユースやリサイクルはゴミの減量だけでなく、資源循環の観点からも重要です。譲渡や回収のルールや条件は自治体によって異なるため、事前に詳細を確認し、適切に利用しましょう。
粗大ゴミとしての出し方
ペンキの処分でよく利用される方法のひとつが、自治体による粗大ゴミ回収サービスです。多くの場合、液体のペンキは処分が難しいため、あらかじめ新聞紙や砂などで固めて乾燥させ、完全に硬化させてから缶ごと出す必要があります。処分する際は、自治体指定の処理券を購入し、指定された回収日に決められた場所へ出すのが基本ルールです。回収の対象となるかは自治体によって異なるため、必ず事前に自治体のホームページや窓口で確認してください。誤って液体のまま出すと回収してもらえないだけでなく、環境汚染の原因にもなるため、必ず固める処理を徹底しましょう。
自治体の回収センターへの持ち込み
お住まいの地域に環境センターや資源回収センターが設置されている場合、ペンキを直接持ち込んで処分できることがあります。特に大量のペンキや業務用のペンキを処分したい場合は、こちらの方法が便利です。持ち込みの際は、受付時間や処理できるペンキの種類・量に制限がある場合が多いため、事前に電話や自治体のウェブサイトで詳しい情報を確認しておくことが重要です。また、ペンキの容器が空か、固まっているかなどの状態もチェックされることがあるため、適切な準備をしてから持ち込みましょう。回収センターでは自治体の許可を得た適正処理が行われるため、安心して依頼できます。
不用品回収業者に依頼する方法
大量のペンキを含む複数の不用品を一度に処分したい場合は、不用品回収業者に依頼する方法もあります。信頼できる業者であれば、廃棄物処理法を遵守し、適正にペンキを処理してくれます。ただし、業者ごとに料金体系や対応可能な品目に違いがあるため、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。また、悪質な業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、必ず自治体の許可証や認可番号の有無を確認しましょう。口コミや実績もチェックし、安心して任せられる業者を選ぶことが大切です。
ペンキの処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回はペンキの処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
ペンキを処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!