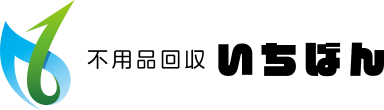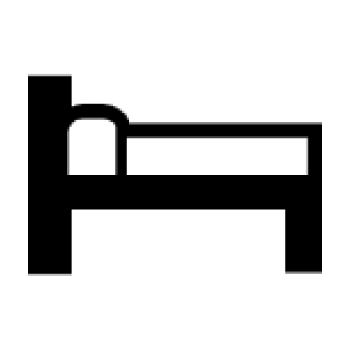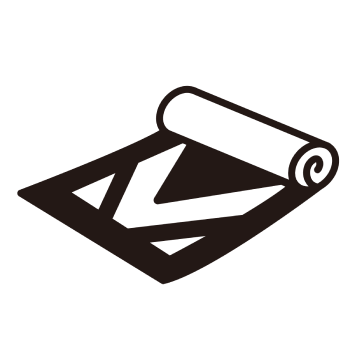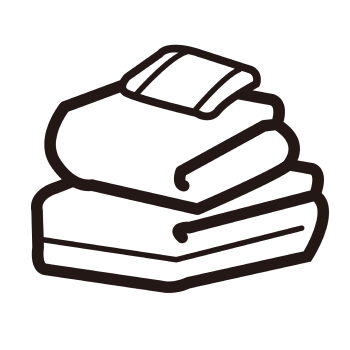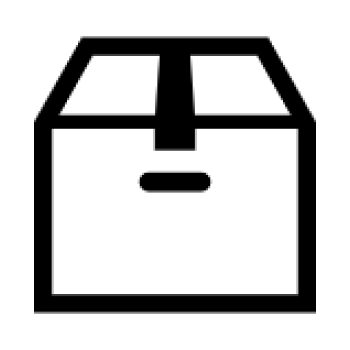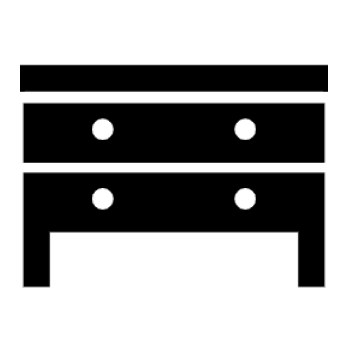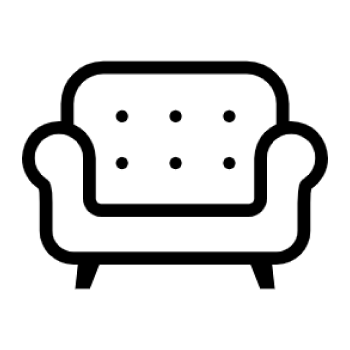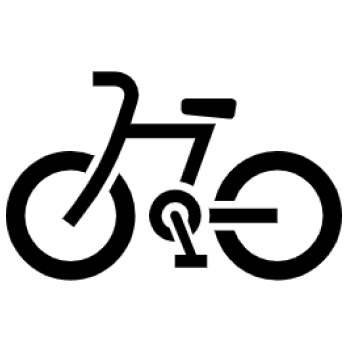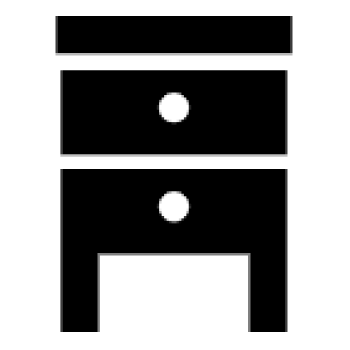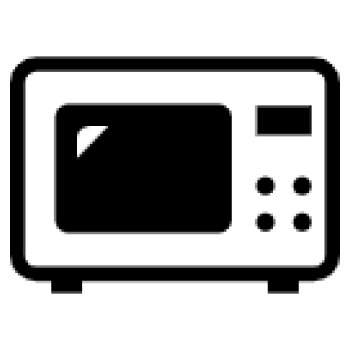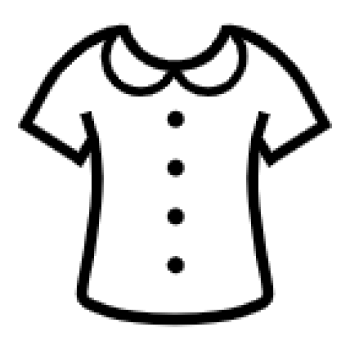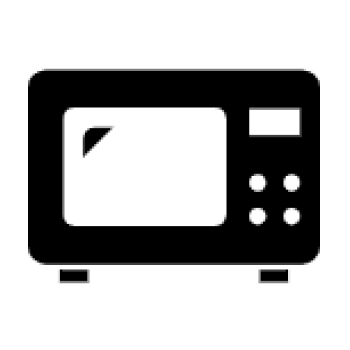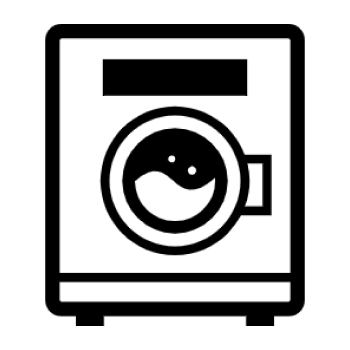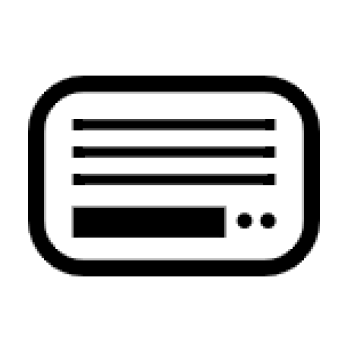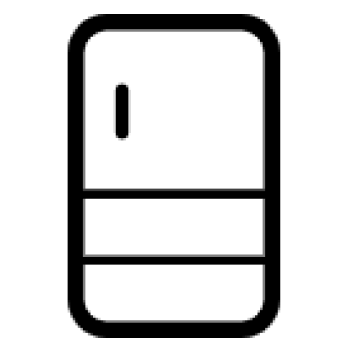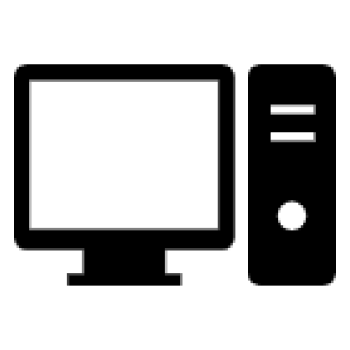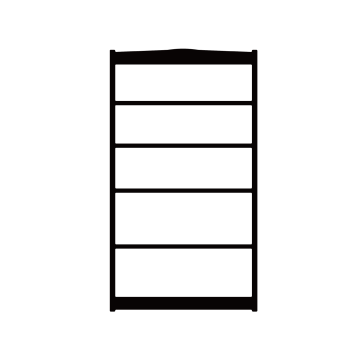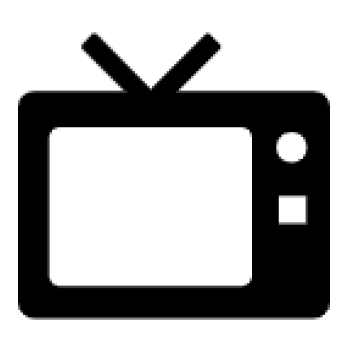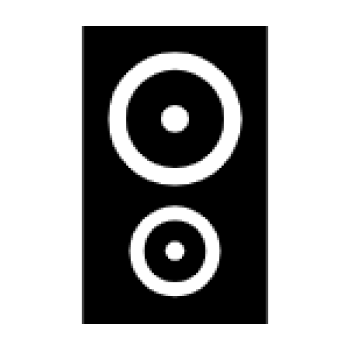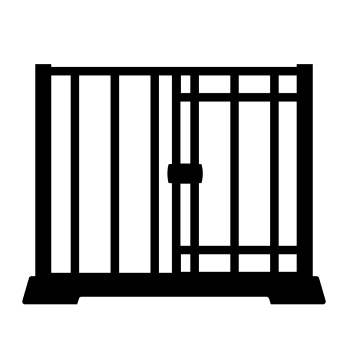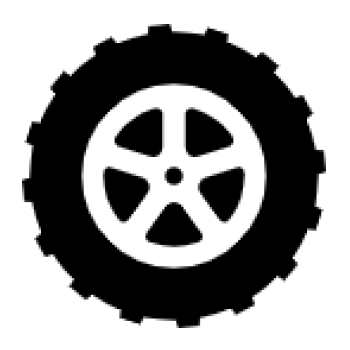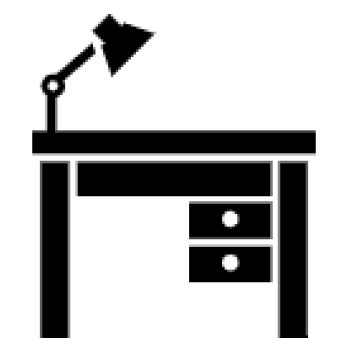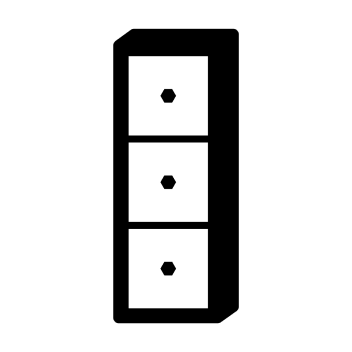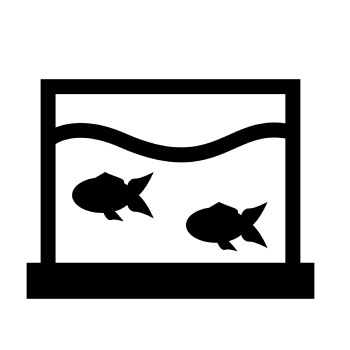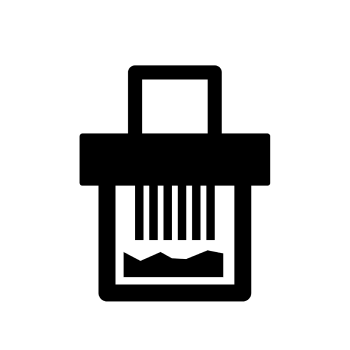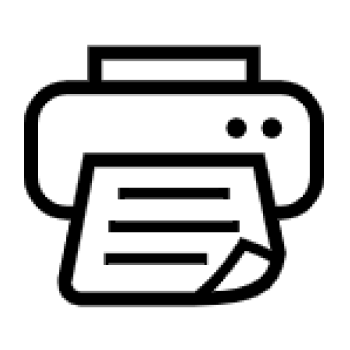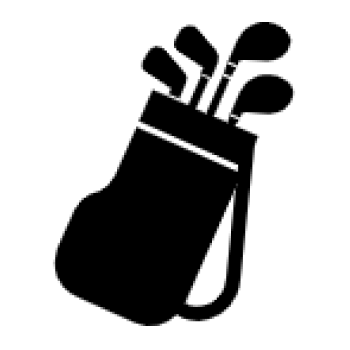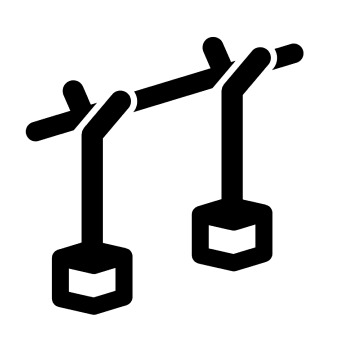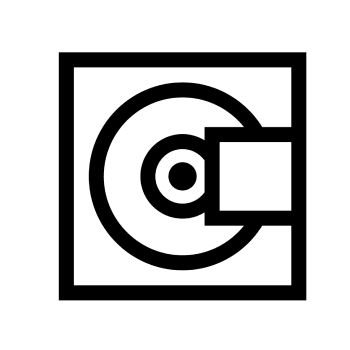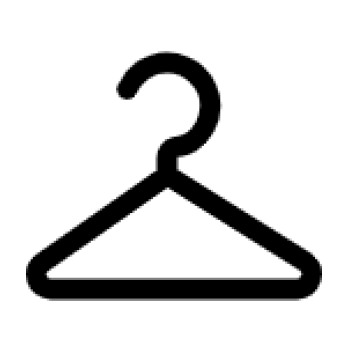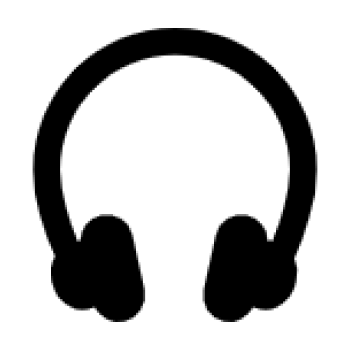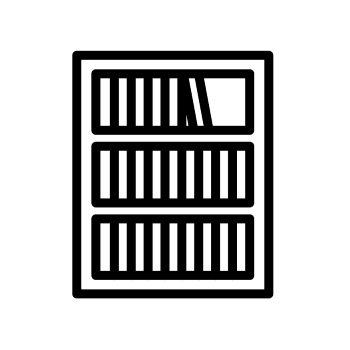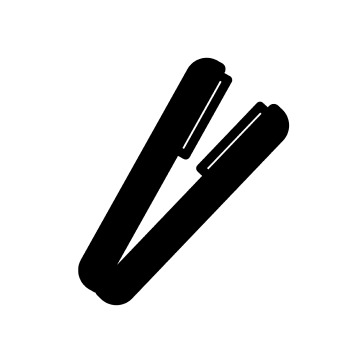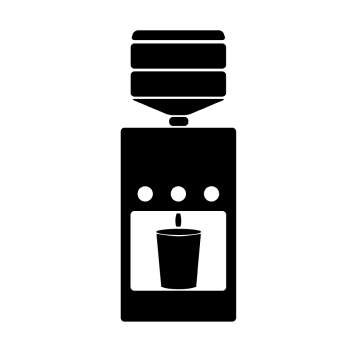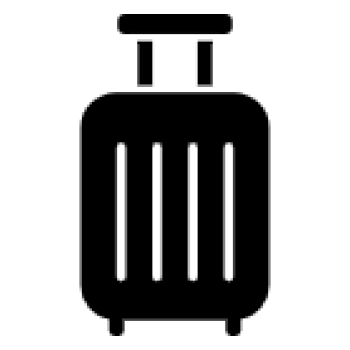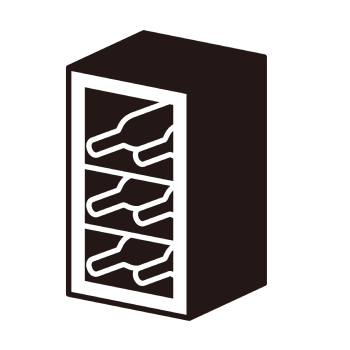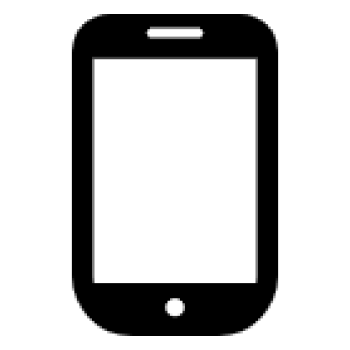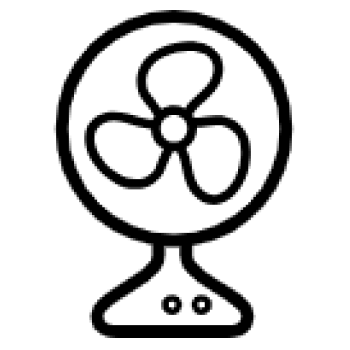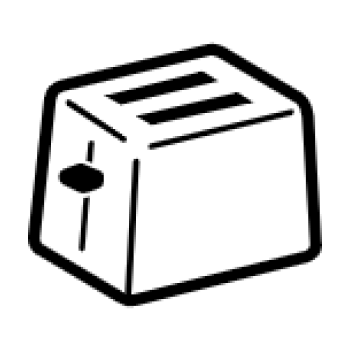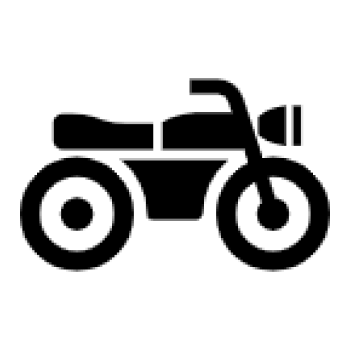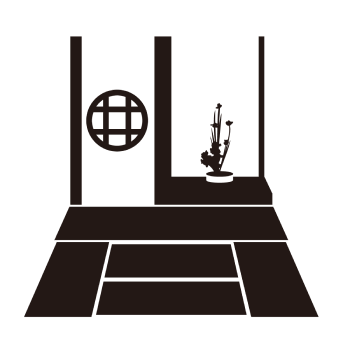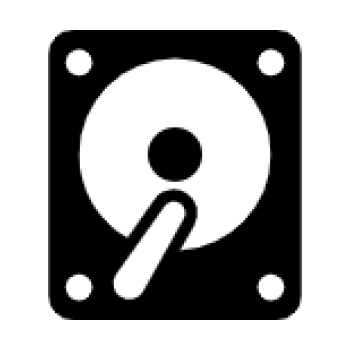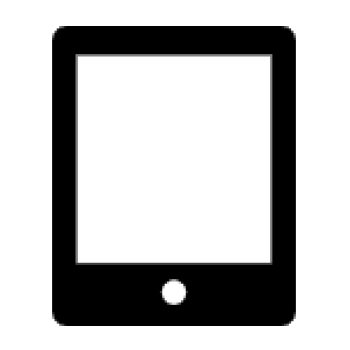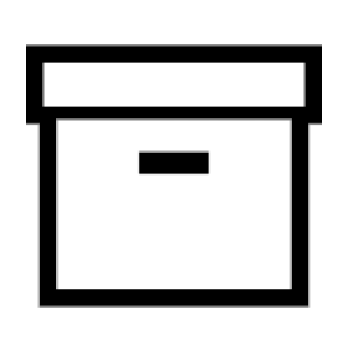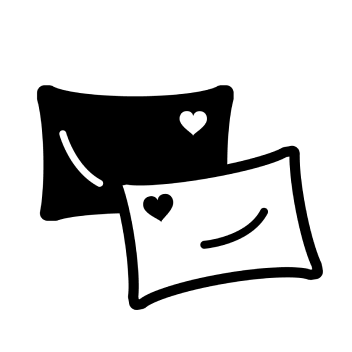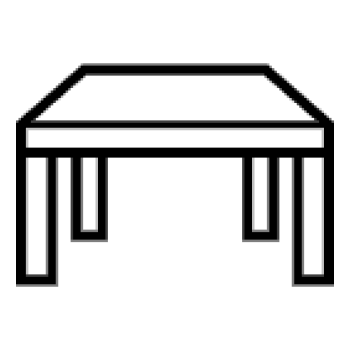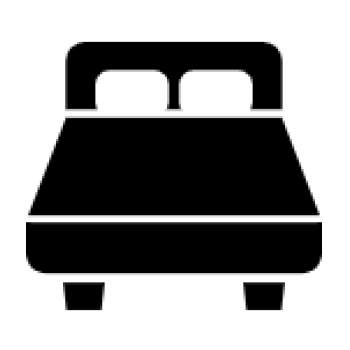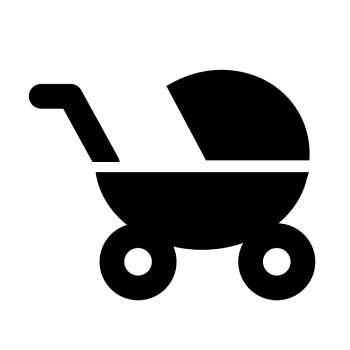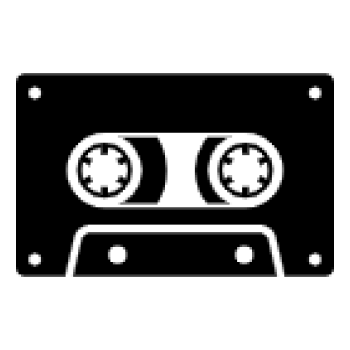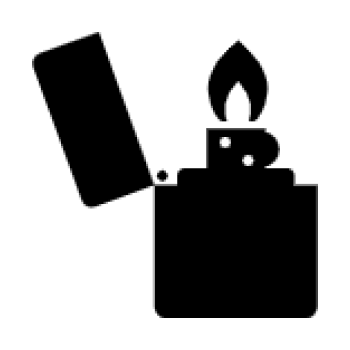傘は、突然の雨や風から私たちを守ってくれる生活の必需品です。しかし、長く使っているうちに骨が折れたり、布が破れたりして、使いづらくなったり壊れてしまうことも多いでしょう。そんなとき、「どうやって処分すればいいの?」と悩む方は少なくありません。傘は素材も複雑で、自治体ごとに処分のルールも異なるため、適切な処分方法を知っておくことが大切です。また、捨て方を間違えると、リサイクルできる資源を無駄にしてしまうこともあります。さらに、骨や柄の先端などがとがっているため、そのまま捨てると周囲の人にケガをさせてしまうリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、傘を処分するタイミングや注意点、素材別の処分方法、そして具体的な捨て方をわかりやすく解説します。大切に使ってきた傘を最後まで丁寧に扱い、環境にも配慮した処分の仕方を一緒に学んでいきましょう。困ったときの参考にしていただければ幸いです。
傘を処分する適切なタイミング
骨組み(骨)が壊れて開閉ができなくなったとき
まず最もわかりやすい処分の目安は、骨組み(骨)が壊れて開閉ができなくなったときです。傘の骨は開閉機能の要であり、鉄やアルミ、グラスファイバーなどでできています。強風や長期間の使用で骨が折れたり曲がったりすると、傘をきちんと開け閉めできなくなり、風にあおられて壊れやすくなるだけでなく、周囲の人に怪我をさせてしまう危険もあります。
特に小さな子どもやお年寄りが使用する場合は安全面を最優先に考え、骨がぐらついたり異音がする時点で処分を検討することが望ましいです。無理に使い続けると突然の骨折れで転倒やトラブルになる恐れもあるため、早めに見切りをつけましょう。
傘布に大きな穴や破れができて修理が難しいとき
次に、傘布に大きな穴や破れができて修理が難しいときも明確な処分のサインです。傘の布地はナイロンやポリエステルなどの合成繊維でできており、防水機能を担っています。小さな穴やほつれなら一部修理が可能な場合もありますが、広範囲にわたる破れや裂けがあると、水が侵入して雨を防げなくなるため、実用的ではありません。
また、布が薄くなっていたり生地が劣化している場合も同様に、防水性が失われていることが多いです。これらの状態は修理にかかる手間や費用が割に合わないことも多いため、買い替えを検討するのが現実的です。
使用感が強く雨を防ぐ効果が著しく低下したとき
さらに、使用感が強く、雨を防ぐ効果が著しく低下したときも処分を考えるタイミングです。長期間使っていると、傘布の表面が日焼けで色あせたり、汚れやシミが目立つようになります。これらは防水スプレーなどである程度のメンテナンスができますが、水をはじかなくなっている場合は機能が大きく落ちています。見た目の悪さも気になるようなら、新しい傘に買い替えることで雨の日の気分も上がり、快適に過ごせるでしょう。使い古した傘を無理に使い続けると、雨が染み込んで衣服が濡れてしまうこともあります。
新しい傘を購入し古い傘が不要になったとき
そして、新しい傘を購入し、古い傘が不要になったときも処分の良いタイミングです。生活スタイルの変化や好みの変化で傘を新調した場合、古い傘をいつまでも持ち続ける必要はありません。特に使わないまま長期間放置すると、湿気やほこりが付着し、カビの発生や悪臭の原因となることもあります。カビが生えた傘は衛生的に問題があるだけでなく、見た目も悪く気分が下がります。こうしたトラブルを避けるためにも、使わない傘は早めに整理して処分するのが賢明です。
長期間使わず放置してカビや汚れが目立ってきたとき
また、傘は長期間使わずに放置しておくと、特に傘布の内側に湿気がこもりやすいため、カビや汚れが付着しやすくなります。カビが繁殖すると素材が弱くなるだけでなく、健康面でも良くありません。アレルギーや皮膚のトラブルを引き起こす恐れもあるため、使わない傘がある場合は湿気の少ない場所で保管し、定期的に換気やメンテナンスを行うことが大切です。もし劣化やカビが進んでしまったら、早めに処分を検討してください。
傘を処分する際の注意点
自治体ごとの分別ルールをしっかり確認すること
傘は骨組み部分に鉄やアルミ、プラスチック、グラスファイバーなど様々な素材が使用されているため、自治体ごとにゴミの分別ルールが大きく異なります。例えば、傘全体を「可燃ごみ」として回収している自治体もあれば、骨組みを「金属ごみ」や「不燃ごみ」として別に分けなければならない自治体もあります。また、サイズが一定以上のものは「粗大ごみ」として扱われ、処分のために別途手数料が必要になる場合もあるのです。
このため、処分をする前には必ず自分が住んでいる地域の自治体のホームページを確認したり、ゴミの分別カレンダーをチェックすることが欠かせません。特に傘のように複数の素材が混ざっているものは、誤った出し方をすると回収されなかったり、場合によっては罰則や追加料金が発生することもあります。正しいルールを守って出すことで、地域のリサイクルシステムにも協力でき、環境保全にもつながるのです。
傘の先端や骨組みの取り扱いに十分注意を払うこと
傘の先端部分は尖っていて危険なため、そのまま普通に出してしまうと、ゴミ収集の作業員が怪我をする恐れがあります。特に骨組み部分には鋭利な金属が使われていることが多く、無造作に投げ込まれた傘の骨が収集車の回転部に絡まったり、作業員の手や腕に刺さったりする事故も報告されています。
こうした事故を防ぐために、処分の際は必ず傘の先端部分や骨組み全体をガムテープや布テープでしっかりと包むことが大切です。特に尖った部分が他のゴミと触れないように丁寧に巻くことで、回収作業の安全性を高められます。また、傘をまとめて出す場合は、バラバラにならないよう紐やテープで束ねると扱いやすくなり、作業員の負担も軽減されます。こうしたひと手間をかけることがマナーでもあり、地域の方々への思いやりにもつながるのです。
まだ使える傘はリユースやリサイクルを積極的に検討すること
壊れていない、あるいは一部の修理でまだ十分使える傘を処分する際は、単に捨てるのではなくリユースの可能性を考えることも重要です。例えば、知人や友人に譲ったり、フリマアプリやオークションサイトで販売したりする方法があります。特にデザイン性の高い傘や高級ブランドの傘は中古市場での需要が根強く、買い手がつくことも少なくありません。
また、地域によっては傘のリサイクルボックスやリユースショップが設置されている場合もあります。こうした場所に持ち込むことで、傘がまだ使える人に渡り、資源の再利用が促進されます。環境負荷を減らすためにも、ただゴミとして処分するのではなく、できるだけ傘を「循環させる」ことを心がけるのが現代の賢い選択と言えます。
さらに、リユースの際には傘の清掃や簡単なメンテナンスをしておくと、受け取る側も気持ちよく使うことができるためおすすめです。たとえ売れなくても、寄付や地域のフリーマーケットに出すことで、無駄を減らし環境に優しい処分ができるでしょう。
傘の素材別・部分別の処分方法の違い
骨組み(骨)の処分方法
鉄製・アルミ製の骨組み
多くの傘の骨組みは鉄やアルミニウムでできており、これらは金属ごみとして扱われることが多いです。自治体によっては金属類の回収日が決まっていたり、専用の金属ごみ袋に入れて出すことが求められます。
金属はリサイクル資源として価値があるため、適切に分別することで再利用が促進されます。
グラスファイバー製の骨組み
近年増えているグラスファイバー製の骨組みは、軽くて丈夫な反面、リサイクルが難しい素材です。
そのため、多くの自治体では不燃ごみや粗大ごみとして扱われることが多く、自治体ごとのルールを必ず確認する必要があります。分解して出すことが求められる場合もあります。
傘布(布地)の処分方法
ポリエステルやナイロン製の布地
傘の布地は主に合成繊維(ポリエステルやナイロン)で作られています。これらは基本的に燃えるごみとして処分できますが、自治体によっては不燃ごみとして扱う場合もあるため、地域の分別ルールを確認してください。
また、汚れや湿り気が強い場合は処分時に臭いや腐敗の原因になるため、乾かしてから出すことをおすすめします。
柄・持ち手の処分方法
プラスチック製の柄・持ち手
プラスチック製の柄や持ち手は、一般的に燃えるごみかプラスチックごみとして処理されます。自治体によってはプラスチックごみの回収日が別に設定されていることもあるので、必ず確認しましょう。
木製の柄・持ち手
木製の柄は燃えるごみとして出せる場合が多いですが、塗装がされているかや長さによって処理の仕方が変わる自治体もあります。木材はリサイクル可能な場合もあるため、自治体の指示に従ってください。
金属製の柄・持ち手
金属製の場合は骨組み同様、金属ごみとして分別されます。分解して金属部分を分けて出すとリサイクルに適しています。
壊れている傘の分解と処分
傘が破損している場合は、できるだけ分解して素材ごとに分けて処分するのが基本です。骨組みの金属部分は金属ごみ、傘布は燃えるごみ、柄や持ち手も素材ごとに分けることで、リサイクル効率が向上し環境負荷を減らせます。
特にグラスファイバー製の骨組みは分解が難しいこともありますが、可能な限り分別を心がけましょう。
傘の処分方法5選
自治体のごみ回収に出す
傘の最も基本的な処分方法は、お住まいの自治体のごみ分別ルールに従ってごみ回収に出すことです。傘は骨組みや柄、布地など複数の素材が混ざっているため、自治体によって「燃えるごみ」「不燃ごみ」「金属ごみ」など分類が異なります。まずは自治体の公式ホームページや配布されている分別カレンダーを確認し、傘の扱いを把握しましょう。
処分の際には特に骨組みの先端が鋭利で危険なため、収集作業員の安全のために先端部分や骨組みをガムテープや布テープでしっかり包むことがマナーです。また、濡れている場合はできるだけ乾かしてから出すと、悪臭や虫の発生を防げます。ごみの収集日は地域ごとに異なり、回収に出す時間帯も指定されることが多いため、決められた日に必ず出すようにしましょう。
粗大ごみとして処分する
傘のサイズや自治体の規定によっては、粗大ごみとして処分しなければならない場合もあります。特に長傘や折りたたみ傘であっても、骨組みの長さや全体の大きさが粗大ごみ基準を超えると扱われます。粗大ごみでの処分は、通常のごみ回収とは異なり、事前に自治体へ申し込みを行い、粗大ごみ処理券を購入して貼り付ける必要があります。
申し込みは電話や自治体の専用サイトからできることが多く、収集日も指定されます。処理券の価格は傘のサイズや自治体によって異なりますが、数百円程度のことが一般的です。申し込みから収集まで数日かかる場合があるため、余裕をもって手続きを行うことが望ましいです。粗大ごみは通常のごみとは分けて収集されるため、回収日の前日か当日に指定の場所に出すようにしましょう。
リサイクルショップやフリマアプリで譲る・販売する
まだ十分に使える状態の傘は、捨てるのではなくリサイクルショップに持ち込んだり、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで販売することも賢い処分方法です。特に高級ブランドの傘やデザイン性の高い傘は中古市場でも需要があり、思わぬ価格で売れることもあります。販売にあたっては、汚れや破損の有無をしっかりチェックし、写真や説明文で商品の状態を丁寧に伝えることがポイントです。また、季節や天候によって傘の需要が変わるため、梅雨入り前などのタイミングで出品すると売れやすくなります。譲る場合は知人や友人、地域のフリーマーケットなどを活用し、使わなくなった傘を必要としている人に役立ててもらうことで、環境負荷の軽減にも繋がります。
回収ボックスを利用する
近年、一部のスーパーや商業施設では使わなくなった傘を回収する専用のボックスが設置されています。これは環境保全の一環として、傘の素材を分別しリサイクルする取り組みの一つです。回収された傘は専門業者によって布地や骨組みなどに分けられ、再利用やリサイクルに回されます。利用方法は簡単で、回収ボックスに傘をそのまま入れるだけで良いため、処分の手間が省けるメリットがあります。
ただし、ボックス設置場所は限られており、利用可能な施設は自治体のホームページや施設の案内で確認する必要があります。なお、骨組みの先端をテープで包むなどの事前処理を求める場合もあるため、利用前に注意事項をチェックしておくと安心です。環境に配慮した処分方法として積極的に活用しましょう。
不用品回収業者に依頼する
傘の処分を手軽に済ませたい場合や、大量の傘を一度に処分したいときは、不用品回収業者に依頼する方法が便利です。不用品回収業者は家庭や店舗から出るさまざまな不要品をまとめて引き取ってくれるため、傘のように複数の素材が混ざったものでも一括で処理してもらえます。特に壊れていたり、自治体のごみ収集で出しにくい状態の傘も気にせず任せられるのが大きなメリットです。また、即日対応や深夜・早朝の回収に対応している業者もあり、忙しい方でも都合に合わせて依頼しやすいです。
料金は回収品の量や状態、地域によって異なりますが、見積もりは無料で受け付けている業者がほとんどです。依頼前には、口コミや業者の許認可(古物商許可や一般廃棄物収集運搬許可など)を確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。悪質な業者に依頼すると高額請求や不法投棄のリスクがあるため注意しましょう。不用品回収業者に依頼することで、分別や梱包の手間を大幅に省き、スムーズに傘を処分できます。
傘の処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は傘の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
傘を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!