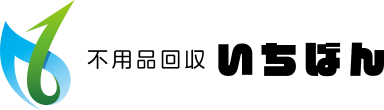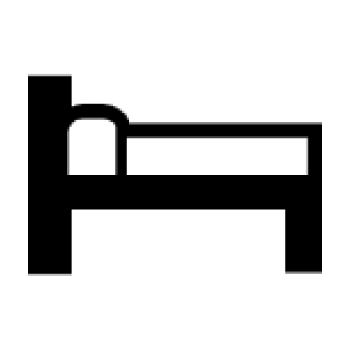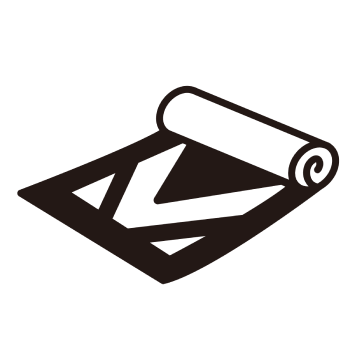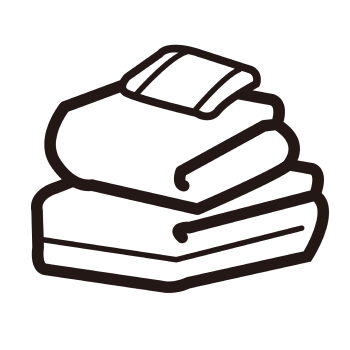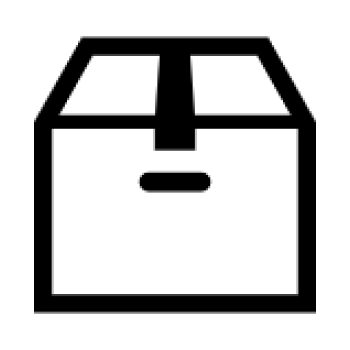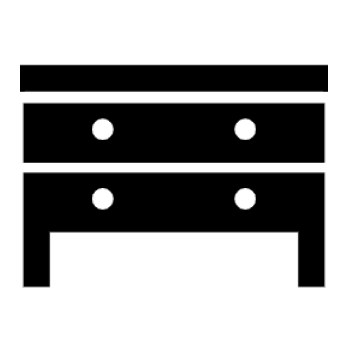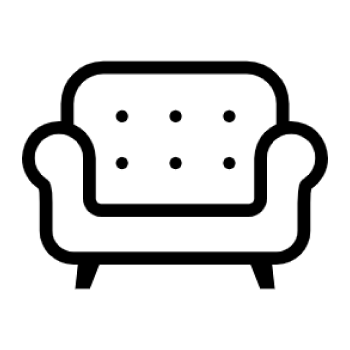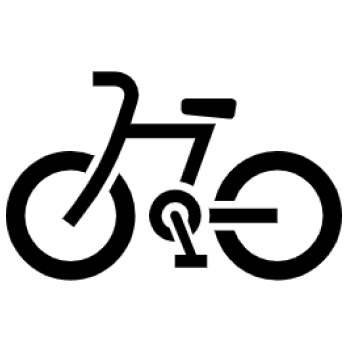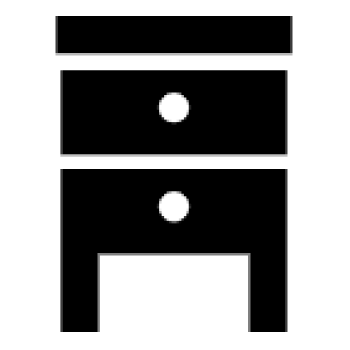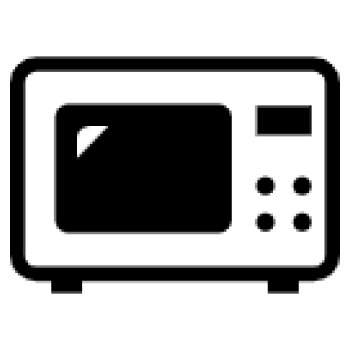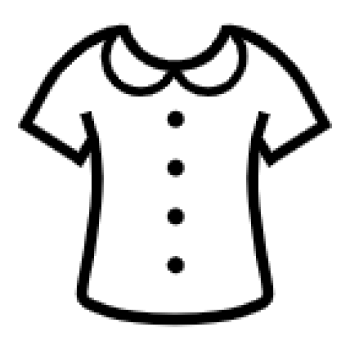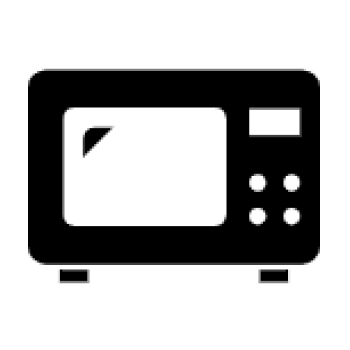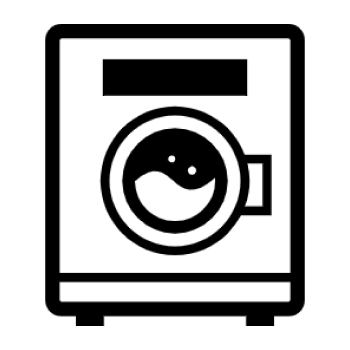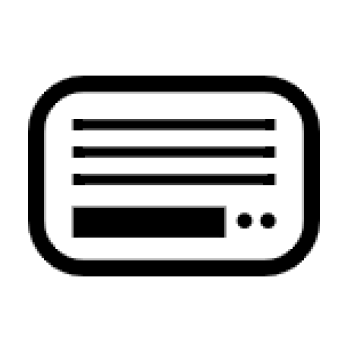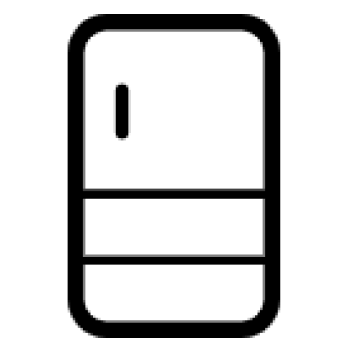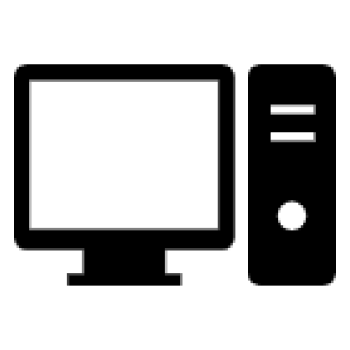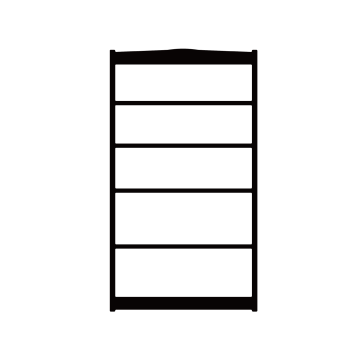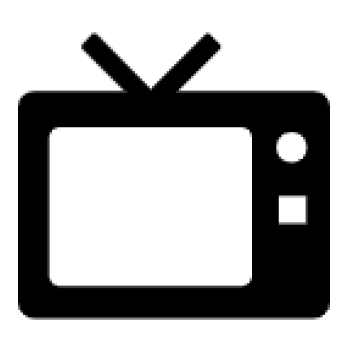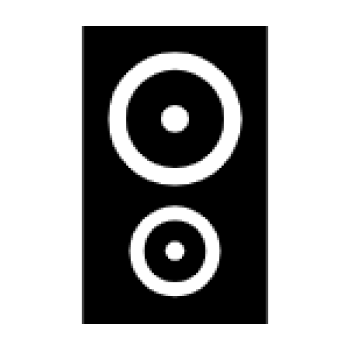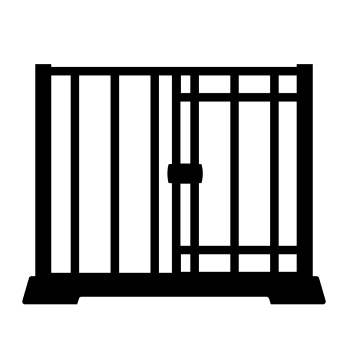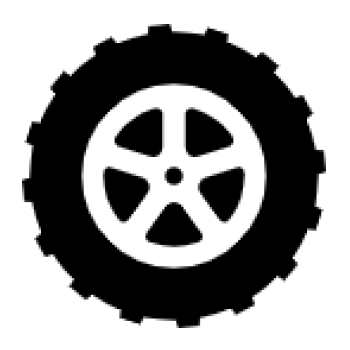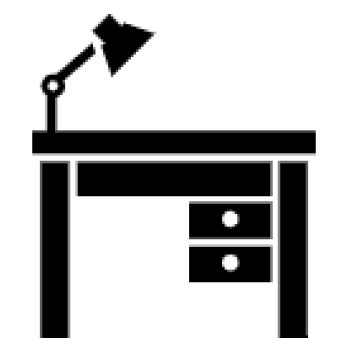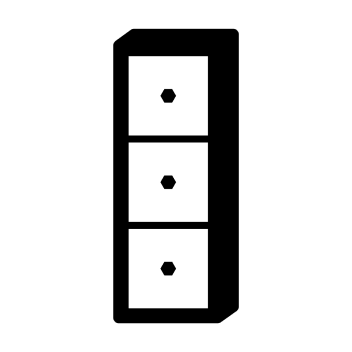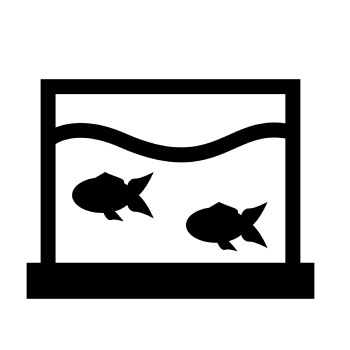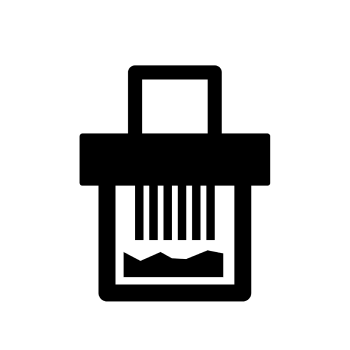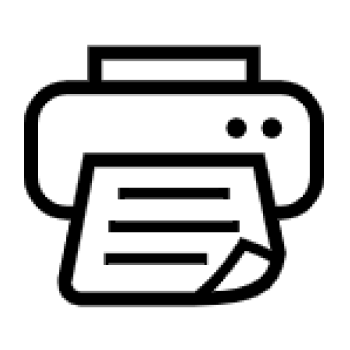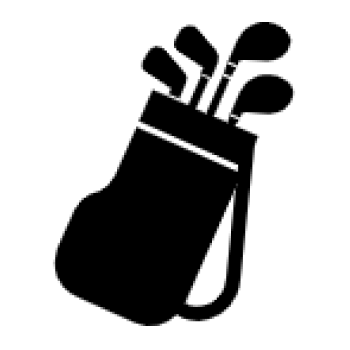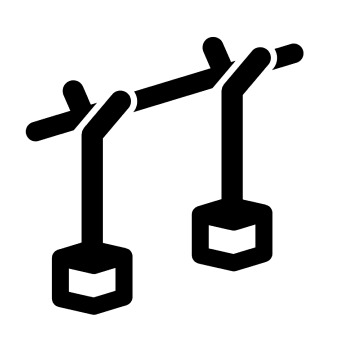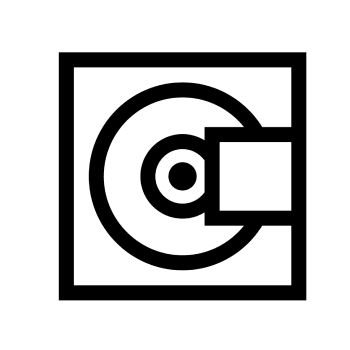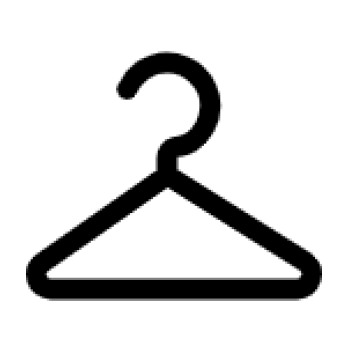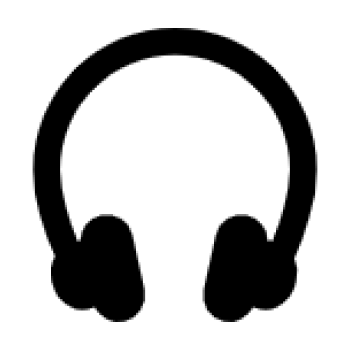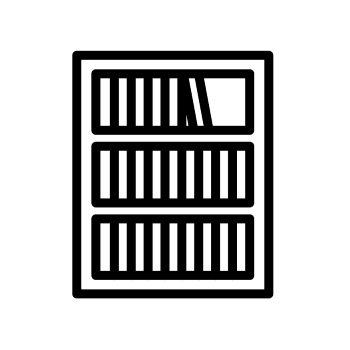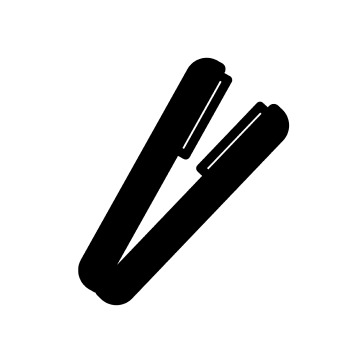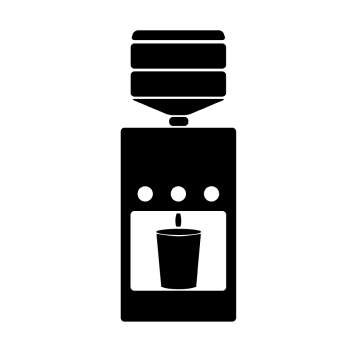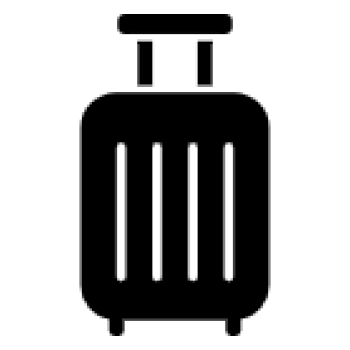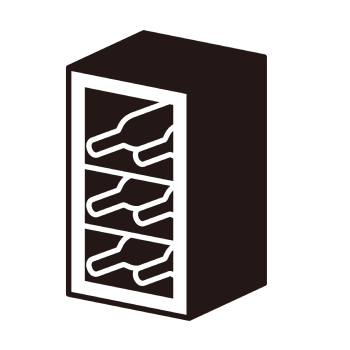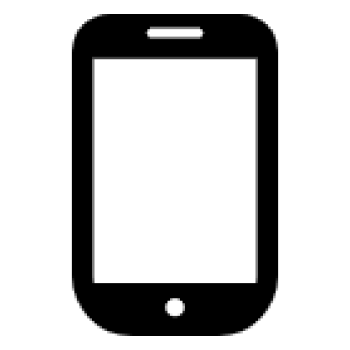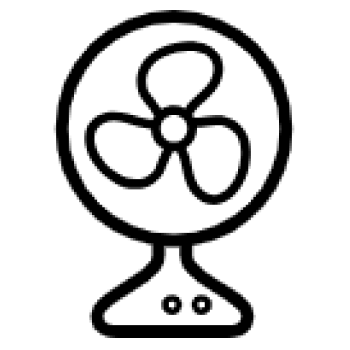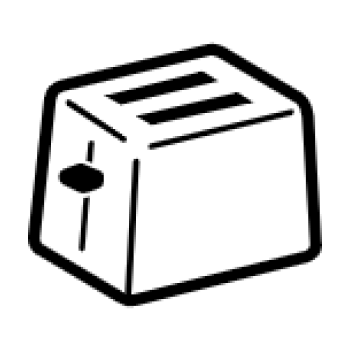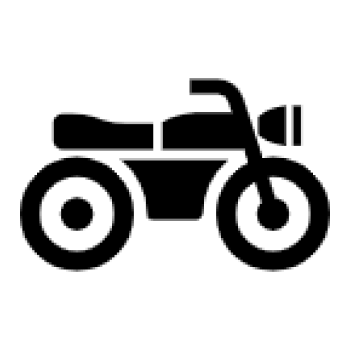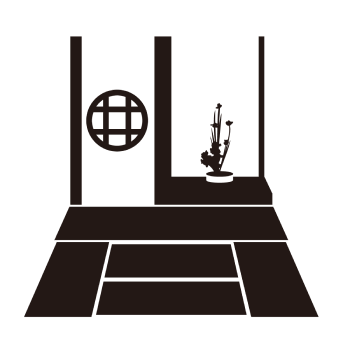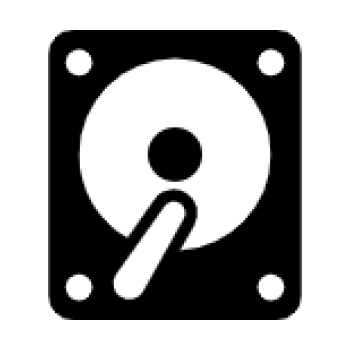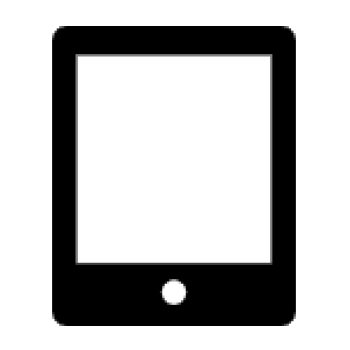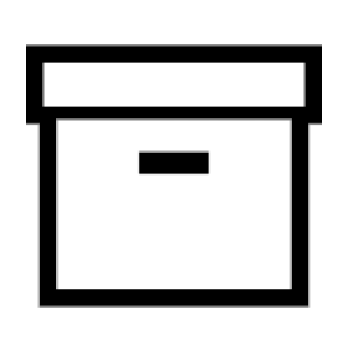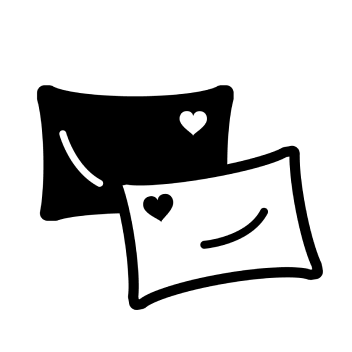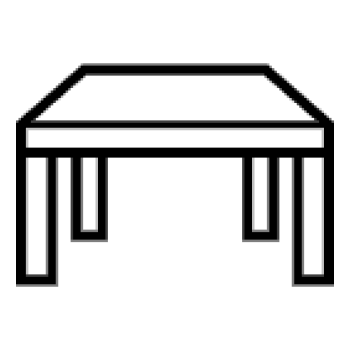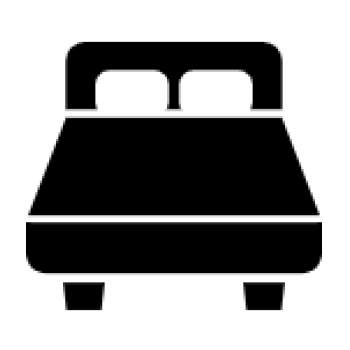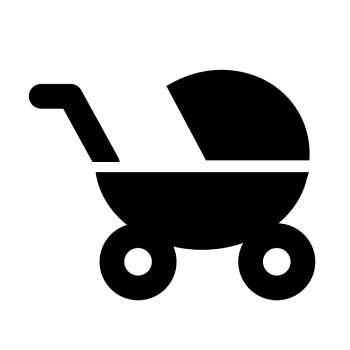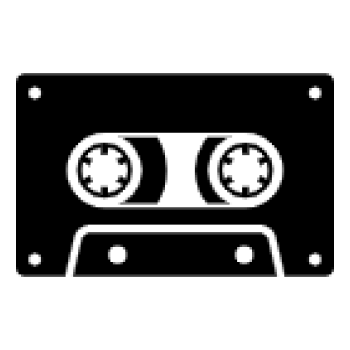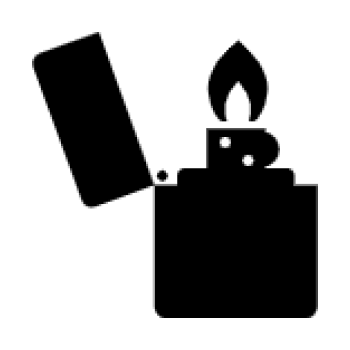障子は、和の雰囲気を演出する日本の伝統的な建具であり、長らく私たちの生活空間に溶け込んできた存在です。柔らかな光を取り込む障子のある和室は、どこか心を落ち着けてくれる特別な空間でもあります。しかし、そんな障子も長年使い続けていれば、和紙が黄ばんだり破れたり、木枠が歪んできたりといった劣化が避けられません。とくに子どもがいるご家庭では、障子が破れる機会も多く、張り替えやメンテナンスの手間が気になってしまうこともあるでしょう。
また、住まいのリフォームや和室の洋室化、さらにはマンションや集合住宅への住み替えなどのライフスタイルの変化に伴って、「もう障子は必要ない」と感じる家庭も少なくありません。高齢化や終活の一環として、使わなくなった障子を整理したいというケースも増えています。実際、障子の張り替え目安は数年に一度ですが、破損の程度によっては「張り替えるより処分したい」という選択肢も現実的です。
この記事では、障子を手放す際に知っておきたい基本情報や、素材ごとの注意点、具体的な処分方法、さらには費用や売却のコツまで丁寧に解説していきます。障子との別れを、スムーズで納得のいくものにするために、ぜひ参考にしてください。
障子の種類と素材別の特徴
和紙製の障子
最も一般的な障子は、和紙を使用した伝統的なタイプです。障子と聞いてまず思い浮かべるのがこの和紙製でしょう。光をやわらかく通し、部屋全体に穏やかな雰囲気をもたらす一方で、和紙は非常に繊細な素材でもあります。少しの衝撃でも破れやすく、ペットや小さなお子さんがいる家庭では特に破損が起きやすいのが難点です。そのため、定期的な張り替えが必要になることも少なくありません。
和紙は燃えるごみとして扱える自治体が多いため、障子紙部分の処分は比較的簡単です。ただし、障子の枠から和紙を剥がす作業が必要で、破れたまま出すと適切に回収されない場合もあるため、丁寧な分別が求められます。処分時には、和紙と木枠を分離し、それぞれの素材に応じて処理することが望ましいでしょう。
プラスチック製の障子紙
最近は、より扱いやすく破れにくい「プラスチック製障子紙」を使った障子も登場しています。このタイプの障子紙は、見た目は和紙に似ているものの、実際には合成樹脂素材で作られているため、耐久性が高く、水拭きできるという利点もあります。特に賃貸物件や子ども部屋など、破れや汚れのリスクが高い場所では、こうした素材が好まれます。
ただし、処分の際には注意が必要です。プラスチック製の障子紙は、自治体によって「可燃ごみ」ではなく「不燃ごみ」や「プラスチック資源ごみ」に分類されることがあります。紙と異なり自然分解されないため、分別が厳格な自治体では誤って出すと収集されないケースもあります。また、見た目が和紙と酷似しているため、間違えないように製品表示や材質表示を確認することも大切です。
木枠の素材による違い
障子の枠部分には、主にヒノキやスギなどの天然木材が使用されることが多く、国産材を使ったものは特に質感が高く、見た目にも高級感があります。こうした木材は耐久性があり、適切に手入れすれば長持ちするため、長年使っている家庭も多いでしょう。しかし、年月とともに枠が歪んだり、木が反ったりしてくると、張り替えも難しくなり、処分を検討するタイミングが訪れます。
天然木の枠は、一般的な可燃ごみや不燃ごみとしては出せないサイズや重量であることが多く、多くの自治体では「粗大ごみ」に分類されます。処分する際は、木枠をのこぎりでカットしてサイズを小さくすれば、可燃ごみとして出せる場合もありますが、解体作業は手間がかかる上、安全面にも配慮が必要です。また、釘や金属部品が使われている場合、それらを取り除いて別途処分する必要があり、時間と手間を要します。
障子の処分時の注意点について
自治体ごとの分別ルールを必ず確認しよう
障子を処分する際、最も重要なのが自治体のごみ分別ルールを確認することです。自治体ごとに、素材やサイズによって処分方法が異なるため、一律に「可燃ごみ」として出せるとは限りません。たとえば、和紙は多くの地域で「可燃ごみ」として扱われますが、プラスチック製の障子紙は「プラスチックごみ」や「不燃ごみ」とされることがあり、分別を間違えると回収されず、自宅前に置き去りにされることもあります。
また、木製の障子枠はサイズが大きいため、「粗大ごみ」として扱われるケースが多く、処分には事前予約や処理券の購入が必要です。粗大ごみとして出す際には、自治体が指定する方法(たとえば所定の場所に出す、電話またはオンラインでの申し込みなど)に従って手続きを行う必要があります。自治体の公式サイトや、配布されているごみ分別ガイドを参考にし、適切な分別と処分を心がけましょう。
紙と木枠を分解して処分するとスムーズ
障子をそのまま一体で処分するのではなく、「紙」と「木枠」を分解して処理することで、処分がよりスムーズになります。特に和紙製の障子紙は、破れていたとしてもそのまま枠についた状態では適切に分別されない場合があります。剥がした障子紙は丸めて袋に入れ、可燃ごみとして出すのが一般的です。一方、木枠部分はサイズを測り、指定の寸法以下であれば、のこぎりなどでカットして可燃ごみとして出せるケースもあります。
分解の際には、ガムテープや接着剤で強く貼り付けられている部分があるため、丁寧に剥がす作業が必要です。また、木枠に金属の釘や金具が使われていることも多く、これらは取り外して別途処分する必要があります。細かく分別することで、ごみの回収がスムーズになり、環境にも配慮した処分が可能になります。処分後にトラブルにならないよう、事前にしっかり分解作業を行いましょう。
不用品回収業者を利用する場合の注意点
大きな障子を自力で処分するのが難しい場合や、枚数が多くて手間がかかる場合には、不用品回収業者に依頼する方法もあります。ただし、業者選びには注意が必要です。まず、料金体系が明確かどうかをチェックしましょう。「基本料金無料」「即日対応」などの言葉に惹かれて依頼すると、後から高額な追加料金を請求されるケースもあります。必ず事前に見積もりを取り、総額を確認してから依頼しましょう。
また、信頼できる業者かどうかを見極めるためには、インターネット上の口コミや評価、運営会社の実績を確認することが有効です。公式サイトが整っていなかったり、所在地が曖昧だったりする業者は避けるのが無難です。不用品回収には適切な許可が必要なため、「一般廃棄物収集運搬業」の許可があるかどうかも確認しておくと安心です。悪質な業者による不法投棄のリスクを回避するためにも、しっかりと下調べを行ったうえで依頼するようにしましょう。
障子を少しでも高く売るコツ
清掃と状態確認で見た目の価値を高める
障子を少しでも高く売るためには、まず第一に「見た目の印象」を整えることが非常に重要です。買い手が最も気にするのは商品の状態であり、障子紙に破れやシミがある場合は、事前に張り替えることで印象が大きく向上します。特に和紙の白さや木枠の色味は、清潔感や丁寧に使われていたかを感じさせるポイントです。木枠部分にホコリや汚れが付いている場合は、やわらかい布で優しく拭き取っておきましょう。木枠の角がささくれていたり割れている場合は、軽くサンドペーパーで整えるだけでも印象が良くなります。
また、障子の数が複数ある場合は、「セット販売」することで全体的な価値が上がる可能性もあります。一枚ずつ売るよりも、まとめて使いたいと考えている人にとっては魅力的に映るからです。見た目と手入れの丁寧さは、買い手の購入意欲を大きく左右するため、しっかりとメンテナンスしてから出品しましょう。
詳細な情報と魅力的な写真で購買意欲を引き出す
商品をオンラインで売却する場合、情報の正確さと写真の質が売却価格に大きく影響します。まず記載すべき情報として、障子のサイズ(高さ・幅・厚さ)、木枠の素材(ヒノキ、スギなど)、障子紙の種類(和紙、プラスチック製など)、使用年数、使用状況(どの程度使われていたか)などがあります。こうした情報が丁寧に書かれていることで、購入者に安心感を与えることができ、相場より高い価格で売れることもあります。
写真は必ず明るい場所で、障子全体がはっきりと写るように撮影しましょう。木枠の質感や、障子紙の張り具合が分かるように、部分的なアップ写真も数枚用意しておくと効果的です。美しく撮影された写真と丁寧な説明文は、購入者の信頼を得やすく、価格交渉でも有利に働きます。写真1枚で商品価値が変わることもあるため、手間を惜しまず丁寧に撮影しましょう。
販売先の選定とDIY需要の活用がカギ
障子を高く売るためには、どこで売るかという「販路選び」も重要です。メルカリやヤフオクなどのフリマアプリは、個人同士のやり取りが基本のため、価格設定や取引条件を柔軟に調整できます。送料を購入者負担にしたり、「引き取り限定」で出品すれば、大きな障子でも送料の負担を気にせずに売却できる可能性があります。また、地元密着型の掲示板サイト(ジモティーなど)も、手渡しでの取引に向いており、配送が難しい大型の障子には最適です。
さらに、最近ではDIY素材としての障子にも注目が集まっています。とくに古民家風の内装やリノベーションに使いたいと考える個人や店舗オーナーなどにとって、味のある木枠や風合いのある障子紙は魅力的に映ります。このようなニーズに合わせて「アンティーク障子」「DIY素材としてもおすすめ」などの文言を商品タイトルに加えると、関心を引きやすくなります。販路とターゲットを意識した売り方が、障子をより高く売るコツといえるでしょう。
障子の処分方法4選
自治体のごみ回収(燃えるごみ・粗大ごみ)として出す方法
障子の最も基本的な処分方法は、各自治体のごみ回収ルールに従って出す方法です。多くの自治体では、障子紙は「可燃ごみ」、木製の枠部分は「粗大ごみ」または「不燃ごみ」として扱われます。まず障子紙は枠から丁寧にはがし、小さくたたんで自治体指定のごみ袋に入れて可燃ごみとして出します。プラスチック製の障子紙であれば、不燃ごみ扱いとなることもあるため、材質の確認も重要です。
木枠部分については、一定のサイズ以下であれば燃えるごみや不燃ごみとして出せる地域もありますが、多くの自治体では粗大ごみ扱いとなります。粗大ごみに該当する場合は、事前に申し込みをして回収日を指定し、処理券(有料)を購入・貼付する必要があります。のこぎりなどを使って解体すれば、通常のごみとして出せるケースもありますが、作業には注意が必要です。自治体のルールは地域によって異なるため、事前に市区町村の公式サイトや清掃局に確認することが大切です。
リサイクルショップや専門業者に引き取ってもらう方法
状態の良い障子や、デザイン性のある古い建具は、リサイクルショップやアンティーク専門店で引き取ってもらえる場合があります。特に、昭和初期〜戦前の時代に作られた木工障子などは、素材の良さや職人技が評価され、買い手がつくことも少なくありません。また、最近は古民家ブームや和風リノベーションの需要により、障子を再利用したいと考える個人やインテリア業者からのニーズも高まっています。
ただし、一般的な量産型の障子や、障子紙が破れていたり、木枠が劣化している場合は、買取不可となることがほとんどです。店舗に持ち込む前に、電話やメールで写真を送って査定を依頼すると効率的です。買取が難しい場合でも、無料で引き取ってもらえることもあるため、まずは問い合わせてみる価値はあるでしょう。
リサイクルを通じて、障子を誰かに再利用してもらえるのは、環境に優しいだけでなく、処分コストの削減にもつながります。資源を無駄にしないという観点からも、有力な処分方法の一つです。
DIYでリメイクや再利用する方法
障子を処分する代わりに、自分でリメイクして再利用するという選択肢も注目されています。近年はDIYブームの影響で、障子の木枠を使って棚や間仕切り、フォトフレーム、アクセサリースタンドなど、さまざまなアイテムに生まれ変わらせるアイデアが人気です。特に和の雰囲気を取り入れたインテリアが好まれる現代では、障子の再利用価値が見直されています。
木枠を好みのサイズにカットし、ペンキやオイルステインで塗装することで、雰囲気のあるアンティーク風のアイテムを作ることも可能です。障子紙を外し、ガラスやアクリル板をはめてディスプレイケースにしたり、LEDライトを取り付けて間接照明として使うといったアレンジもできます。
DIYが得意な方や、物を大切にしたい方にとっては、単なる「ごみ」として捨てるのではなく、新たな価値を生み出す機会となるでしょう。また、子どもの工作や趣味の素材としても再利用できるため、家庭内での活用方法を検討してみるのもおすすめです。
不用品回収業者に依頼する方法
障子を一度に複数枚処分したい、または木枠が大きく解体が難しいといった場合は、不用品回収業者に依頼する方法が便利です。業者に依頼すれば、自宅まで来てくれて搬出・運搬・処分まですべてを代行してくれるため、高齢者や力仕事が苦手な方にも適しています。特に引っ越しや家のリフォームなどで大量の障子を処分する際には、有力な選択肢です。
ただし、業者によって料金体系は大きく異なり、障子1枚あたり1,000円〜3,000円程度かかることが一般的です。トラックの積載量に応じた「定額パック」を提供している業者もあるため、障子以外の不要品もまとめて処分したい場合にはコストパフォーマンスが高くなります。一方で、悪質な業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれる恐れもあるため注意が必要です。
依頼する際は、必ず事前に見積もりを取り、追加料金の有無や回収日程を確認しましょう。インターネットで口コミをチェックしたり、許可を受けた正式な業者かどうかを確認することも大切です。
障子の処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は障子の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
障子を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!