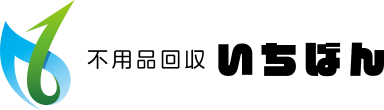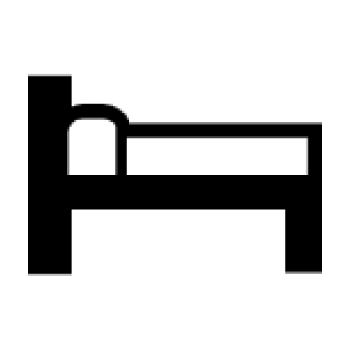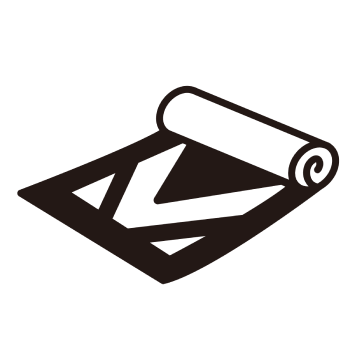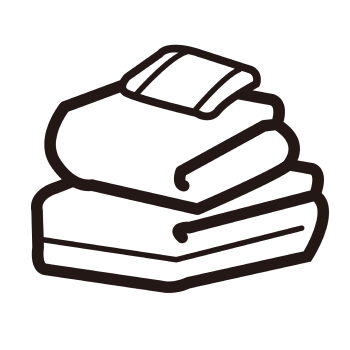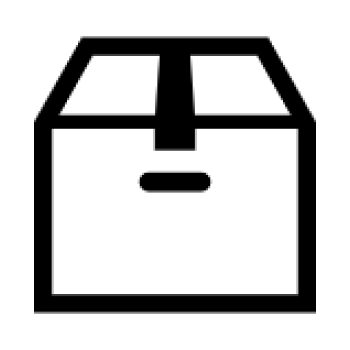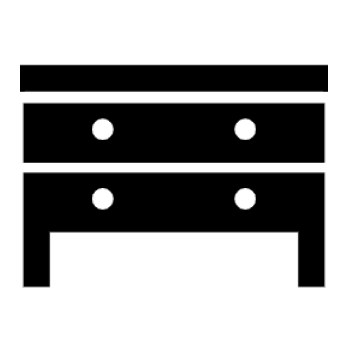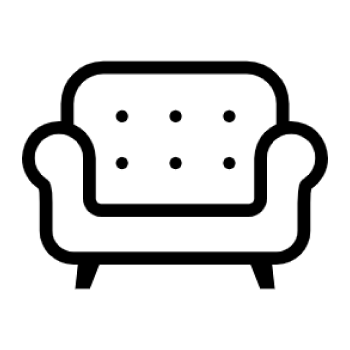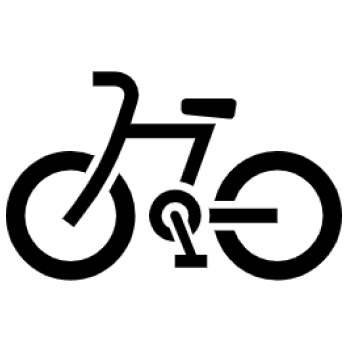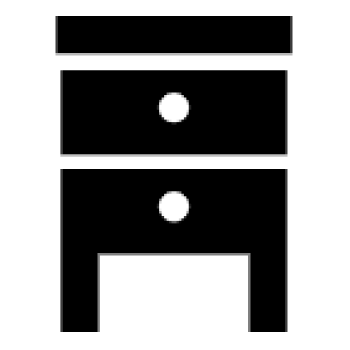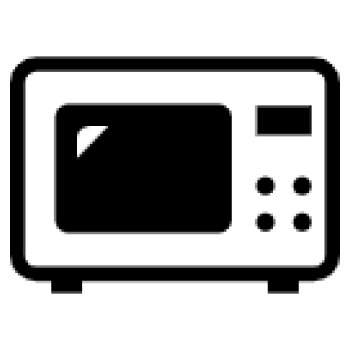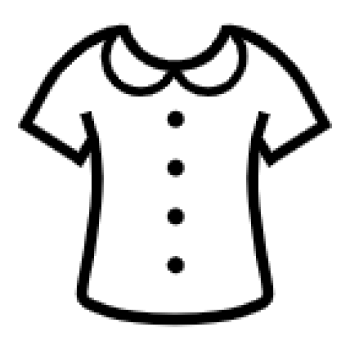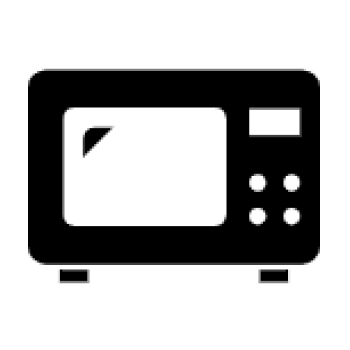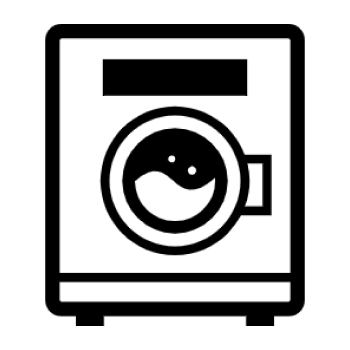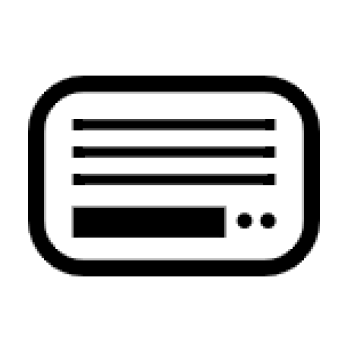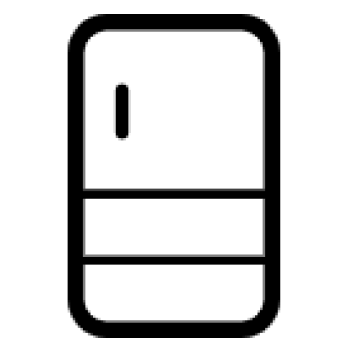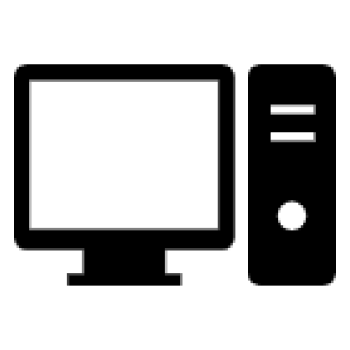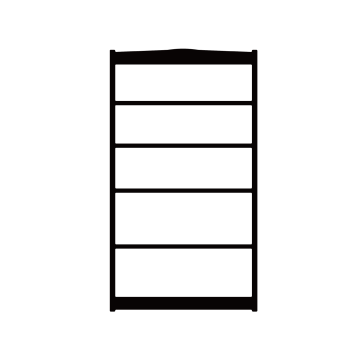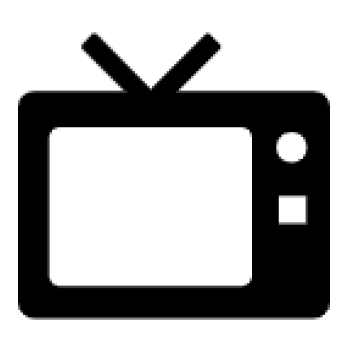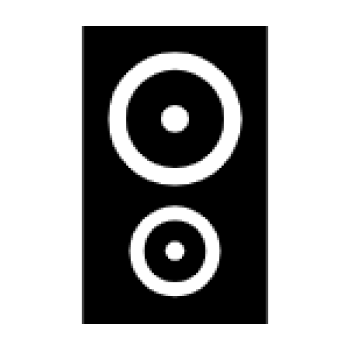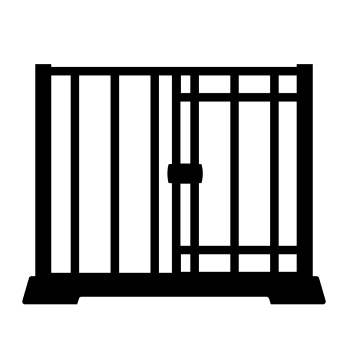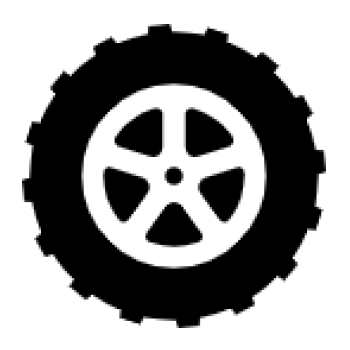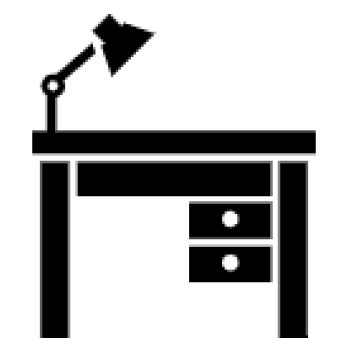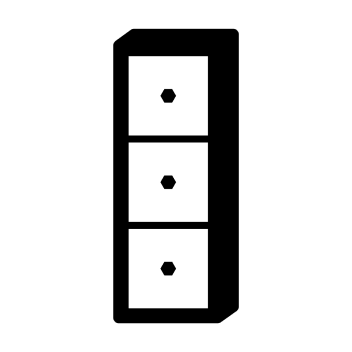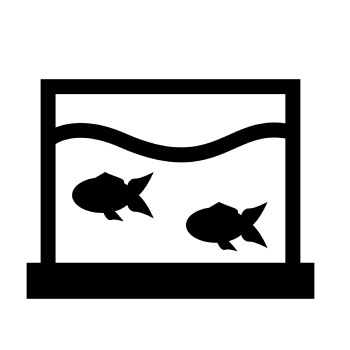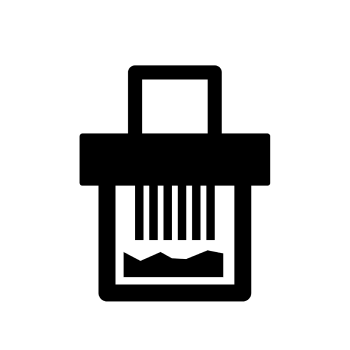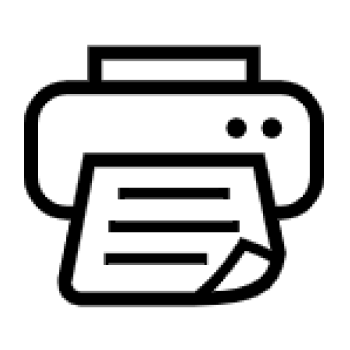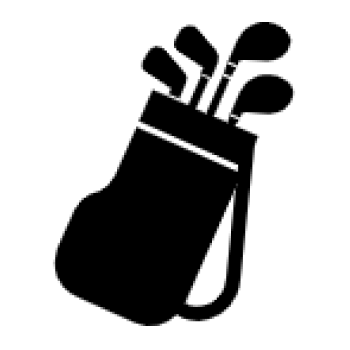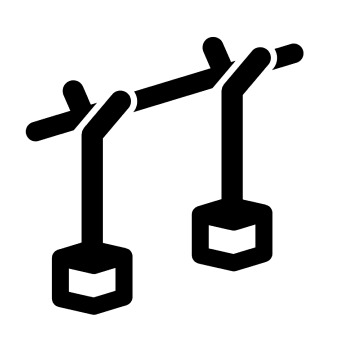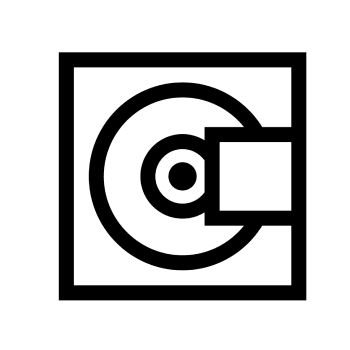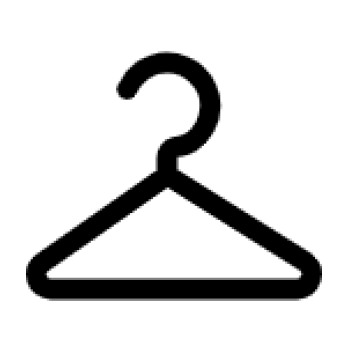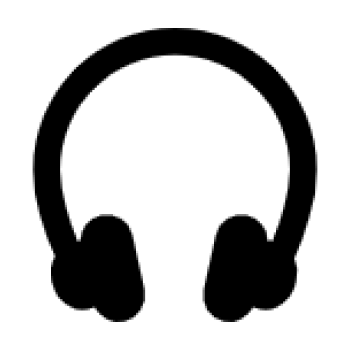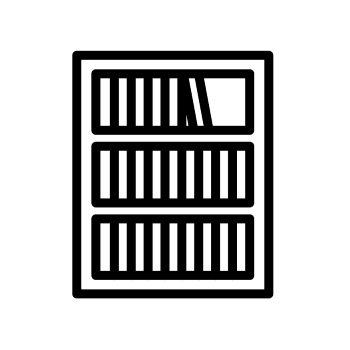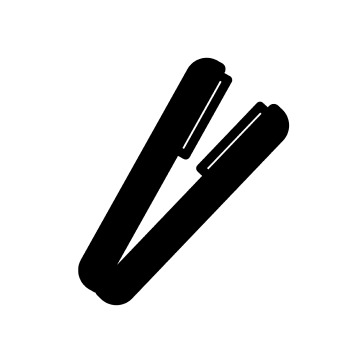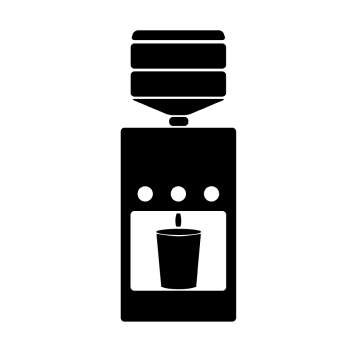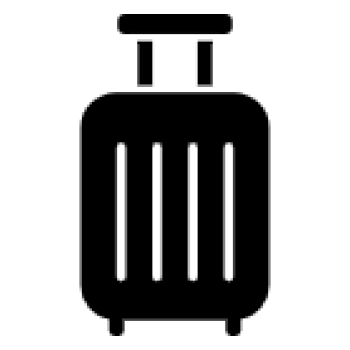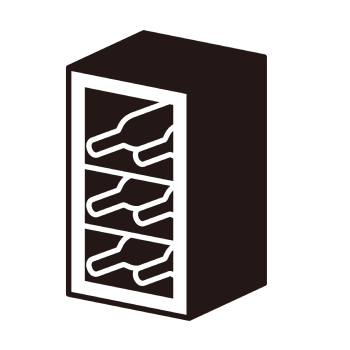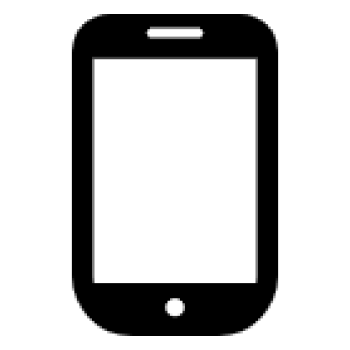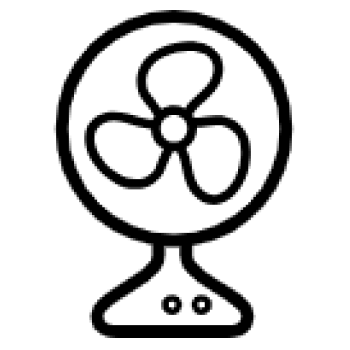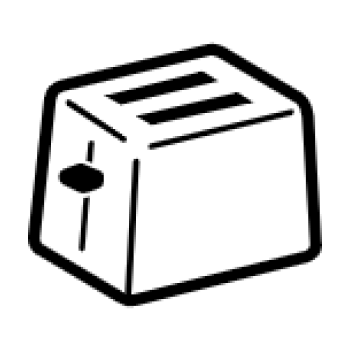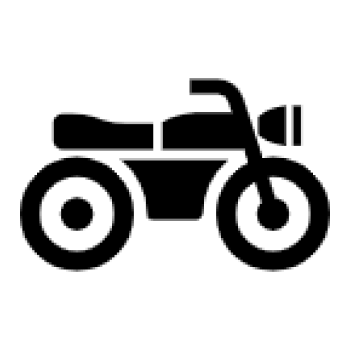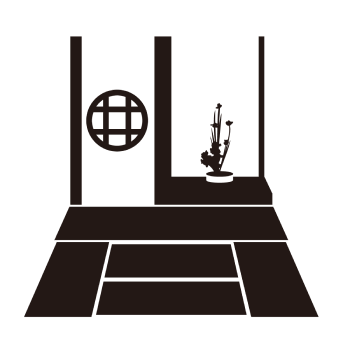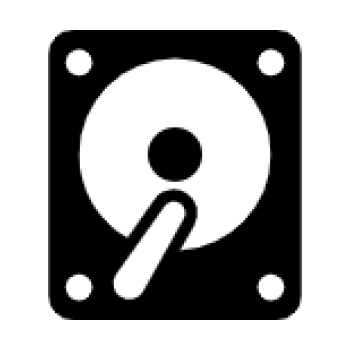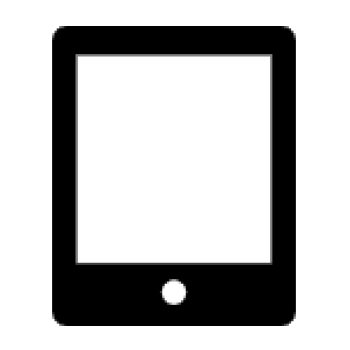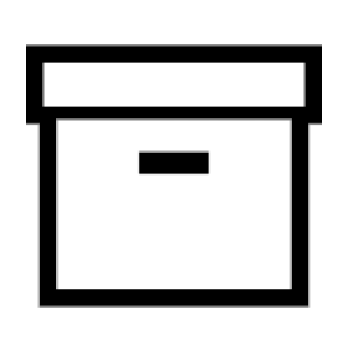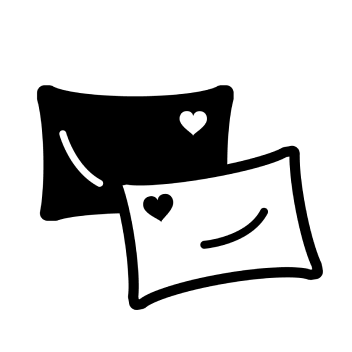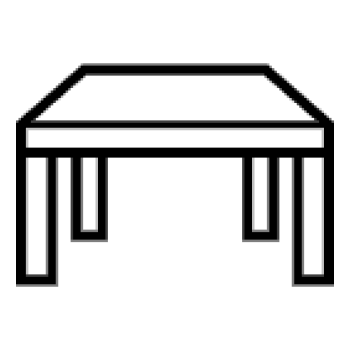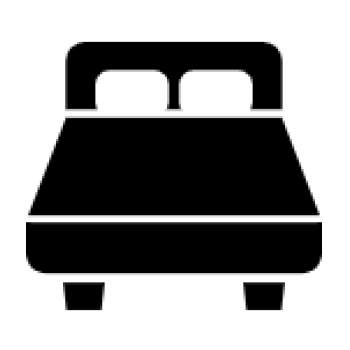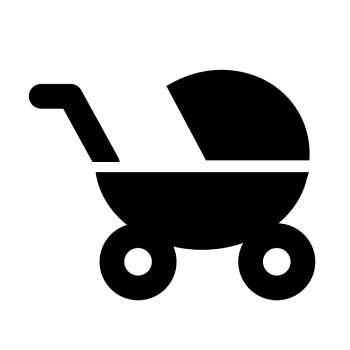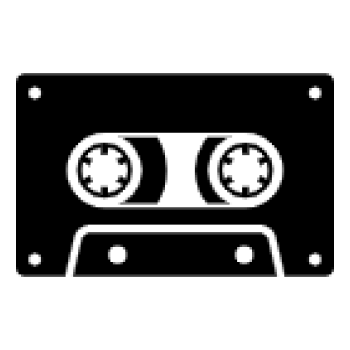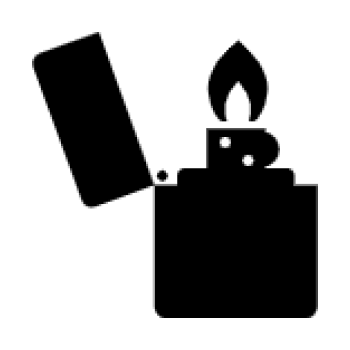庭木や枝木の処分は、家庭でのガーデニングや庭の手入れを行ううえで避けて通れない作業です。剪定や伐採をしてすっきりしたはいいものの、「切った枝をどう処分したらいいのかわからない」「量が多すぎて家庭ゴミでは出せない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。特に自治体によって処分ルールが異なるため、誤った方法で出してしまうと回収されなかったり、罰則の対象になることもあります。
また、処分方法には無料で行える方法から費用がかかる方法までさまざまで、状況によって適した選択肢も異なります。本記事では、庭木や枝木を処分するタイミングや注意点、枝木の種類の違いを踏まえたうえで、具体的な処分方法を詳しく解説していきます。適切な知識を身につけ、安全かつスムーズに庭木の整理を進めていきましょう。
庭木・枝木を処分するタイミング
庭木や枝木の処分を考えるタイミングには、いくつかの明確なきっかけがあります。庭の美観を保つためにも、また衛生面や安全面の観点からも、適切な時期を見極めて計画的に処分を進めることが重要です。処分のタイミングを見誤ると、ただ単に庭が荒れて見えるだけでなく、害虫やカビの発生、近隣トラブルの原因になることもあるため、慎重な対応が求められます。
剪定や伐採を行った直後
まず基本となるのは「剪定や伐採を行った直後」です。庭木の剪定は、樹種や目的によって時期が異なりますが、一般的には植物の成長が緩やかになり、ダメージを受けにくい休眠期、すなわち秋から冬、または春先に行われることが多いです。特に落葉樹の場合、葉がすべて落ちた冬の間に剪定を行うと、枝ぶりがよく見えて作業しやすい上に、木にかかる負担も少なくて済みます。このようなタイミングで剪定を行えば、同時に枝木の処分も計画できるため、非常に効率的です。
一方、常緑樹の場合は比較的年間を通じて軽い剪定が可能ですが、それでも太い枝を切るような「強剪定」は冬季に行うのが望ましいとされています。強剪定後は一時的に大量の枝が出るため、速やかな処分を前提とした準備が欠かせません。放置すると腐敗や病害虫の発生源になり、他の木にも影響を与える可能性があります。
自然災害後
次に挙げられるのは「自然災害後」の処分です。台風や豪雨、積雪などによって木が折れたり傾いたりすることがあります。特に風の強い台風の後は、折れた枝が隣家に落下したり、道路に散乱して通行を妨げたりする危険性があるため、速やかな対応が必要です。こうした状況では、応急的な処理だけでなく、被害のあった木の根元から伐採が必要なケースもあり、処分する枝の量も通常よりはるかに多くなります。こうした災害後の片付けでは、自治体の臨時回収を利用できることもあるため、地域のルールや対応状況を確認しておくとよいでしょう。
生活環境の変化
さらに、「生活環境の変化」が枝木の処分につながることも多々あります。たとえば、高齢の家族が庭の手入れを続けることが難しくなったことをきっかけに、長年手を加えてきた庭木を整理しようと考える家庭も少なくありません。草木の成長が旺盛な庭は、維持管理にかなりの手間と時間がかかります。
体力的に厳しくなると、いずれは荒れ庭となってしまうリスクがあるため、元気なうちに庭木を間引いたり、伐採したりするという判断は理にかなっています。こうした大掛かりな作業を伴う場合には、当然ながら大量の枝や幹が発生し、処分計画をあらかじめ立てておくことが重要です。
敷地外に出た時
また、「隣家や道路に枝がはみ出すようになった」「庭木の根がコンクリートや配管を圧迫している」といったケースでも、伐採や剪定を行い、処分のタイミングを迎えることになります。こうした場合には、トラブルを未然に防ぐという意味でも早めの対応が肝心です。特に都市部では、庭のスペースが限られている分、境界を越えた枝の処理がトラブルの火種となりやすいため、近隣への配慮と定期的な手入れが求められます。
さらに見落としがちですが、剪定や伐採の直後だけでなく、「剪定作業の前段階」であっても処分のタイミングを見極める価値はあります。たとえば、剪定で出る量が多くなると予想される場合、事前に可燃ごみ・粗大ごみの回収日を調べたり、不用品回収業者への依頼を検討したりすることで、作業後の処理をスムーズに行うことができます。作業と処分を同じ日に終わらせることで、庭が一時的に荒れることも避けられ、近所からの印象もよく保てます。
このように、庭木や枝木の処分タイミングは単に「剪定した後」という一言では済まされません。季節、災害、生活環境の変化、さらには近隣との関係といった、さまざまな要素が絡み合って「今が処分のタイミングだ」と判断できる瞬間が生まれるのです。大切なのは、その瞬間を見逃さず、適切な手段で素早く対処すること。処分を後回しにせず、日頃から「手入れのあとは処分までがワンセット」という意識を持っておくことで、美しく整った庭を維持できるだけでなく、安全で快適な生活環境も守ることができるのです。
処分する際の注意点
庭木や枝木を処分する際には、いくつかの重要な注意点を事前に理解しておく必要があります。これらを知らずに処分を進めてしまうと、回収してもらえなかったり、罰則の対象になったり、近隣トラブルを引き起こしてしまうリスクもあります。スムーズで安全に処理を行うために、あらかじめ把握しておきたいポイントを詳しく解説します。
自治体ごとのルールを確認する
まず第一に押さえておきたいのが、「自治体ごとのルールを確認する」という点です。枝木のような自然ごみは、単純に「燃えるごみ」として出せるわけではなく、多くの自治体では枝の長さや太さ、本数、束ね方など、細かいルールが定められています。たとえば、「枝の直径は10cm以下」「長さは50cm以内」「1回の収集で出せるのは5束まで」といった制限がある場合もあります。このようなルールに従わずに処分してしまうと、当日に収集してもらえなかったり、改善を求められて再度出し直すことになってしまいます。
縛るものの素材
また、枝を束ねる際にも注意が必要です。たとえば「麻紐などの天然素材で縛る」ことが求められることがあり、ビニール紐やガムテープでまとめてしまうとルール違反になることもあります。自治体の公式ウェブサイトやごみ分別アプリなどで、必ず最新の情報を確認してから処分準備を進めましょう。特に引越しなどで地域が変わった場合は、以前のルールと違う可能性があるため、要注意です。
量に応じた適切な処分方法を行う
さらに、量の多い枝木を処分する場合には、「一度に出さず、数回に分けて処分する」「粗大ごみとして申し込む」「クリーンセンターへ直接持ち込む」など、量に応じた適切な処分方法を検討する必要があります。一軒家の庭を大きく整理したあとなどは、トラック1台分以上の枝木が出ることもあります。そうした場合には、一般のごみ回収では対応しきれないため、不用品回収業者への依頼を検討することも現実的な選択肢です。料金はかかりますが、すべてを一括で片付けてくれるため、時間や労力の節約につながります。
安全面に配慮する
また、安全面での注意も欠かせません。庭木の中にはトゲのあるバラやユッカ、アロエなど、手や腕を傷つけやすい植物もあります。処分作業中にケガをしないよう、厚手の軍手、長袖・長ズボン、保護メガネなどを着用し、十分な防護をしたうえで作業を行うことが大切です。特にトゲのある枝や、乾燥して折れやすい枝などは、作業中に跳ね返って顔や手を傷つけることがあるため、慎重に扱うようにしましょう。
毒性を持つ植物にも注意が必要です。たとえば、キョウチクトウやスズランなどは強い毒性があるため、剪定中に出た樹液が皮膚に触れることで炎症やかぶれを起こすことがあります。こうした植物は、処分時にも一般の枝木と分けて対処し、むやみに燃やしたり砕いたりせず、自治体の指示に従って適切に処理する必要があります。
剪定後の枝木を放置する
剪定後の枝木をそのまま放置しておくことも避けるべきです。時間が経つと乾燥して腐食が進み、害虫の温床となる恐れがあります。特にシロアリやゴキブリ、カミキリムシなどが発生しやすく、そこから建物や他の植物に被害が広がることもあります。さらに、雨水によってぬかるみや悪臭が生じることもあるため、剪定や伐採後は速やかに処分の段取りを行いましょう。
環境への配慮も、現代における重要な観点です。一部地域では、庭木の枝を「資源ごみ」として処理するためのリサイクル施設が整っているところもあります。たとえば、枝木を細かく砕いて「木材チップ」として再利用する自治体も増えており、処分の際に回収場所や日時が指定されていることがあります。焼却処分と違ってCO₂の発生を抑えられるため、できる限りリサイクルの選択肢を利用することが推奨されます。
このように、枝木の処分と一口に言っても、自治体のルール、安全面、環境配慮など、さまざまな観点から注意が必要です。特に剪定のシーズンは他の家庭でも処分が集中するため、タイミングを見計らって余裕を持って準備することが大切です。面倒に感じるかもしれませんが、正しい知識と心構えで処分に臨むことで、自分にも地域にも優しい庭づくりが実現できます。
種類ごとの処分方法
枝の太さと木の種類
庭木の処分において、最も重要なポイントは「枝の太さ」と「木の種類」です。これらの要素によって、処分方法が大きく異なります。
- 細い枝や柔らかい木: 例えば、ヤマボウシやモミジ、サクラなど、比較的細く柔らかい枝の木は処分がしやすいです。これらの木は家庭ゴミとして処理できる場合が多く、自治体のルールに従って束ねて出すことが可能です。さらに、細かい枝であれば、剪定くずとして家庭でコンポスト化することも可能です。こうした木材は、燃やしても問題ないため、自治体によっては可燃ごみとして簡単に処理できます。
- 太く硬い木: 一方、カシやケヤキ、クスノキなど、太くて硬い木は処理が非常に困難です。これらの木は切断が難しく、通常の家庭用の道具では対応できません。そのため、こうした木材の処分には専門的な知識と道具が必要となります。多くの自治体では、太い木や幹部分は「粗大ごみ」として扱われ、収集が難しい場合もあります。そうした場合、業者に依頼して処理してもらうのが一般的です。
常緑樹と落葉樹の違い
庭木には、常に葉が茂っている「常緑樹」と、季節によって葉が落ちる「落葉樹」があります。これらの違いは、処分方法にも影響を与えます。
- 常緑樹: 常緑樹は一年中葉が残り、葉の量が多くなるため、処分にはやや手間がかかります。特に、夏場や秋に大量の葉が落ちるため、定期的に剪定を行う必要があります。剪定後に出る葉や枝は、可燃ごみとして処理することが一般的ですが、葉の量が多い場合、自治体が定めたルールに従って分別して捨てる必要があります。また、常緑樹は害虫が付きやすいこともあり、処分の際には害虫の駆除や隔離が求められることもあります。
- 落葉樹: 落葉樹は、葉が落ちる時期が限られているため、その後の処理は比較的簡単です。しかし、落ち葉が大量に出るため、掃除や整理が大変になることがあります。落ち葉はそのままコンポストにすることができるため、処分後の再利用が可能です。枝や幹部分の処理も比較的簡単で、枝が細ければ家庭ごみとして出せますが、太い幹部分はやはり粗大ごみとして分別する必要があります。
竹や笹の処分
竹や笹は他の木に比べて非常に処分が難しいです。これらの植物は根が広がりやすく、周囲に被害を与えることもあるため、慎重に処分しなければなりません。
- 竹: 竹は成長が早いため、定期的に伐採しないと庭が竹に占拠されてしまいます。しかし、竹は非常に硬くて処理が難しく、自治体によっては可燃ごみとして処理できないことがあります。また、竹はその根が深く広がっているため、根を取り除かないと新たに竹が生えてくることがあり、根の処分は専門業者に依頼する必要がある場合もあります。竹は適切に処理しないと、次の生育を促進してしまう可能性があるため注意が必要です。
- 笹: 笹も竹と同様に広がりやすく、根を適切に処分しないと庭中に広がってしまいます。笹の葉や細い枝は可燃ごみとして処理できる場合が多いですが、根や太い幹部分は粗大ごみや産業廃棄物として扱われることがあります。笹を扱う際には根の取り除きが重要となり、根が広がっている場合は専門的な処分が必要です。
剪定くずと伐採した幹部分の処分
剪定くずと伐採した幹部分では、処分方法が大きく異なります。
- 剪定くず: 一般的に、剪定くずは細かいため、家庭で処理できることが多いです。枝が細く柔らかい場合は、家庭用のゴミ袋に入れて可燃ごみとして出せます。また、剪定くずをコンポストとして活用することもできます。自治体によっては、剪定くずを専門の回収ボックスに入れて出す方法もあります。
- 幹部分や根: 幹や根は非常に重く、硬いため、個人で処理することは難しいです。こうした部分は粗大ごみとして出すか、業者に依頼する必要があります。特に根は深く埋まっていることが多いため、専門的な道具を使わなければ処理が難しく、時間と手間がかかります。
庭木・枝木の具体的な処分方法5選!
自治体のごみ収集に出す
庭木の処分方法として最も一般的なのが、自治体のごみ収集に出す方法です。多くの自治体では、剪定した枝木や小さな木を一般ごみとして、または粗大ごみとして収集しています。しかし、自治体のルールにはいくつかの制約があるため、事前に確認しておくことが重要です。
例えば、枝木の長さや太さに制限がある場合が多いです。大きな枝は、一定の長さにカットしてから出さなければならないことがあります。また、細かく分割したり、ひもで束ねたりすることが求められることが一般的です。束ねる際のサイズや重さにも規定があるため、指定されたルールを守って準備を整える必要があります。
さらに、処分できる量にも上限が設定されていることがあります。特に剪定後に大量の枝木が出る場合、1回の収集で処理できる量には限りがあり、何回かに分けて出さなければならないことがあります。こうした制限に従わないと収集されない場合があるため、注意が必要です。また、収集日や時間帯にも指定があるため、自治体のホームページで最新の情報をチェックすることをおすすめします。
自治体のごみ収集は、手軽で安価に庭木を処分できる方法ですが、事前準備が求められます。複数回に分けて処分する必要がある場合もあるため、処分のタイミングをよく考えて準備を進めましょう。
ごみ処理センターに自己搬入する
大量の庭木を処分する場合、ごみ処理センターやクリーンセンターに自己搬入する方法があります。この方法では、自治体が運営する処理場に直接持ち込むことができるため、比較的安価に大量の枝木を処分することができます。特に自宅から運び出す手間を省き、近隣住民に迷惑をかけずに処分できる点が利点です。
ただし、この方法を利用するには、事前に自治体の規定を確認しておくことが重要です。一部の自治体では、クリーンセンターや処理場の利用には予約や申請が必要な場合があります。ホームページや電話で事前に確認し、予約が必要な場合は、適切な手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
運搬手段にも注意が必要です。軽トラックやワンボックスカーを使用して自分で持ち込む必要があるため、大量の枝木を処理する場合は車両のサイズや積載量を考慮する必要があります。また、自己搬入の場合でも、自治体によっては搬入制限や処理料金が発生することがあるため、事前に確認しておきましょう。
この方法は、大量の庭木を一度に処理できるため、特に自宅での庭木処分が難しい場合や、料金を抑えたい場合におすすめです。
造園業者や庭師に処分込みで依頼する
庭木の剪定や伐採を行う際、処分もセットでお願いする方法もあります。この方法では、造園業者や庭師に剪定を依頼する際に、処分を一緒にお願いすることができます。プロの業者は、庭木を適切にサイズにカットしたり、安全に伐採したりするだけでなく、その後の処分まで一貫して行ってくれるため、非常に安心です。
ただし、処分費用は通常、作業料金に含まれる場合と別途料金がかかる場合があります。事前に料金体系について確認しておくことが重要です。また、業者によっては、処分方法が異なる場合もあり、例えば焼却処理を行う業者もあれば、リサイクルや堆肥化を行う業者もあります。どのように処分するかを確認し、自分のニーズに合った業者を選ぶようにしましょう。
業者に依頼することで、安全かつ確実に庭木を処分してもらえるため、特に大きな木や枝の処分が必要な場合には便利です。時間や労力をかけたくない方には特におすすめの方法です。
焼却や堆肥化
一部の地域では、自家処理として庭木の焼却や堆肥化が認められている場合があります。これらの方法は、環境に配慮しながら庭木を処分する手段として利用できますが、実施する際には地域のルールを確認することが絶対に必要です。
- 焼却: 自宅での焼却は、一部の自治体では許可されていますが、屋外焼却が禁止されている地域も多く、違法となる可能性があります。また、焼却する際は、煙や火の管理が非常に重要であり、周囲に迷惑をかけないようにする必要があります。燃焼温度や時間、煙の処理方法についても確認しておくべきです。特に乾燥した枝木や葉は火がつきやすいため、十分な安全対策が求められます。
- 堆肥化: 自家処理で堆肥化する場合、庭木の枝や葉を堆肥として再利用する方法もありますが、堆肥化には時間がかかるため、注意が必要です。適切に管理しないと、悪臭が発生することがあるため、堆肥作りに必要な条件(湿度、酸素供給など)をしっかりと把握しておくことが重要です。
焼却や堆肥化を行う場合は、必ず自治体のルールに従い、合法的に処分するようにしましょう。
不用品回収業者に依頼する
剪定後の枝や幹が大量に出る場合、不用品回収業者に依頼することが便利です。自宅まで回収に来てくれるため、手間をかけずに庭木を処分できる点が大きな魅力です。特に重くて大きな木や、細かく分けることが難しい枝木などを処分する際に非常に有効です。自宅まで業者が出向いてくれるため、運搬の手間や時間を節約することができます。
ただし、注意しなければならないのは、費用面です。自治体による処分と比較して、業者に依頼する際の費用は高くなる場合が多いです。料金体系は業者によって異なり、通常、枝木の量や種類、処分の難易度によって料金が決まります。したがって、依頼前に複数の業者から見積もりを取り、料金の相場を把握しておくことが重要です。さらに、回収サービスには通常、対応地域が限定されているため、事前に自分の住んでいる地域がサービス対象かどうかを確認することも大切です。
不用品回収業者の利用は、時間や手間を大幅に削減できるため、忙しい方や大量の庭木を迅速に処分したい方にとって非常に便利な方法です。費用対効果をよく考えて依頼しましょう。
庭木・枝木の処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は庭木・枝木の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
庭木・枝木を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!