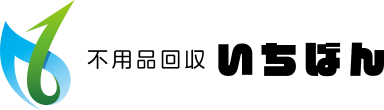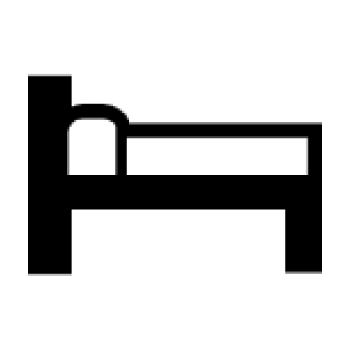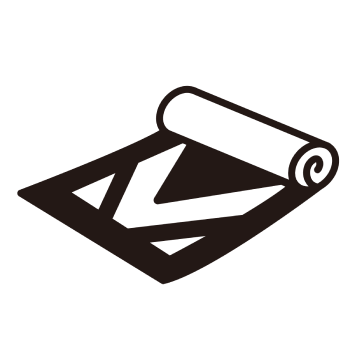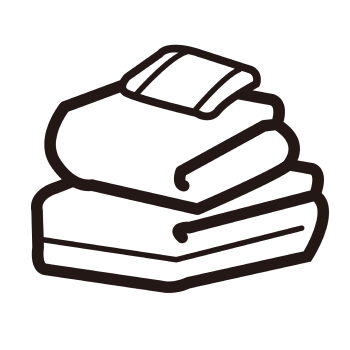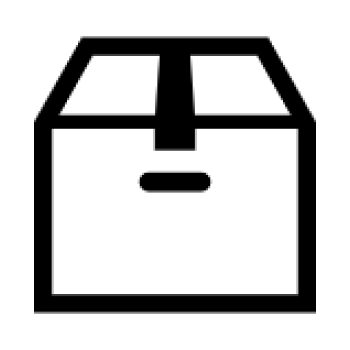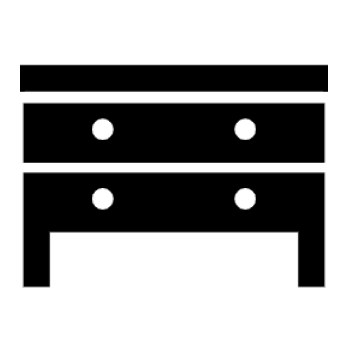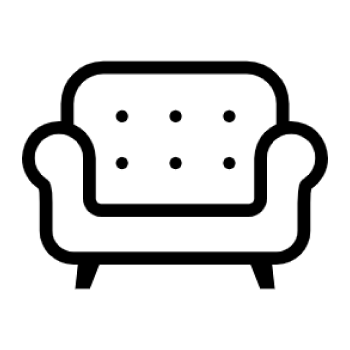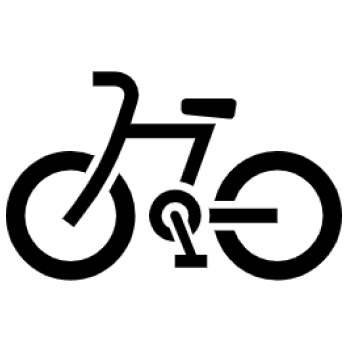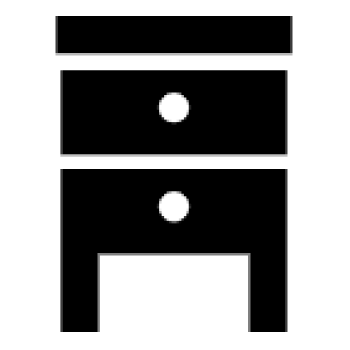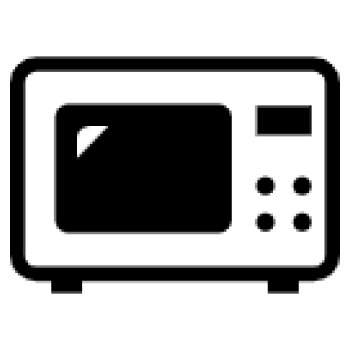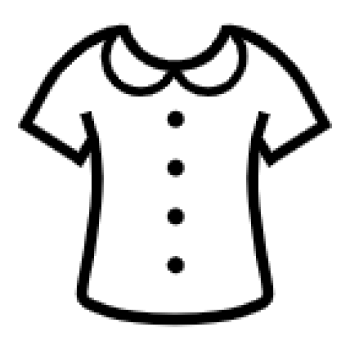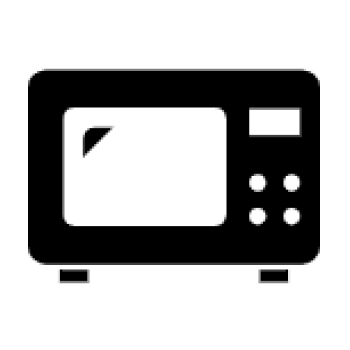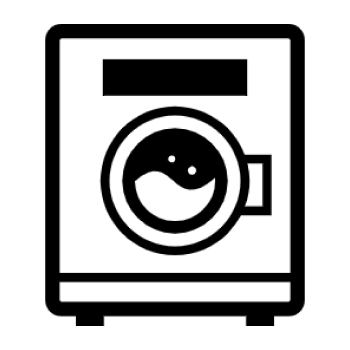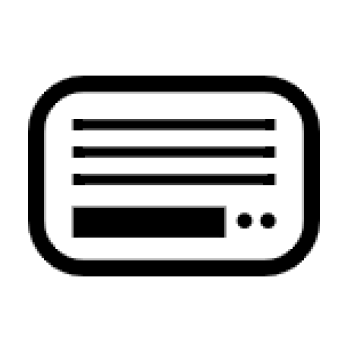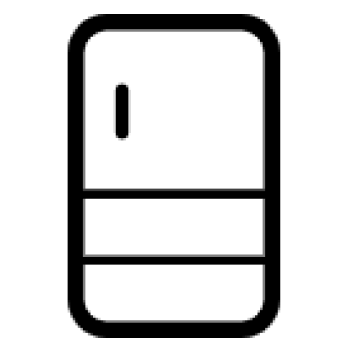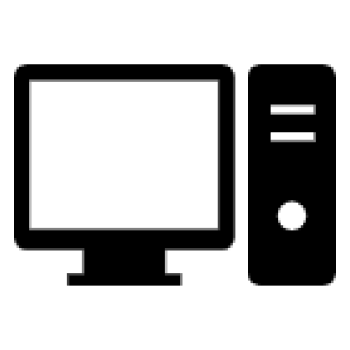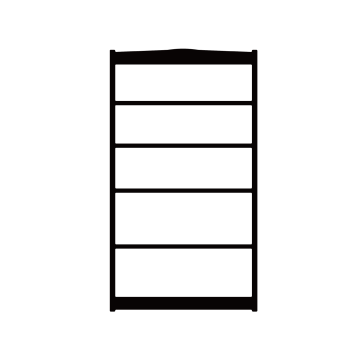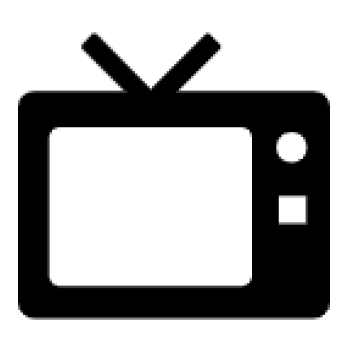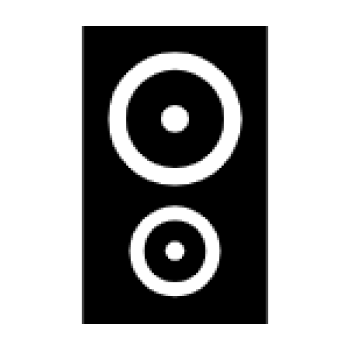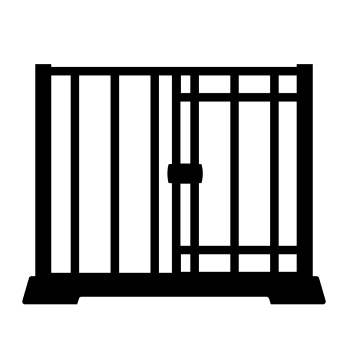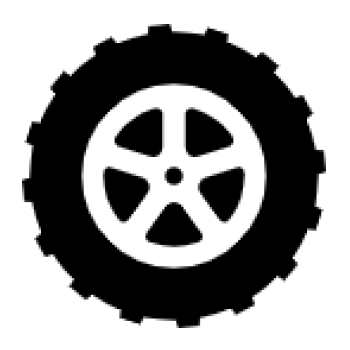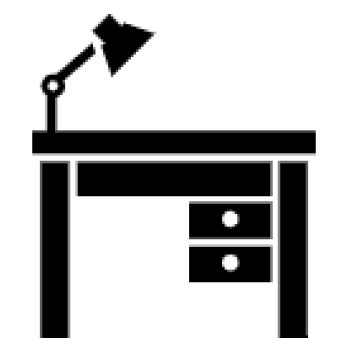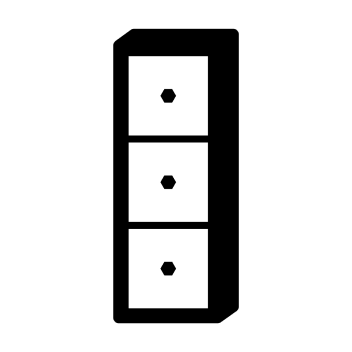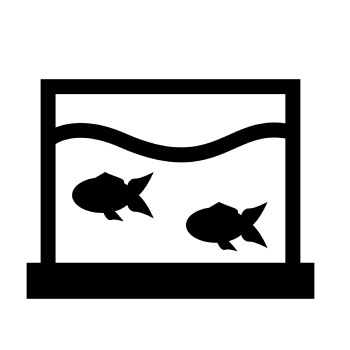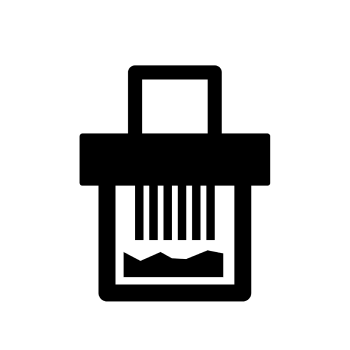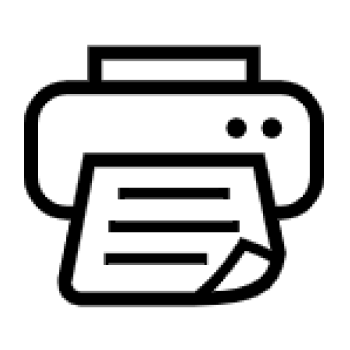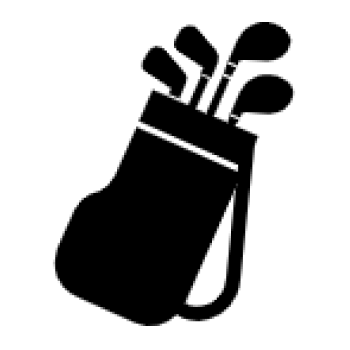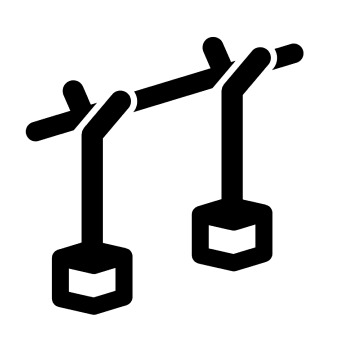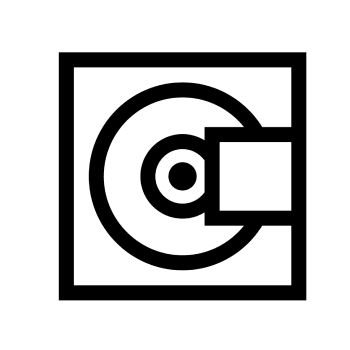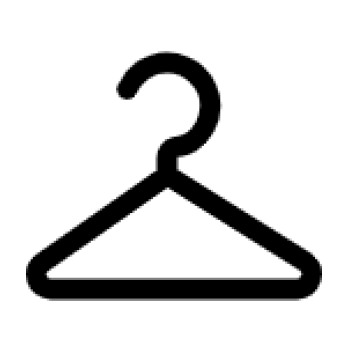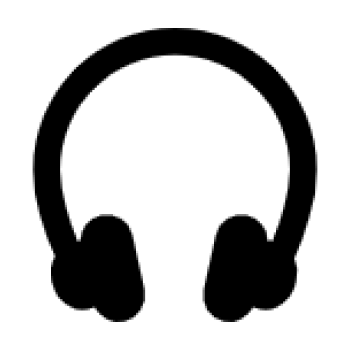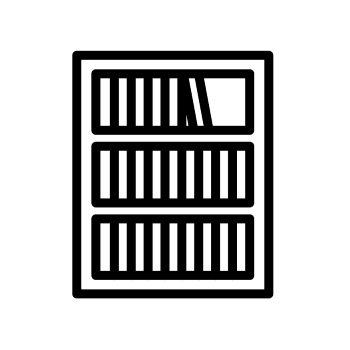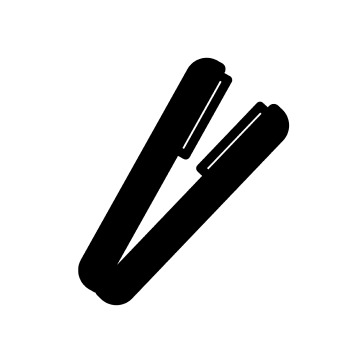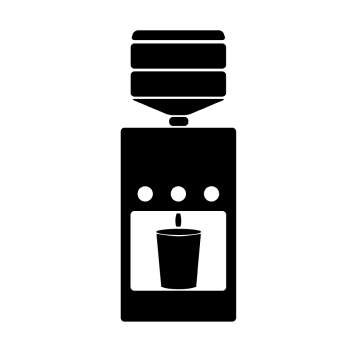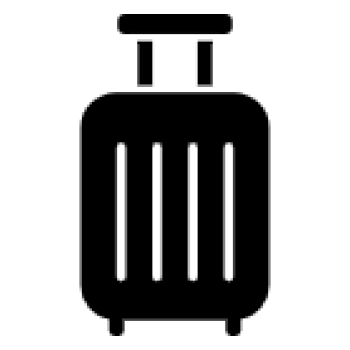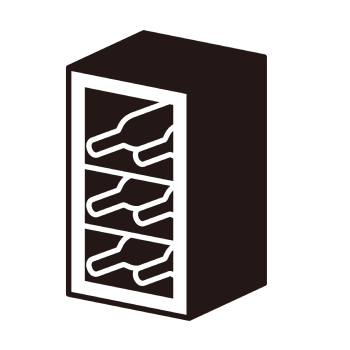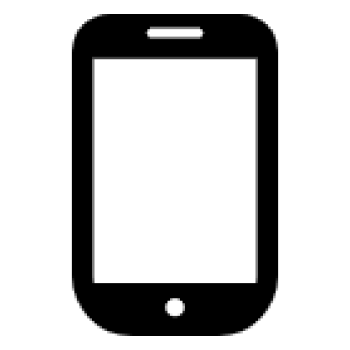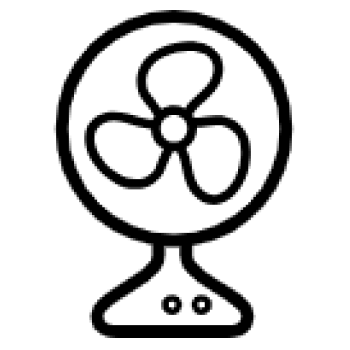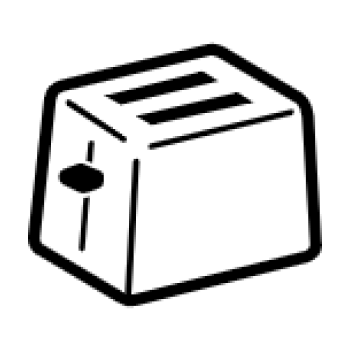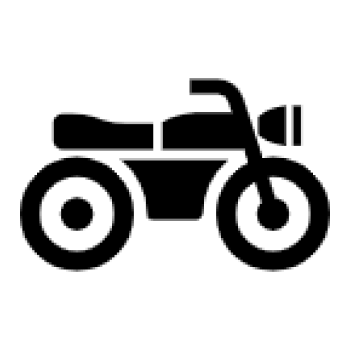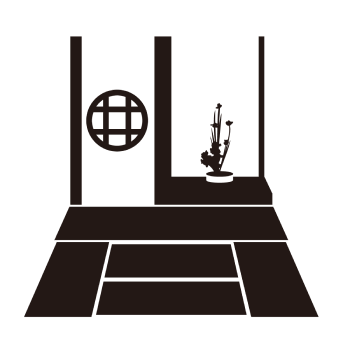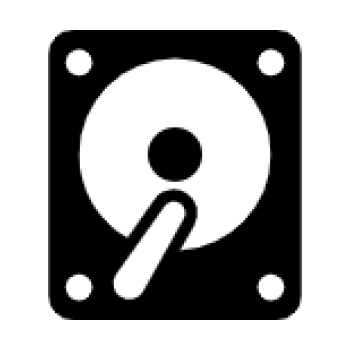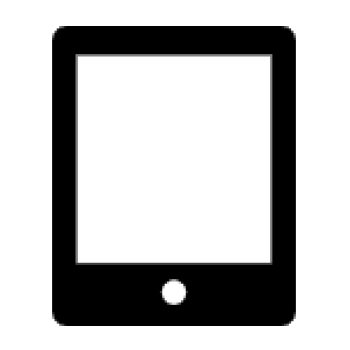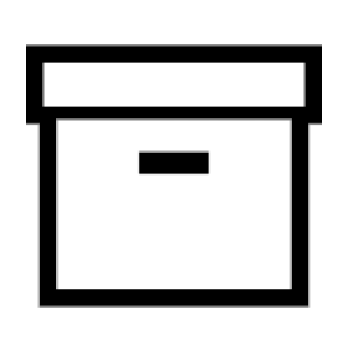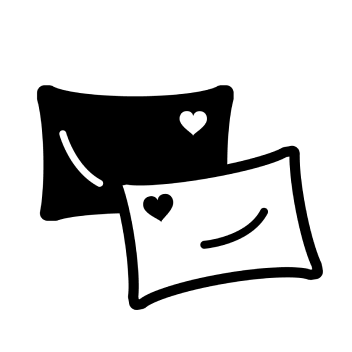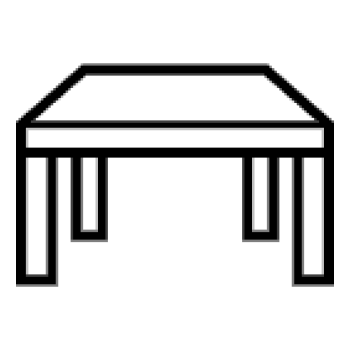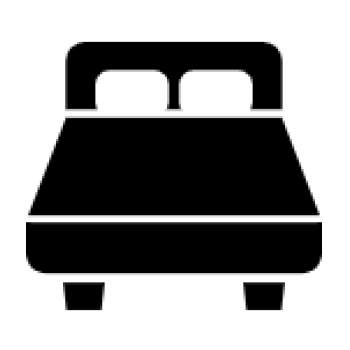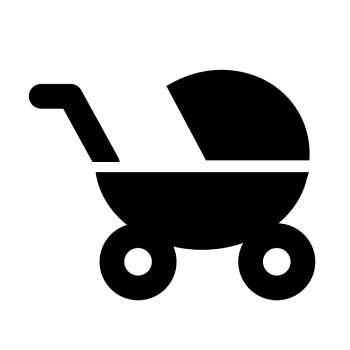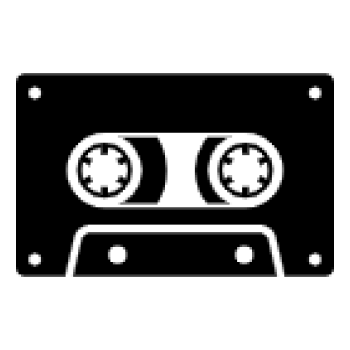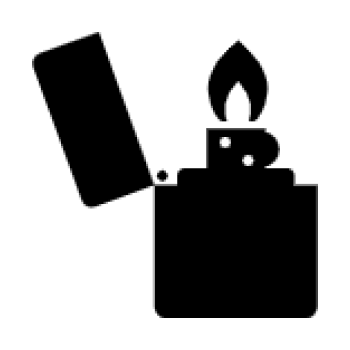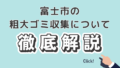近年、高齢化社会が進む中で「老前整理」という言葉が注目されています。老前整理とは、老後を迎える前に自分の持ち物や生活環境を整理し、将来に備えることです。これを通じて、生活がスムーズに進み、精神的な負担も軽減できます。この記事では、老前整理の概要やメリット、進め方について詳しく説明します。
老前整理とは?その意味と取り組む意義
「老前整理(ろうぜんせいり)」とは、自分自身がまだ元気で判断力のあるうちに、身の回りの物や住環境、財産や情報を整理しておくことを指します。これは老後の安心した生活を実現するための準備であり、「これからの人生をどう生きていくか」を見つめ直す、いわば“人生の棚卸し”とも言える重要なプロセスです。
老前整理とよく混同される言葉に「生前整理」がありますが、両者には明確な違いがあります。生前整理は自分の死後に備えて遺品や財産の整理をすることが主な目的であるのに対し、老前整理は「これからの老後を快適に生きるための準備」として、自分自身の未来に向けた前向きな整理です。つまり、老前整理は“これからを生きるための整理”、生前整理は“旅立った後のための整理”とも言えます。
老後は誰にとっても、心身の変化が避けられない時期です。体力の低下、判断力の衰え、病気や介護のリスクなど、不安要素が多くなる中で、元気なうちにできることを先に済ませておくことは、自分自身の安心と、周囲の人への思いやりにもつながります。老前整理は、自立した生活をできるだけ長く続けたいという願いを叶える手段でもあるのです。
老前整理を行うことのメリット
生活動線がシンプルになり、暮らしがスムーズになる
老前整理の第一歩は、身の回りにある「本当に必要なもの」と「不要なもの」とを見極めることです。長年にわたってため込んだ物の中には、すでに使わなくなったものや、存在を忘れていたものが多くあります。これらを手放すことで、自宅の中にスペースが生まれ、生活導線が驚くほどスムーズになります。
たとえば、床に置かれた段ボールや使われなくなった家具がなくなることで、転倒のリスクが減り、安全性が向上します。また、キッチンやクローゼットの中を整理することで、料理や着替えの時間も効率化され、日常のちょっとしたストレスも減っていきます。
生活空間が整うと、掃除もしやすくなり、衛生的な環境を保つことができます。これは、感染症やアレルギーのリスクを下げるという意味でも、健康維持に直結する大きなメリットです。
精神的な安定・安心感が得られる
物が多く、片付いていない空間は、それだけで人の心に重荷を与えるものです。視界に入る情報が多ければ多いほど、脳が処理しなければならない負荷も大きくなり、気づかないうちに疲労やイライラの原因になっています。
老前整理によって、不要な物を手放し、自分にとって本当に大切な物だけに囲まれて暮らすことができれば、精神的にも大きな安定が得られます。部屋がすっきりすると、気持ちが明るくなり、「もっと快適な生活を目指したい」という前向きな気持ちが芽生える方も多いのです。
また、「いつかやらなければ…」と先送りにしていた整理をやり遂げたという達成感は、自己肯定感や自信にもつながります。老前整理は、心の整理と再スタートのきっかけを与えてくれる行為でもあるのです。
家族への負担を減らすことができる
老前整理の重要な目的のひとつに、「家族への負担を軽くする」ということがあります。高齢者が亡くなったあと、その遺品を整理するのはたいていの場合、子どもや近しい親族です。残された物が多いほど、整理にかかる時間や労力、さらには感情的な負担も増大します。
何を捨ててよいのか、何が大切なものなのか分からず、ひとつひとつ確認しながら片付ける作業は非常に大変です。中には「捨ててよかったのか分からない」と罪悪感を抱える家族もいます。
しかし、自分自身で老前整理を進めておけば、家族が迷うことなく行動できるようになります。「これは大切だから残しておく」「これは処分してよい」という判断を自ら下しておくことは、家族にとっても大きな安心材料となるのです。
老後のライフプランが立てやすくなる
老前整理を通じて、今後の人生設計をより明確にすることができます。たとえば、家にある物を整理していくうちに、「もうこんなに広い家は必要ない」と感じるかもしれません。その場合、よりコンパクトで管理しやすい住まいに移るという選択肢が見えてきます。
また、書類や資産を整理することで、年金や貯金、保険、介護体制に関する不安も見える化され、早めに対策を取ることが可能になります。資産運用や相続について考えるきっかけにもなり、家族とも将来についての話し合いをしやすくなるでしょう。
老前整理は、今の自分の生活を見直し、未来に向けた選択肢を広げる作業でもあります。何を大切にし、どう生きたいか――その答えを自分の中で見つけるためのプロセスとして、非常に価値ある取り組みです。
生前整理との違いについてより詳しく解説
「老前整理(ろうぜんせいり)」と「生前整理(せいぜんせいり)」は、どちらも“自分自身の財産や持ち物を整理する”という共通点がありますが、その目的や取り組むタイミング、視点には明確な違いがあります。両者の違いをしっかりと理解することで、自分の人生設計や整理整頓の方向性がより明確になり、後悔のない選択ができるようになります。
生前整理とは?──死後を見据えた“人生の締めくくり”
「生前整理」とは、自分の死後に家族や周囲の人々に迷惑をかけないよう、生きているうちに財産、遺品、重要書類、思い出の品などを整理・処分しておく行為を指します。つまり、人生の終末期を見据え、「死」に備える準備といってもよいでしょう。近年では、「終活(しゅうかつ)」という言葉が一般的になりつつありますが、その一環として生前整理に取り組む人も増えています。
生前整理では、遺言書の作成、エンディングノートの記入、相続に関する取り決め、不動産や預貯金の整理、葬儀や墓の準備など、「死後のことを見越しての準備」が中心です。これは、自分が亡くなったあとの家族の負担をできるだけ軽くしたい、あるいは自分の意思をきちんと残したいという思いに基づいたもので、極めて実務的な側面を持つのが特徴です。
老前整理とは?──これからの生活を快適にする“未来への整備”
一方の「老前整理」は、自分の死後ではなく、「これからの老後を快適に生きるための準備」としての意味合いが強くなります。対象となるのは主に、日常生活に関わる物品や住環境、生活習慣、日々の暮らしの基盤です。生前整理のように「死」に焦点を当てるのではなく、「老い」を見据えた現実的なライフスタイルの最適化が目的となります。
老前整理を通じて、物を減らし、暮らしの動線をシンプルにすることで、加齢による身体的・精神的な変化に対応しやすくなります。たとえば、階段の昇り降りがつらくなった時に備えて住まいを見直したり、不要な家具や衣類を処分して転倒リスクを減らすといった具体的な改善が含まれます。また、思い出の品やアルバム、写真などを見直すことで、自分の歩んできた人生を再確認し、新たな生きがいを見出すきっかけにもなり得ます。
老前整理をするタイミング
老前整理を始める最適なタイミングは人それぞれですが、一般的には「まだ自分で動けるうち」「判断力がしっかりしているうち」に始めるのが理想とされています。つまり、“何かあってから”ではなく、“何かが起こる前に”行動することが老前整理の本質です。以下では、老前整理を意識すべき代表的なタイミングをいくつか挙げ、なぜその時期が適しているのかを詳しく解説します。
体力や健康に不安を感じ始めたとき
年齢を重ねるにつれて、体の変化や健康への不安を感じる場面が増えてきます。たとえば、階段の昇り降りがつらく感じたり、重い荷物を運ぶのが億劫になったりと、日常のちょっとした行動にも影響が出るようになります。このような身体的な変化に気づいたタイミングは、まさに老前整理を始める合図といえるでしょう。
体力に余裕があるうちに、自分のペースで物の整理を行えば、無理なく作業ができます。また、住まいの中を整理し、物を減らすことで、転倒や事故のリスクも減少します。早めに動き出すことで、心身の負担を最小限に抑え、安全で快適な生活環境を整えることができます。
自立した生活ができているうちに
「まだ元気だから必要ない」と思う方もいるかもしれませんが、老前整理は“元気なうち”だからこそスムーズに進めることができるのです。物の要不要を判断したり、思い出の品を手放すかどうかを決めるのには、ある程度の時間と心の余裕が必要です。加えて、体調を崩してからでは、大きな家具や大量の荷物の整理が物理的に困難になることもあります。
自立して動けるうちは、自分の意思で自由に選択しながら整理を進められます。その結果、自分らしい暮らしを再構築することにもつながり、老後をより豊かに、前向きに過ごすきっかけになるでしょう。
生活スタイルが変わるタイミング
退職を迎えたときや子どもが独立して家を出たときなど、人生の節目にあたる時期は、老前整理に取り組む絶好のチャンスです。これまでのライフスタイルが変わることで、使わなくなる物、不要になるスペース、見直すべき習慣などが自然と浮かび上がってくるからです。
たとえば、子どもが巣立ったあとの広すぎる家に住み続けることが精神的にも金銭的にも負担になるようであれば、住み替えやリフォームを視野に入れて整理を始めるのも良いでしょう。物理的な整理だけでなく、生活設計そのものを見直す機会として、ライフステージの変化は非常に有効です。
家族に迷惑をかけたくないと思ったとき
「自分が高齢になって、もし何かあったときに、子どもや家族に迷惑をかけたくない」――こうした思いから老前整理を決意する方も多くいます。実際、親の持ち物を整理する立場になった経験がある人ほど、「自分のときは子どもに負担をかけたくない」と考えるようになる傾向があります。
老前整理を進めておけば、いざというときに家族が困らないよう、物の所在や重要書類の保管場所も明確になります。整理された住環境は、将来的に介護や手助けが必要になったときにも役立ちますし、家族とのコミュニケーションの機会にもなります。早めに行動しておくことで、家族との信頼関係をより深めることにもつながるのです。
気持ちに余裕があるとき
老前整理は、単なる“片付け”ではなく、自分の人生を見つめ直す作業でもあります。そのため、心に余裕があるときに取り組むことで、より納得のいく判断ができるようになります。たとえば、思い出の品に触れながら、過去の出来事や人間関係を振り返り、「これからどんな暮らしをしていきたいか」を自然と考えるようになります。
逆に、心に余裕がないと、不要なものをなかなか手放せなかったり、作業が億劫になって途中で挫折してしまうこともあります。だからこそ、「やってみようかな」と思ったその瞬間が、もっとも自然でスムーズに老前整理を始められるベストタイミングといえるのです。
老前整理の具体的な進め方
老前整理は、単なる片付けや掃除とは異なり、将来の生活をより快適にするための準備であり、同時に家族への思いやりを形にする行動でもあります。無理なく進めるには、計画性を持ち、段階を踏んで進めることが重要です。ここでは、老前整理を進めるうえでの基本的なステップを詳しく解説します。
部屋ごとに整理を始める
老前整理に取りかかるとき、最初に陥りやすいのが「どこから手をつけていいかわからない」という状態です。一度に家中すべての物を見直そうとすると、労力も精神的な負担も大きくなり、途中で挫折してしまう恐れがあります。そのため、まずは「場所を区切って取りかかる」ことが大切です。
例えば、リビング、キッチン、寝室、洗面所、押し入れ、納戸といったように、家の中をエリア別に分けて、ひとつずつ順番に整理していきましょう。「今日は寝室のタンスだけ」「次の週末はキッチンの収納棚」など、具体的な計画を立てて小分けに作業を進めることで、負担を感じにくくなります。
また、使用頻度の低い場所や、物が多く溜まりやすい収納スペースから着手するのも効果的です。見えにくい場所から始めることで、達成感を得やすく、モチベーションの維持にもつながります。
不要なものを仕分ける
老前整理の中心となるのが、不要なものの見極めです。特に長年住んでいる住まいには、意識していないだけで使っていないものや、存在を忘れていた物が数多く眠っています。「いつか使うかもしれない」という理由で取っておいたものも、この機会に本当に必要かどうかを見直してみましょう。
仕分けのコツは、「使っている」「使っていない」「迷っている」の3つに分類することです。「使っているもの」は元の場所や使いやすい場所へ戻し、「使っていないもの」は処分または譲渡の対象にします。「迷っているもの」は一時保留として箱などにまとめ、数か月後に見直すようにすると、気持ちの整理もしやすくなります。
また、同じ種類の物をまとめて確認することで、無駄を可視化できます。たとえばタオルや食器、文房具など、「こんなにたくさんあったのか」と驚くことも少なくありません。これにより、持ち物を必要最小限に絞る意識も自然と高まります。
思い出の品を整理する
老前整理の中で最も時間がかかり、心の負担にもなりやすいのが「思い出の品」の整理です。写真、手紙、子どもが描いた絵、旅行の記念品など、感情が強く結びついたものを手放すのは難しいものです。しかし、すべてを残しておくわけにもいかないのが現実です。
このとき意識したいのは、「思い出と現物は別」と考えること。写真はアルバム1冊にまとめたり、スキャンしてデジタル保存する方法もあります。記念品は「一つだけ選んで残す」など、ルールを決めて整理すると良いでしょう。
また、家族と一緒に思い出を振り返りながら整理することで、話のきっかけにもなり、物への執着心を手放しやすくなります。どうしても迷うものは無理に処分せず、保管期間を設けて、気持ちに整理がついたタイミングで見直しましょう。
遺品整理を見越して記録を残す
老前整理の大きな目的の一つは、将来的に遺品整理を行う家族の負担を減らすことです。そのためには、物の整理だけでなく、「重要な情報を明文化する」ことも重要です。
たとえば以下のような情報をリスト化しておくと、万一のときに家族がスムーズに対応できます。
- 通帳、保険証券、不動産登記簿などの保管場所
- パソコンやスマホのパスワード
- インターネット契約やサブスクリプションの管理情報
- どこに何があるかの簡単な間取り図
- 遺言書の有無、またはエンディングノート
特に最近では、デジタル遺品(SNS、ネットバンキング、メールアカウントなど)の存在も忘れてはなりません。紙のノートやUSBメモリ、パスワード管理アプリなどを活用し、家族に「どこを見れば情報があるか」を伝えておくだけでも、大きな助けになります。
定期的な見直しをする
老前整理は一度きりで終わるものではなく、年齢や生活環境の変化に応じて定期的な見直しが必要です。たとえば体力が落ちた、生活の動線が変わった、気持ちが整理されたなどの変化があれば、その都度アップデートしていきましょう。
一度きちんと整理をしておけば、その後の見直しは格段に楽になります。年に一度のペースで、誕生日や年末など「自分の節目」となるタイミングを決めて定期的に点検する習慣を持つと、無理なく維持が可能です。
老前整理を進める際の注意点
老前整理は人生の節目ともいえる大切な作業です。将来の自分と家族のために環境を整え、心の整理を行う行動である一方、思い出と向き合いながら物を手放していくことは、決して簡単なことではありません。無理なく、そして後悔のない整理を行うためには、いくつかの大切なポイントに注意する必要があります。
無理をしない
老前整理を行ううえで最も重要なことのひとつは、「体に無理をさせないこと」です。年齢を重ねると、若い頃には平気だった作業も思いのほか負担になることがあります。重たい荷物の持ち運びや、高所にある収納の整理などは、無理をすれば転倒やケガの原因にもなりかねません。
そのため、整理は一気に終わらせようとせず、時間をかけて「少しずつ、こまめに」行うことが大切です。例えば「今日は引き出しひとつだけ」「明日は押し入れの手前だけ」というように、作業を細かく区切ることで、身体的にも精神的にも無理のないペースで進められます。
また、暑さの厳しい時期や体調が優れない時期には無理をせず、休息を第一に考えましょう。自分のペースを大切にし、楽しみながら取り組む意識を持つことが、長続きのコツです。
感情的にならない
老前整理は、単なる物の片付けにとどまらず、これまでの人生と向き合う作業でもあります。思い出の品や、亡くなった家族の遺品、自分の若い頃の手紙や写真などに触れると、どうしても感情が動くものです。しかし、その感情に流されすぎると、なかなか物が捨てられず、作業が進まなくなってしまうこともあります。
こうしたときは、無理に処分を決めず、一時的に「保留ボックス」や「思い出コーナー」を設けて、一旦そこにまとめておくのがおすすめです。数週間、あるいは数か月経ってから見直すと、気持ちが整理され、判断しやすくなることがあります。
また、感情的になってしまうのは自然なことです。だからこそ、一人で抱え込まず、家族や信頼できる人と話しながら整理を進めることで、気持ちの整理も並行して行えます。感情を無理に押し殺す必要はありませんが、「物に思い出がある」という点と、「思い出は心の中にある」という点のバランスを意識することが大切です。
整理を家族と共有する
老前整理は、自分ひとりで進めるよりも、家族と一緒に行うことで得られるメリットが数多くあります。まず、家族と一緒に整理を進めることで、「何を残すのか」「何を手放すのか」の価値観を共有できます。これにより、将来的に遺品整理や相続の際に発生しがちなトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
たとえば、自分では価値がないと思っていたものが、家族にとっては思い出深い品だったり、その逆もあります。事前に「これは残しておいてほしい」「これは処分しても構わない」という意思疎通ができていれば、家族が安心して老後をサポートしやすくなります。
また、重要な書類や貴重品、財産関係の情報などは、どこに保管しているのかを明確にして家族に伝えておくことが非常に重要です。整理を通して家族との対話の機会を増やし、「何を、どう残したいのか」という思いを共有することは、老前整理の本来の意義をより深めることにつながります。
判断に迷ったら専門家の手を借りる
老前整理をしていると、「これはどうすればいいんだろう?」と迷う場面が少なからず出てきます。財産や相続に関わる書類の整理、リサイクルや買取の可否、大型家具の処分方法など、判断に困るようなケースも多いものです。
そうした場合は、行政の高齢者支援窓口や、遺品整理士、終活アドバイザー、不用品回収業者など、専門家に相談することを検討しましょう。正しい知識を持った第三者にアドバイスをもらうことで、安心して進めることができますし、失敗やトラブルのリスクを避けることにもつながります。
また、地域によっては「老前整理講座」や「終活セミナー」などを開催している自治体もあります。そうした場に参加することで、同じ悩みを抱える人との情報交換ができ、孤独感を感じずに前向きに整理を進めるきっかけになります。
老前整理は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は老前整理の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
老前整理を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!