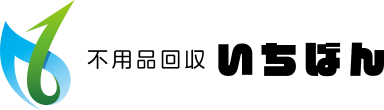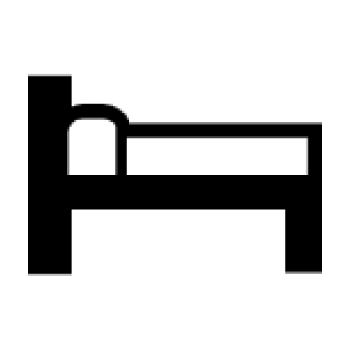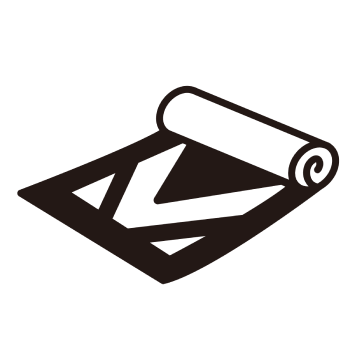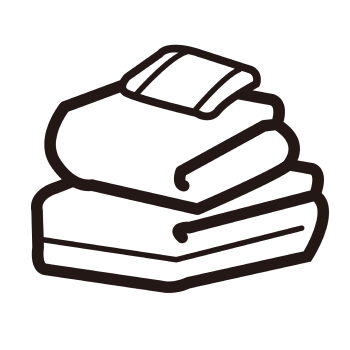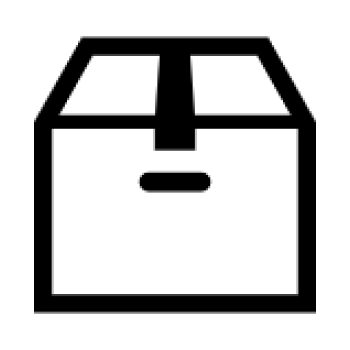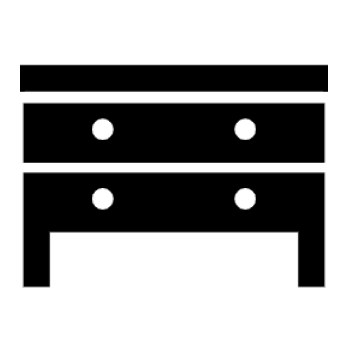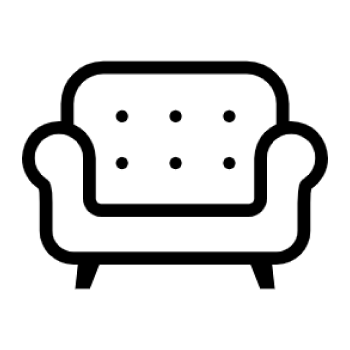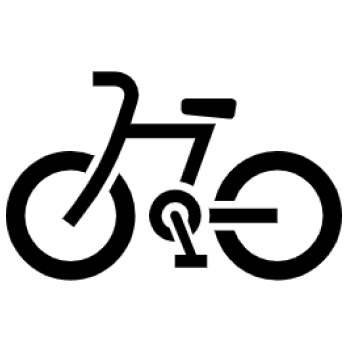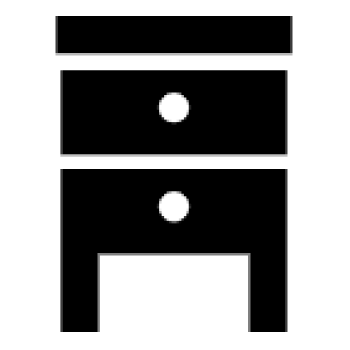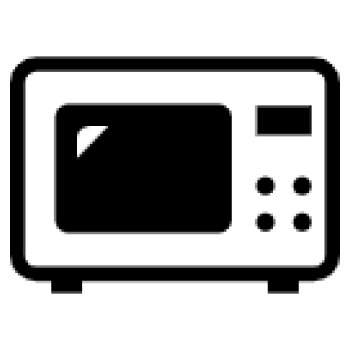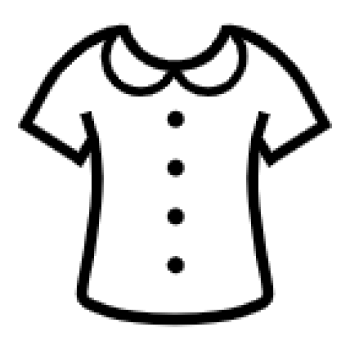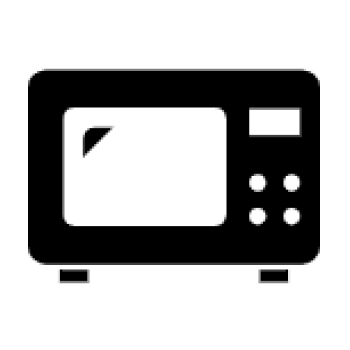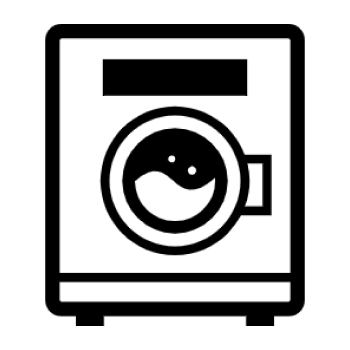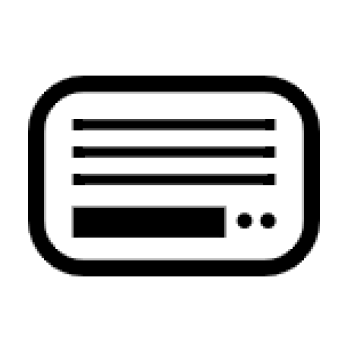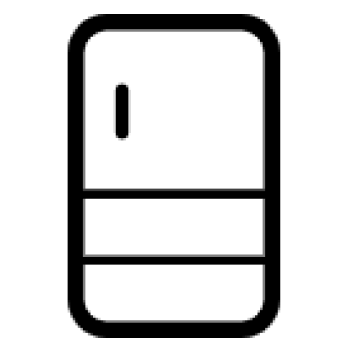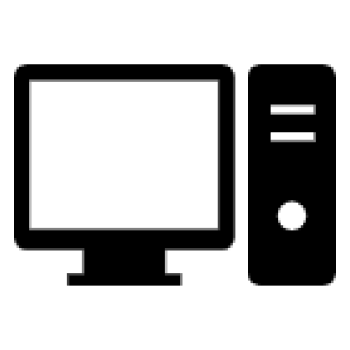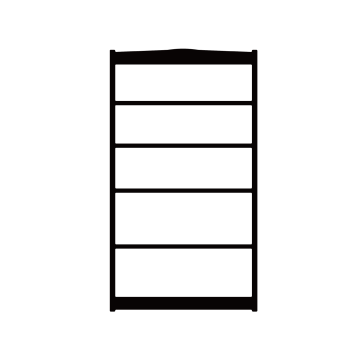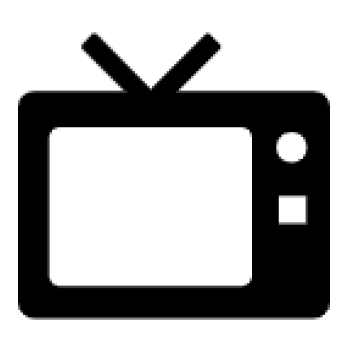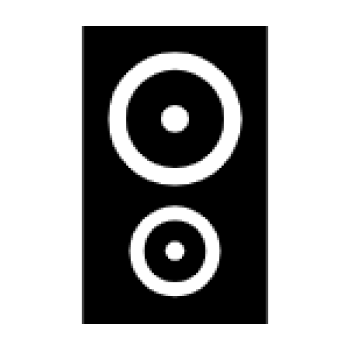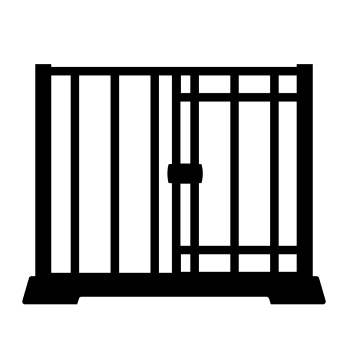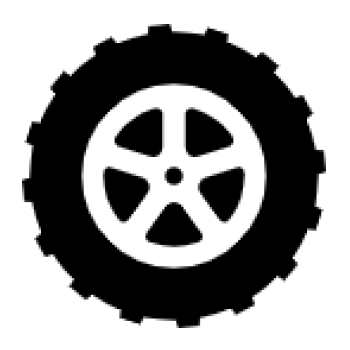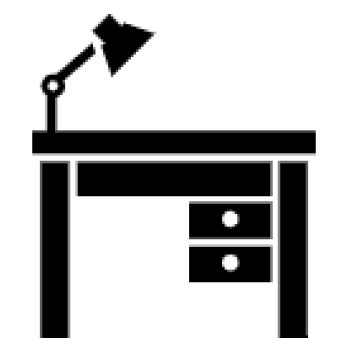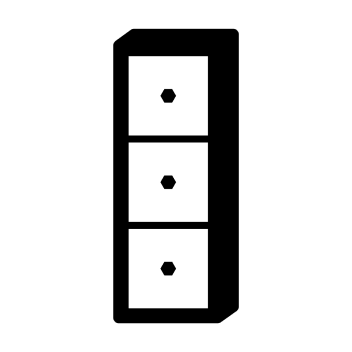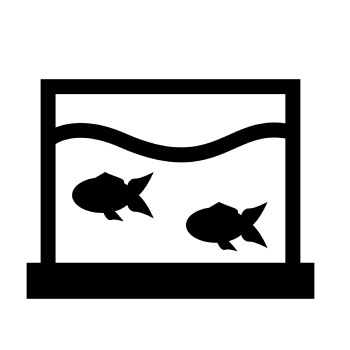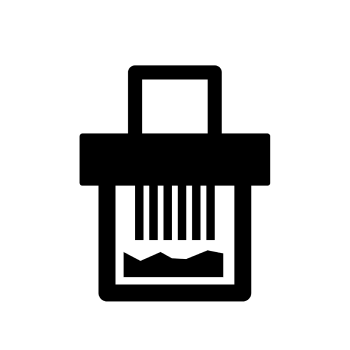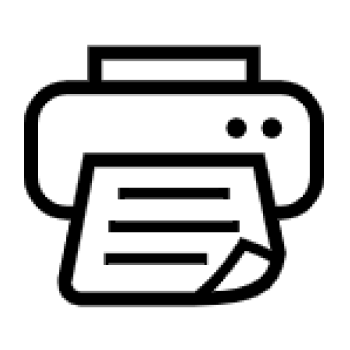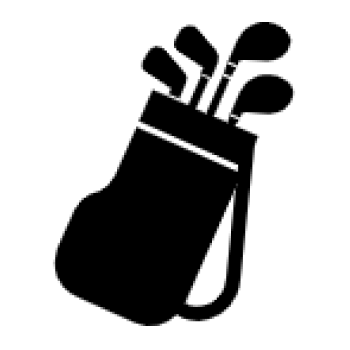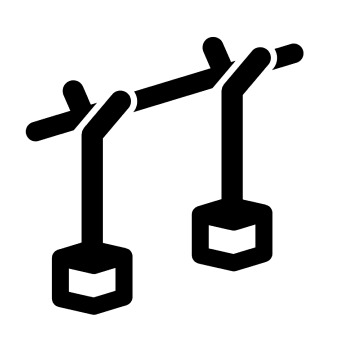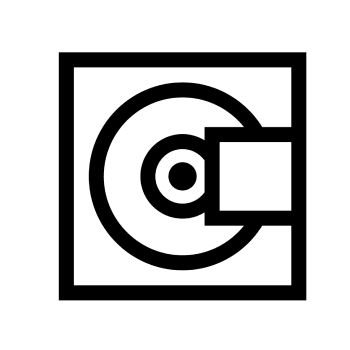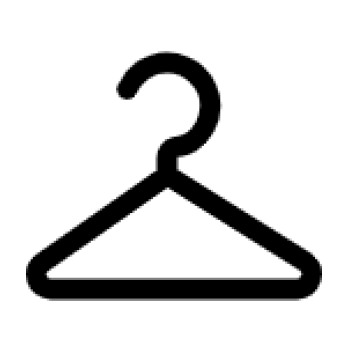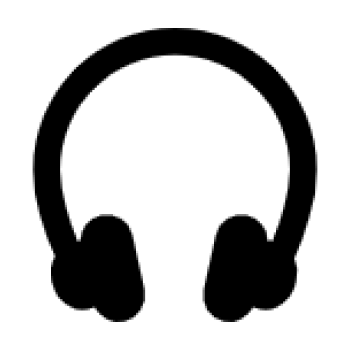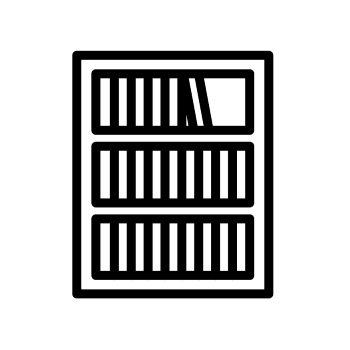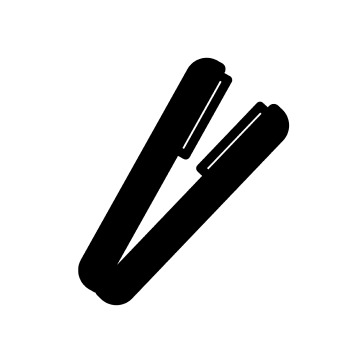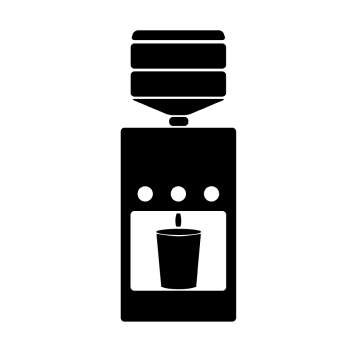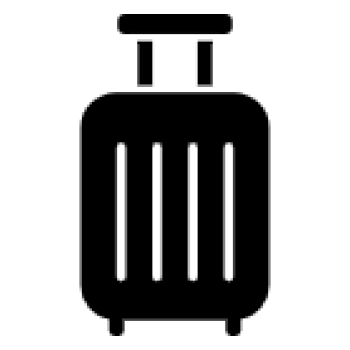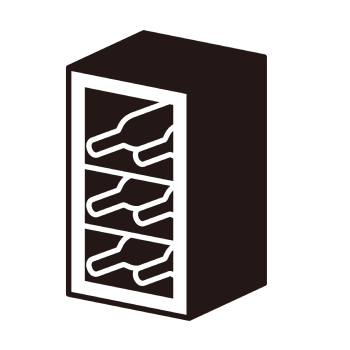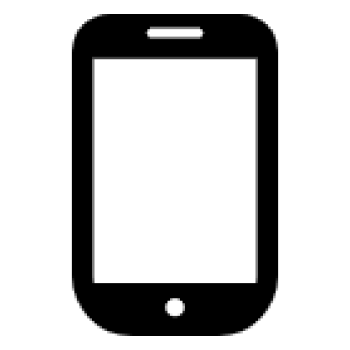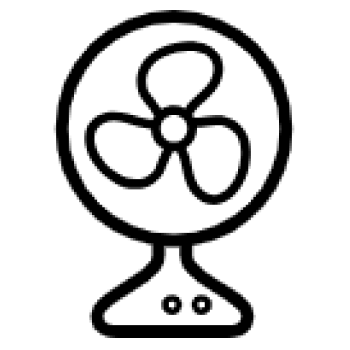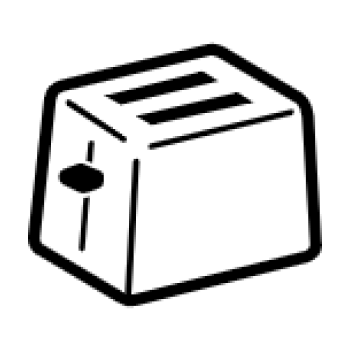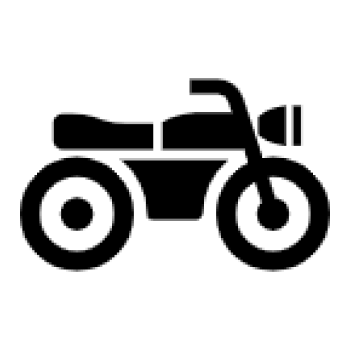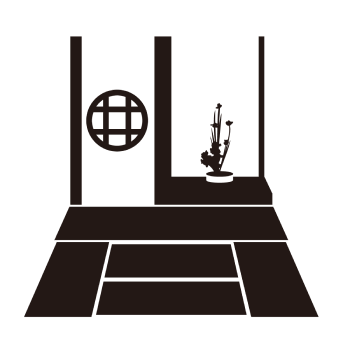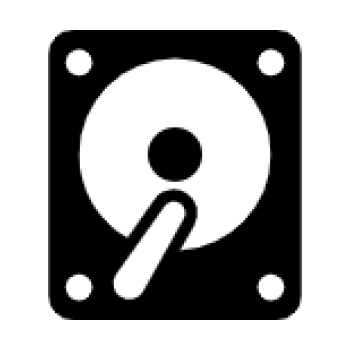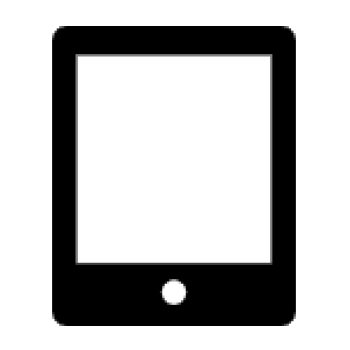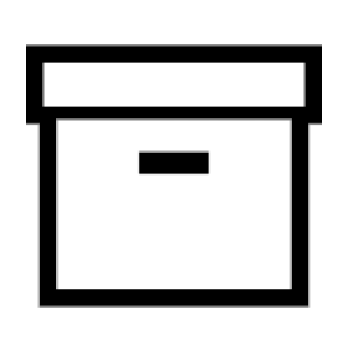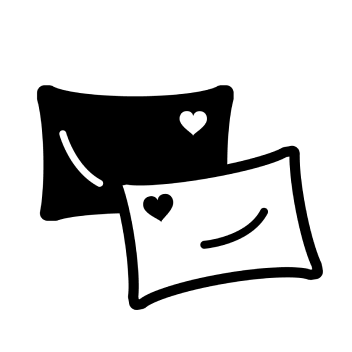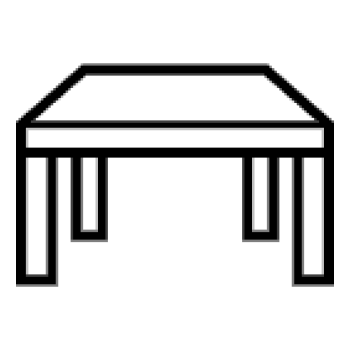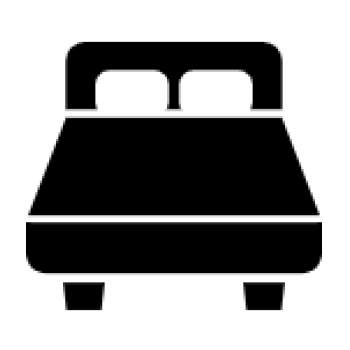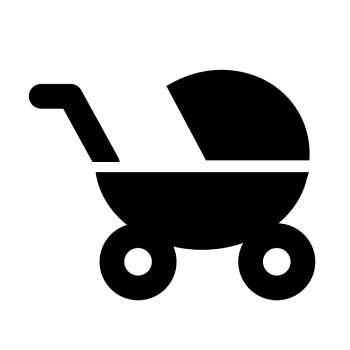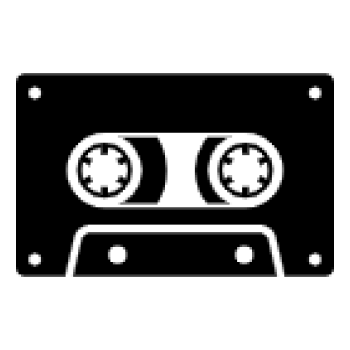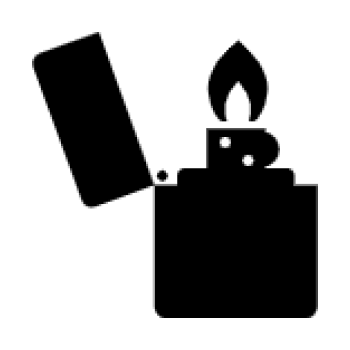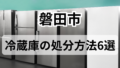部屋の片づけや引っ越し、模様替えなどのタイミングで、意外と処分に悩むのが「ハンガーラック」です。日常的に使っている家具の一つですが、いざ不要になったときにはその大きさや素材の違いから、どうやって捨てればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
ハンガーラックには、パイプ製・木製・プラスチック製といった素材の違いや、キャスター付き、棚付きなどの機能の違いもあります。そのため、自治体のごみ分別ルールや回収方法に従う必要がありますが、適切な手順を踏まないと回収してもらえなかったり、追加料金が発生することもあります。
また、状態が良いものであれば、リサイクルショップやフリマアプリを通じて「売る」ことも可能ですし、地域によっては「譲る・寄付する」ことで再活用されるケースもあります。ただし、こうした選択肢にはそれぞれメリットと注意点があるため、正しい情報をもとに自分に合った方法を選ぶことが大切です。
この記事では、ハンガーラックをスムーズに、そしてできるだけ負担をかけずに処分するためのポイントを、種類別・方法別にわかりやすく解説します。適切な処分方法を知って、手間なくスッキリと片づけましょう。
ハンガーラックを処分するタイミング
使用感の悪化や破損
ハンガーラックを処分するタイミングは人それぞれですが、共通して見られるきっかけには、「使用感の悪化」「インテリアとのミスマッチ」「破損・老朽化」「生活環境の変化」などが挙げられます。長年使用していると、少しずつガタつきや不具合が出てきて、本来の機能を十分に果たせなくなる場合が多く、買い替えや処分を検討する重要なサインとなります。
キャスターやフレームの不具合
たとえば、キャスター付きのハンガーラックであれば、車輪の動きが悪くなってスムーズに移動できなくなったり、脚部が不安定になってガタつくといった症状が目立ち始めると、使い勝手に大きな影響を及ぼします。また、フレーム自体が歪んだり、接続部分のボルトやネジが緩んでぐらつくようになった場合、重い冬物のコートやジャケットを掛けたときに傾いたり倒れてしまうリスクも出てくるため、安全面からも処分の検討が必要です。
インテリアや収納計画との不一致
さらに、引っ越しや模様替えなどで部屋の広さや収納の配置が変わった場合にも、これまで使っていたハンガーラックが合わなくなることがあります。部屋の印象を統一したいのに、色味やデザインがインテリアと合わなくなったことで、見た目が気になるようになったという理由で手放す人も少なくありません。近年ではおしゃれなオープンラックやシステム収納が人気を集めており、古いハンガーラックが時代遅れに感じられてしまうこともあるでしょう。
放置状態が続いているなら要見直し
また、収納スペースの無駄遣いになっている場合も見直しのタイミングです。しばらく使っていないハンガーラックが部屋の隅に置かれたままホコリをかぶっている状態なら、それはすでに「不要なモノ」に分類される可能性が高いです。特に衣替えの時期や大掃除のタイミングなどに、使っていないアイテムを再評価することは、生活空間をスッキリさせる良い機会でもあります。
判断に迷ったときは「お試し保留期間」を活用
処分するかどうか判断に迷うときは、一定期間だけ使わずに様子を見る方法も有効です。たとえば「1ヶ月ルール」や「90日ルール」といった、自分なりの基準を設けて、その間に使用しなかった場合は処分対象とする、といったやり方です。こうしたルールを活用すれば、感情に左右されずに合理的な判断ができるようになります。
快適な空間づくりのために
収納家具の役割は、「空間を有効活用し、生活を快適にすること」です。その役割を果たしていないと感じたら、それはハンガーラックを手放すべきタイミング。新しい収納方法や生活スタイルに合わせて、不要になったハンガーラックを見直すことで、部屋全体がよりスッキリし、快適な空間へと生まれ変わるかもしれません。
処分する際の注意点
ハンガーラックを処分する際には、ただ単に捨てるのではなく、安全性や自治体のルール、さらにはリユース・リサイクルの観点からも注意すべき点がいくつかあります。以下のポイントを押さえて、トラブルなくスムーズに処分しましょう。
自治体のごみ分類ルールを確認する
まず第一に確認すべきなのが、「処分方法は自治体によって異なる」という点です。ハンガーラックは素材やサイズによって、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」と分類が分かれます。たとえば、木製で小型のものであれば可燃ごみ扱いで処分できる自治体もありますが、スチール製の大型タイプはほとんどの場合、粗大ごみに分類され、事前申請が必要です。
粗大ごみとして出す場合は、各自治体のルールに従って収集の申し込みを行い、指定された日に収集場所へ出す必要があります。また、処分費用として「粗大ごみ処理券」の購入が必要になるケースも多く、相場は200〜800円ほどです。自治体のホームページやごみカレンダーを参照し、必ず最新の情報を確認しましょう。
分解の可否と安全対策
次に注意したいのが、ハンガーラックの「解体が必要かどうか」です。粗大ごみとしてそのまま出せるケースもあれば、「45リットルのごみ袋に入るサイズに分解すれば不燃ごみとして出せる」といったルールのある自治体もあります。解体によって処分費用を抑えられることもあるため、できるだけ確認しておくとよいでしょう。
ただし、ハンガーラックには金属部品や鋭利なパーツが使われていることも多く、無理に工具を使って解体しようとすると、手を切るなどのケガをする恐れがあります。作業する際は必ず軍手や保護手袋を着用し、安全に注意しながら行ってください。パイプの断面やバネなどにも注意が必要です。解体後のパーツは、それぞれ「可燃」「不燃」など分別して処分することになります。
リユースする場合は状態確認と手入れが必須
まだ使用可能で、リユースや買取を検討している場合は「状態チェック」が重要です。リサイクルショップやフリマアプリで売却を考える際、見た目の清潔感だけでなく、耐久性や構造の安定性も問われます。以下の点に注意してチェックを行いましょう:
- サビや腐食の有無(特に金属製の場合)
- フレームの歪みやガタつき
- ネジやキャスターの欠損
- 臭い(保管場所によってはカビ臭などがつくことも)
小さな汚れやホコリは、雑巾で拭き取るだけでも印象が大きく変わります。取扱説明書や購入時の箱などの付属品が残っている場合は、セットにしておくとより高値で売れる可能性が高まります。
違法投棄は絶対に避ける
稀に、処分が面倒だからといってハンガーラックを公園や道路脇などに放置してしまうケースもありますが、これは明確な「不法投棄」となり、発覚すれば罰金や処罰の対象になります。処分費用を惜しむより、正しく処分して安心を得る方がずっと合理的です。
家族や近所との相談も忘れずに
大型のハンガーラックを処分する際、ひとりでの運搬が困難なこともあります。粗大ごみの収集場所まで持って行くのが難しい場合は、家族に手伝ってもらうか、状況に応じて不用品回収業者に依頼することも検討しましょう。また、同居家族が「まだ使うかもしれない」と思っている場合もあるので、勝手に捨てず、一度確認しておくとトラブルを防げます。
ハンガーラックの種類や素材別の処分方法
ハンガーラックはその素材やデザインにより、処分方法が異なります。ここでは、スチール製、木製、プラスチック製、キャスター付き・棚付きのハンガーラックについて、それぞれの特徴と適切な処分方法を詳しく解説します。
スチール製(パイプタイプ)のハンガーラック
スチール製のハンガーラックは、耐久性が高く、衣類をたくさんかけてもたわみにくいのが特徴です。軽量でありながら丈夫で、長期間使用することができます。見た目がシンプルで、インテリアにも自然に馴染むため、非常に人気があります。スチールは錆びにくいものや防錆加工が施されているタイプも多く、メンテナンスが簡単です。
スチール製のハンガーラックの処分方法は、自治体のルールにより異なりますが、一般的には「不燃ごみ」や「資源ごみ」に分類されることが多いです。サイズが大きい場合や解体が難しい場合は、粗大ごみとして処分する必要があります。しかし、スチール製のラックが非常に大きい場合や解体可能な場合、部品ごとに分けて出すことができる地域もあります。もし解体できる場合、金属部分は不燃ごみとして処分し、プラスチック部品があればそれは別途プラスチックごみとして処理します。また、スチールはリサイクル可能な素材であるため、リサイクル施設に持ち込むことで再利用されることもあります。
木製(天然木や合板)のハンガーラック
木製のハンガーラックは、天然木や合板を使用しているものが一般的です。木製のラックは、デザイン的に温かみがあり、部屋のインテリアにも自然な風合いを加えるため、非常に人気があります。長期間使用することで劣化が目立つこともありますが、適切に手入れをすれば長持ちします。木製のラックは傷がつきやすい反面、リサイクルショップなどでは一定の需要があります。
木製のハンガーラックを処分する場合、小型のものであれば「可燃ごみ」として処分できることがあります。しかし、大きなサイズのものは「粗大ごみ」として出す必要がある場合が多いです。天然木を使用したものについては、分解して「可燃ごみ」として出せることもありますが、大きな木材が使われている場合や解体が難しい場合には粗大ごみとして扱われることが一般的です。また、木製のラックは状態が良ければリサイクルショップや中古買取店に引き取ってもらえることもありますので、処分前にその可能性を確認するのも一つの方法です。
プラスチック製のハンガーラック
プラスチック製のハンガーラックは、軽量で持ち運びがしやすく、価格が手頃なため広く使用されています。ただし、プラスチックは耐荷重が低いため、重い衣類をかけると変形することがあります。また、長期間使用していると劣化して割れやすくなることがあります。プラスチック製のラックは多くの場合、安価で手に入るため、一度使ってしまうと買い替えが必要になりがちです。
プラスチック製のハンガーラックを処分する場合、一般的には「可燃ごみ」や「プラスチックごみ」として出せます。ただし、金属部分が使われている場合は、金属部分とプラスチック部分を分別して処分する必要があります。金属部分は不燃ごみとして、プラスチック部分はプラスチックごみとして処理します。さらに、プラスチック製品はリサイクルが可能な場合もあるため、近隣のリサイクル施設に持ち込むことも選択肢の一つです。
キャスター付き・棚付きのハンガーラック
キャスター付きや棚付きのハンガーラックは、便利な収納機能がついているため、衣類だけでなく他のアイテムも収納できる点が大きな特徴です。これらのラックは複数の素材(木材、金属、プラスチック)を組み合わせて作られていることが多く、そのため処分方法が複雑になります。例えば、棚板が木製で支柱が金属製、キャスターがプラスチック製というように、複数の素材が混在しています。
このようなラックを処分する場合、素材ごとに分解して処理することが求められます。木製の部分は「可燃ごみ」として、金属部分は「不燃ごみ」として分別し、プラスチック部分は「プラスチックごみ」として処理するのが理想です。複合素材でできているハンガーラックは、分解が難しいこともありますが、分別しやすいように解体することを心がけましょう。もし分解が困難な場合は、自治体のゴミ回収サービスに相談することをおすすめします。
ハンガーラックの処分方法5選
自治体の粗大ごみに出す
ハンガーラックを処分する最も一般的な方法の一つが、自治体の粗大ごみに出すことです。ほとんどの自治体では、大型の家具や家電などを粗大ごみとして処分するためのサービスを提供しています。ハンガーラックも通常、このカテゴリに該当します。
まず、自治体のゴミ回収に関するルールを確認し、粗大ごみの回収日を確認します。回収には事前の申し込みが必要なことが多く、その際に処分費用も発生します。料金は自治体によって異なりますが、一般的には200円から800円程度が相場です。多くの自治体では、コンビニエンスストアや指定の場所で処分券を購入することができます。購入した処分券をハンガーラックに貼り付け、指定された回収日に出すことで処分が完了します。
メリットとしては、手間が少なく、一般的に安全かつ確実に処分できる点です。しかし、デメリットとしては、回収日まで待たなければならない点や、サイズが大きい場合に手間がかかることです。また、自治体によっては回収時間が限られているため、事前にスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。
分解して一般ごみに出す
ハンガーラックの素材やサイズによっては、分解することで一般ごみに出すことができる場合もあります。特にスチール製やプラスチック製のラックは、分解して45Lのごみ袋に収められるサイズにすることで、可燃ごみや不燃ごみとして処分できることがあります。例えば、金属部分を解体して小さな部品に分けることで、不燃ごみとして捨てることが可能です。木製やプラスチック製の部分も、それぞれの素材に応じた処分方法を選ぶことができます。
分解作業の際には、怪我をしないよう十分に注意を払いましょう。特に金属のネジや鋭利な部分は危険ですので、作業用の手袋を着用することをお勧めします。また、ネジや小さな部品は必ずまとめて処分し、バラバラにしないよう心がけましょう。分解作業が面倒に感じるかもしれませんが、一般ごみとして出せる場合は、費用を抑えて処分することができます。なお、分解が難しい場合や、全体が大きすぎて一般ごみに出せない場合は、他の方法を検討した方が良いかもしれません。
リサイクルショップで売る
状態の良いハンガーラックは、リサイクルショップでの買取を検討するのも一つの方法です。特に、無印良品、IKEA、ニトリなどの有名ブランドのハンガーラックは、需要が高く、リサイクルショップでも取り扱っていることがよくあります。使用感が少ない、もしくはほぼ新品に近い状態であれば、リサイクルショップで高価買取してもらえる可能性があります。
また、リサイクルショップでは出張買取サービスを提供している店舗もあり、大型の家具やハンガーラックを運ぶ手間を省くことができます。自宅までスタッフが来て、無料で査定してくれるため、重い家具を自力で運ぶ必要がありません。買取の際は、事前にラックの状態やブランドを確認し、見積もりを依頼することをお勧めします。買取価格は状態やブランドによって異なりますが、出張買取を利用する場合は、交通費などの追加料金がかかることもあるため、事前に確認しておきましょう。
フリマアプリやジモティーに出品する
フリマアプリやジモティーを活用する方法も、近年非常に人気があります。メルカリやラクマ、ジモティーなどのプラットフォームを利用すれば、自分の希望価格でハンガーラックを売却することができます。特に状態が良いものやデザイン性の高いハンガーラックは、すぐに売れることがあります。また、大型の家具の場合、「引き取り希望」と記載して出品すれば、送料を抑えることができるため、買い手が見つかりやすくなることがあります。
フリマアプリを使う利点は、自分のペースで販売できる点と、地域の購入者をターゲットにできる点です。ジモティーなどでは、近隣の人に直接引き取ってもらうことができるため、送料がかからず非常にお得です。ただし、フリマアプリでは、手続きや発送に少し手間がかかることがありますし、大型のものは発送が難しい場合があるため、出品前に注意点をよく確認しておくことが重要です。
不用品回収業者に依頼する
ハンガーラックをすぐに処分したい、または他の家具と一緒にまとめて処分したい場合、不用品回収業者の利用が便利です。業者に依頼すると、自分で運ぶ手間がなく、搬出から処分まで全てを任せることができます。不用品回収業者の費用は、1点あたり約3,000円から5,000円程度が相場ですが、複数点を一度に処分する場合は、パック料金を選ぶことで割安にすることができます。
業者によっては、即日対応してくれるところもあり、急いで処分したい場合に非常に便利です。さらに、回収業者によってはリサイクルを積極的に行っているところもあるため、環境に配慮した処分が可能です。しかし、業者によって料金が異なるため、事前に見積もりを取ってから依頼することをお勧めします。また、悪質な業者も存在するため、口コミや評判を確認して信頼できる業者を選ぶことが重要です。
ハンガーラックの処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回はハンガーラックの処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
ハンガーラックを処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!