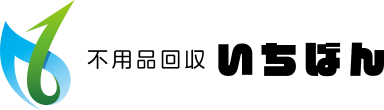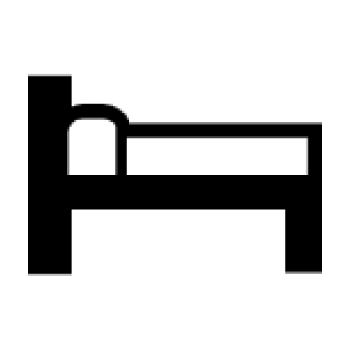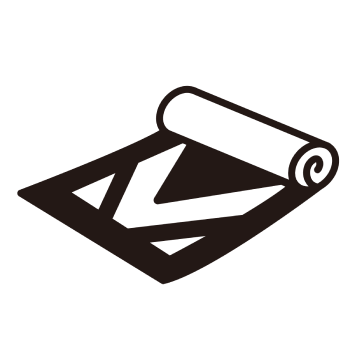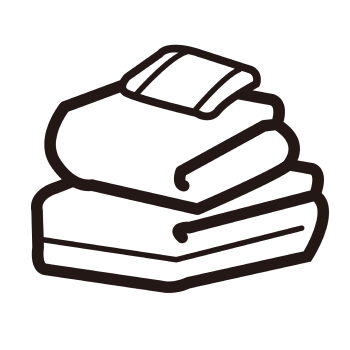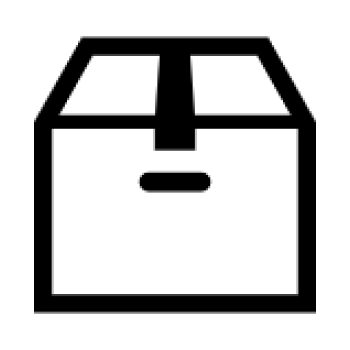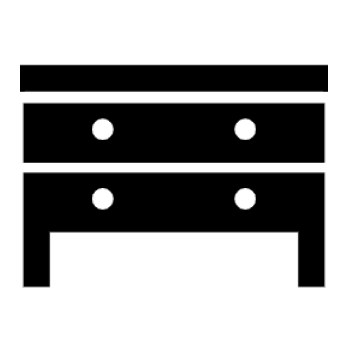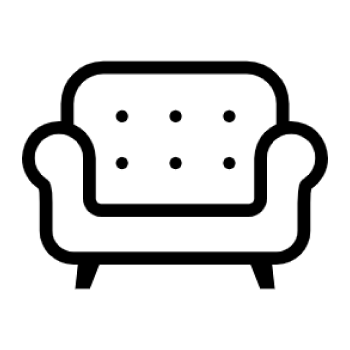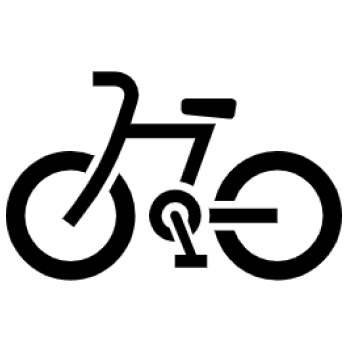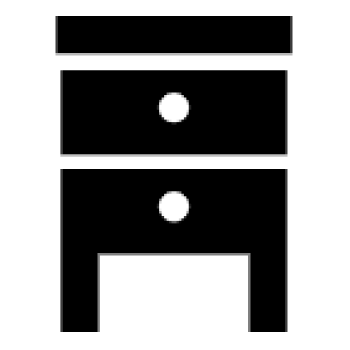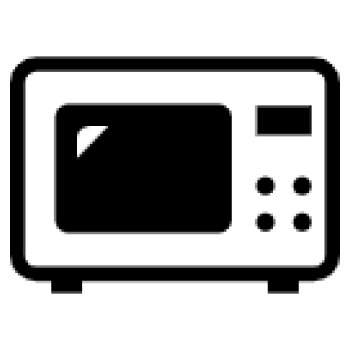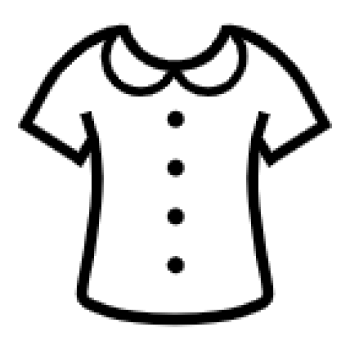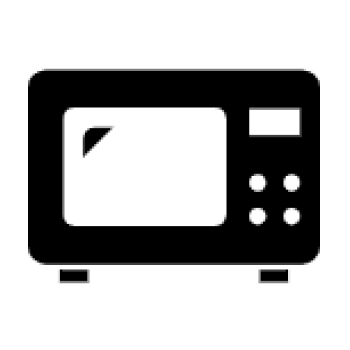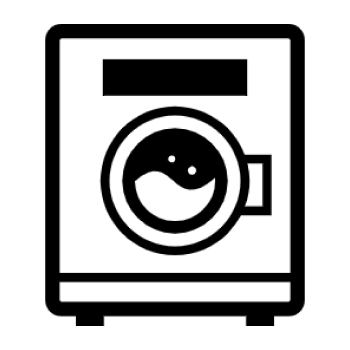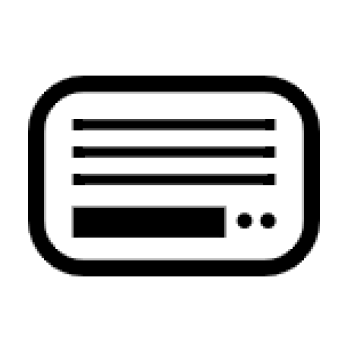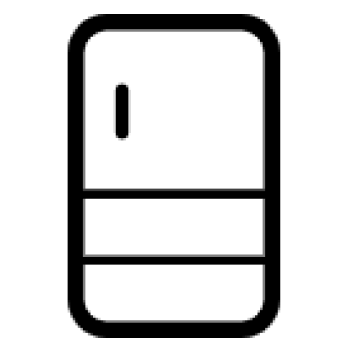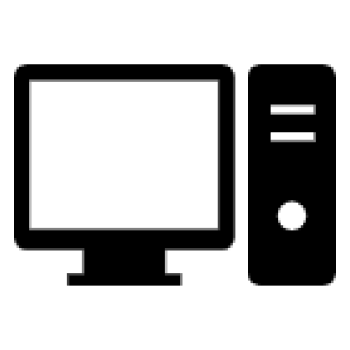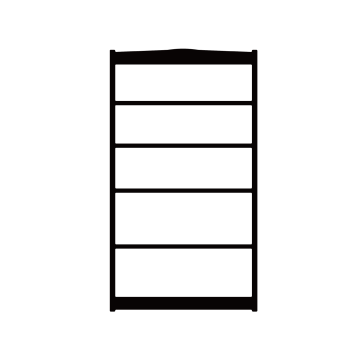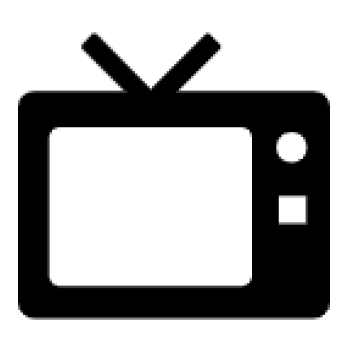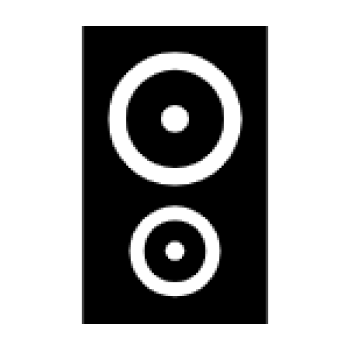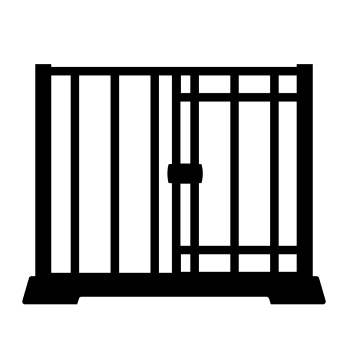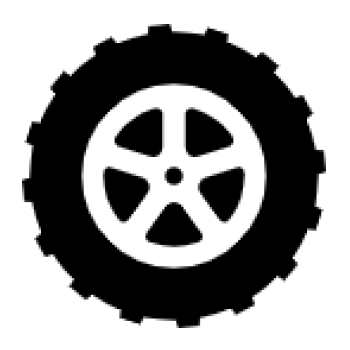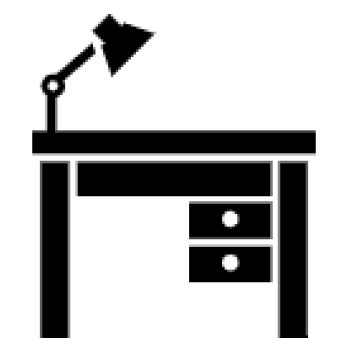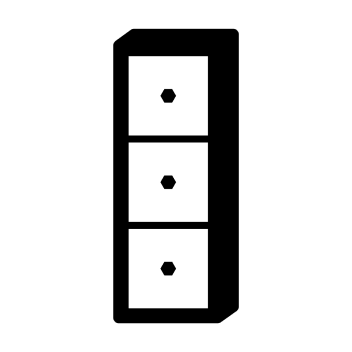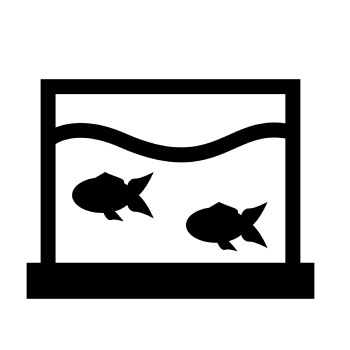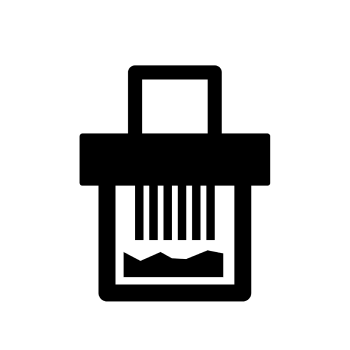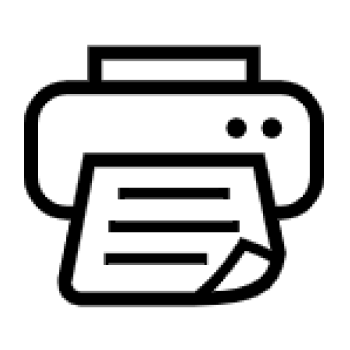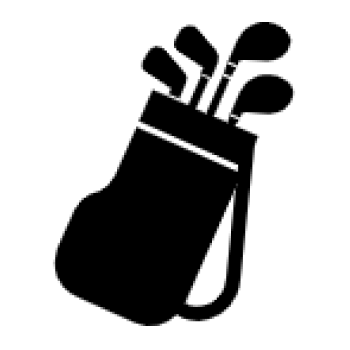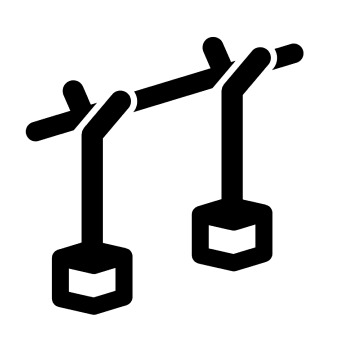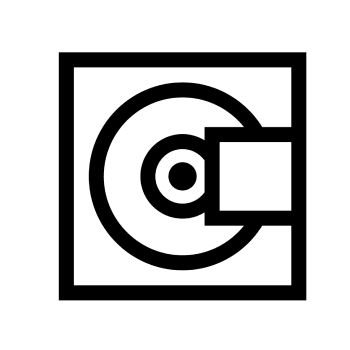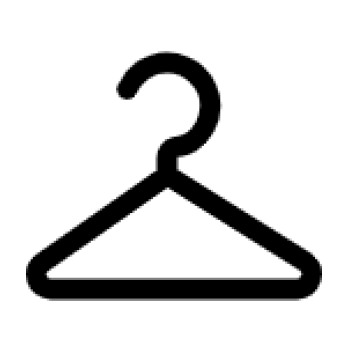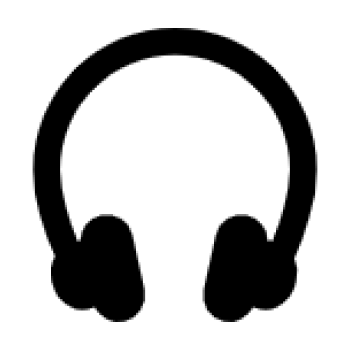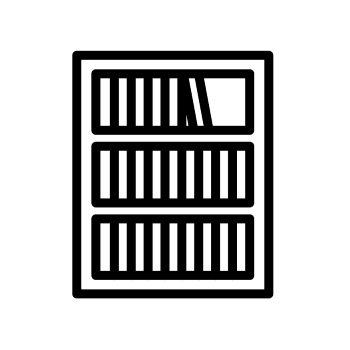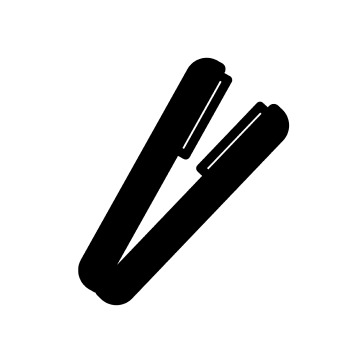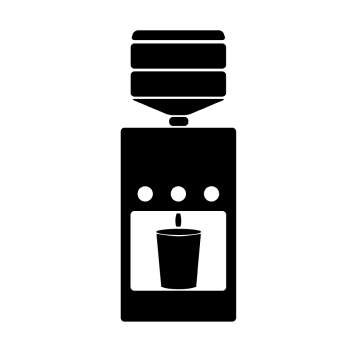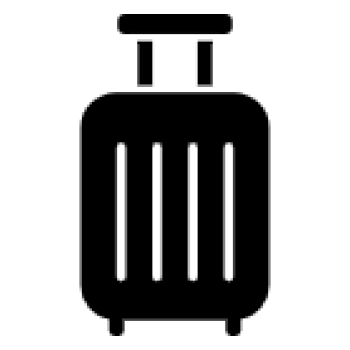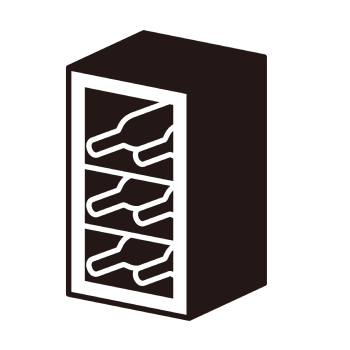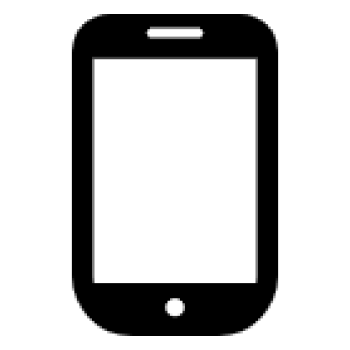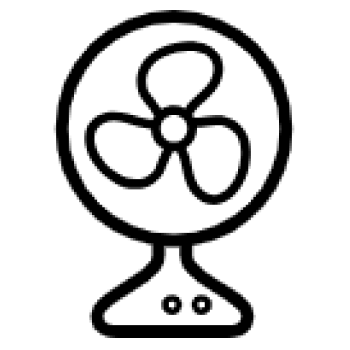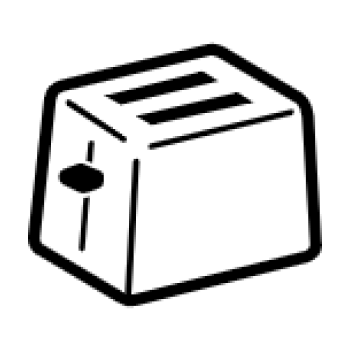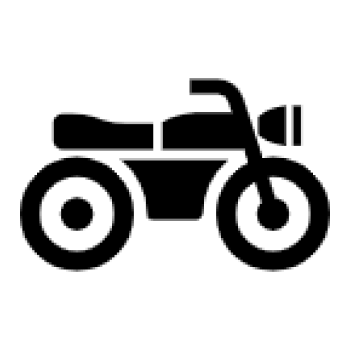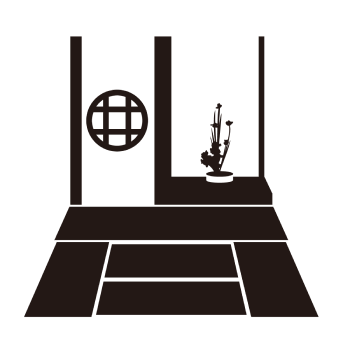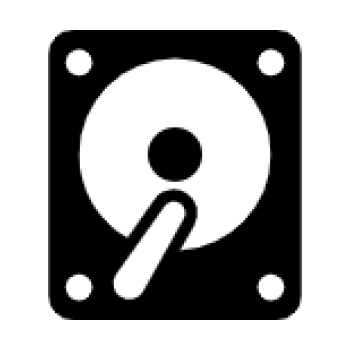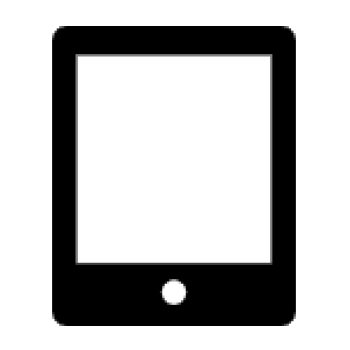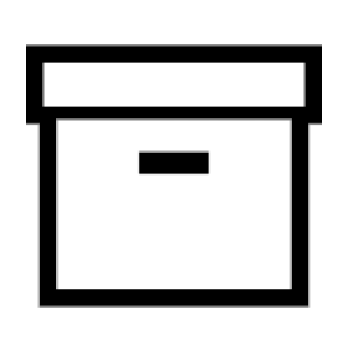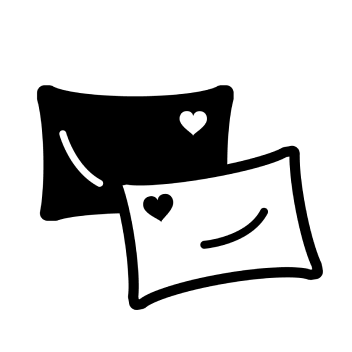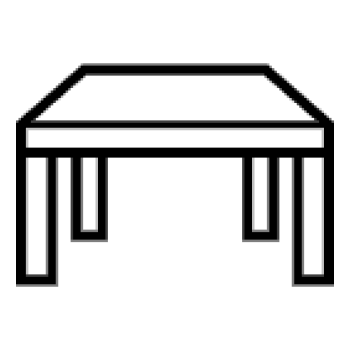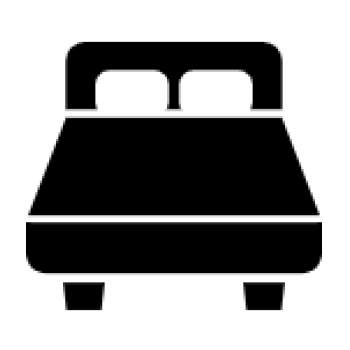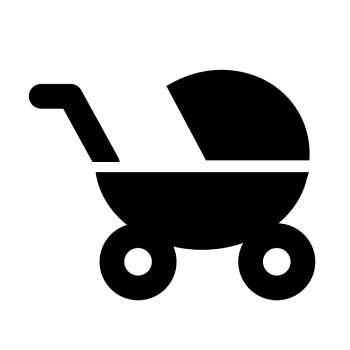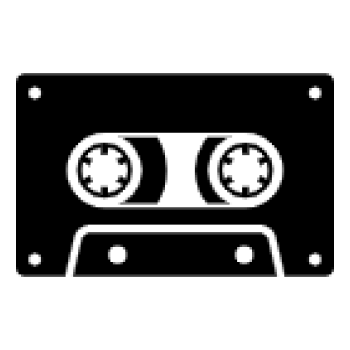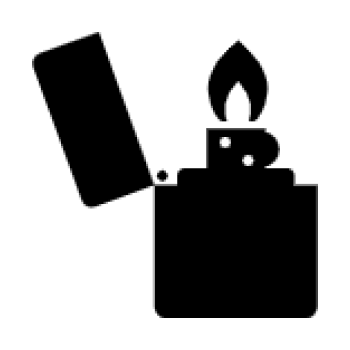子どもが遊ぶおもちゃは、成長とともに数が増えたり、遊ばなくなったりして、いつか処分を考える必要が出てきます。しかし、おもちゃの処分は単に「捨てる」だけではなく、環境への配慮や安全面の注意が求められます。例えば、まだ使えるおもちゃを捨ててしまうのはもったいないため、リサイクルや譲渡を検討することが大切です。また、電池が内蔵された電子玩具や小さな部品があるものは、正しい手順で分解しないと事故の原因になることもあります。さらに、おもちゃの素材や種類によって処分方法が異なり、それぞれの自治体のごみ分別ルールも異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
本記事では、おもちゃを処分する際に知っておきたいタイミングや種類別の処分法、安全に処分するための注意点、そして具体的な処分方法まで幅広く解説します。お子さんとの思い出が詰まった大切なおもちゃを、環境にも優しく、安心して手放すための参考にしていただければ幸いです。
おもちゃを処分する適切なタイミングは?
子どもの成長や興味の変化による処分
おもちゃの処分タイミングで最も多いのが、子どもの成長や興味の変化によるものです。乳幼児期に夢中になっていたおもちゃも、年齢が上がるにつれて遊ばなくなってしまうことがあります。たとえば、赤ちゃん向けの音が鳴るおもちゃや柔らかい布製のおもちゃは、幼児期以降は興味を持たなくなることが多いです。子どもが新しい遊びや趣味に移行していく中で、古いおもちゃは自然と使われなくなります。このようなタイミングで処分を考えることが一般的です。
壊れたおもちゃや修理が難しい場合
おもちゃが壊れたまま放置されていることもよくありますが、修理が難しかったり費用がかかりすぎる場合は処分を検討しましょう。特に電動や電子部品が入ったおもちゃは修理が高額になることも多く、無理に使い続けるよりは新しいものに替えたほうが安全です。また、壊れたおもちゃは怪我の原因になることもあるため、早めに手放すことが望ましいです。
収納スペースの確保と整理のための処分
おもちゃが増えすぎて収納場所が足りなくなるのも処分を考えるきっかけの一つです。子ども部屋やリビングにおもちゃが散乱していると、掃除が大変になり、子ども自身も遊びにくくなります。
定期的に使っていないおもちゃを見直し、処分や譲渡をすることで、整理整頓がしやすくなり、快適な環境を保てます。特に新しいおもちゃを購入する際には、古いものを整理する習慣をつけると良いでしょう。
安全面の観点から処分を検討する場合
おもちゃは使用年数が長くなると劣化し、安全性が低下することがあります。例えば、表面の塗装が剥がれたり、小さな部品が取れかけていると、子どもが誤って飲み込む危険性があります。
また、電池が入っている場合は液漏れや発熱のリスクもあるため、劣化したおもちゃは早めに処分することが重要です。安全面を考慮して、定期的におもちゃの状態をチェックし、問題があれば処分を検討しましょう。
新しいおもちゃを迎える前の整理
新しいおもちゃを購入する際に、古いおもちゃを処分したり譲ったりすることで、整理がスムーズに進みます。子どもにとっても遊ぶスペースが確保され、新しいおもちゃに集中しやすくなるため、整理整頓の良い機会です。また、古いおもちゃをただ捨てるのではなく、誰かに譲ることで再利用を促し、環境にも優しい選択となります。
おもちゃの種類ごとの処分方法
おもちゃは素材や構造、使われている電池や電子部品の有無によって、適切な処分方法が異なります。そのため、処分する前にはおもちゃの種類や状態をよく確認することが大切です。ここでは代表的なおもちゃの種類ごとに、処分の注意点やおすすめの方法をご紹介します。
プラスチック製おもちゃ
最も一般的なおもちゃの素材がプラスチックです。ブロックやフィギュア、小型の乗り物などが該当し、多くの場合は「燃やせないごみ(不燃ごみ)」として処分されます。ただし、自治体によっては「燃やせるごみ」として分類されていることもあるため、必ず地域のごみ分別ルールを確認しましょう。大きさによっては粗大ゴミ扱いになるケースもあるため、サイズにも注意が必要です。
電子おもちゃ(電池・バッテリー内蔵)
音が鳴る、光る、動くといった電子おもちゃには乾電池やボタン電池、リチウム電池などが使われている場合があります。これらのおもちゃを処分する際は、必ず電池を取り外してから廃棄するようにしましょう。
電池は小型充電式電池リサイクル協力店や回収ボックスを活用して適切にリサイクルすることが大切です。また、基板などの電子部品が含まれているおもちゃは、不燃ごみではなく家電小物として回収している自治体もあります。
木製おもちゃ
木のおもちゃは自然素材でできているものが多く、ナチュラルな風合いが人気です。壊れていない状態であれば、リユースショップや保育施設などで引き取ってもらえることがあります。
ただし、汚れや破損がひどい場合は燃やせるごみや粗大ごみとして扱われることがあります。サイズが大きな積み木や木馬などは、粗大ごみに該当するケースが多いため、各自治体のルールに従って処分しましょう。
布製おもちゃ・ぬいぐるみ
ぬいぐるみや布製のラトルなどは、家庭で遊ばれなくなった後も寄付や譲渡で活用されることがあります。状態が良ければ福祉施設や海外支援団体などが受け入れている場合もありますが、必ず事前に受け入れ可能かどうか確認する必要があります。
汚れやカビ、破損がある場合は衛生面の理由から寄付できないため、その場合は可燃ごみとして処分します。サイズによっては粗大ごみに該当することもあるため要注意です。
手作り・複合素材のおもちゃ
手作りのおもちゃや、複数の素材が組み合わさったおもちゃ(例:布と木、プラスチックと金属など)は、分別が難しいため基本的には自治体の分別ルールに従い、可能な範囲で解体してから処分するのが望ましいです。解体が困難な場合は粗大ごみとして出すか、不用品回収業者への依頼も検討しましょう。
安全に処分するための注意点
おもちゃを処分する際には、ただゴミ袋に入れて捨てるだけでは不十分です。特に電子部品を含むものや、鋭利なパーツ、小さな部品を持つおもちゃは、安全性に十分配慮した処理が必要です。ここでは、事故や環境被害を防ぐための具体的な注意点について説明します。
電池の取り外しと適切な処分
電子玩具の多くには乾電池やボタン電池、リチウムイオン電池などが使用されています。これらの電池を入れたままおもちゃを廃棄すると、ゴミ収集や処理の過程で発火や爆発、液漏れなどの事故につながる可能性があります。特にリチウム電池は非常に発火性が高いため、必ず事前に取り外し、電池だけを適切な方法で処分する必要があります。
乾電池やボタン電池は、家電量販店やスーパーなどに設置されている「電池回収ボックス」に出すか、自治体が実施している「電池回収日」に分けて提出しましょう。また、電池が劣化して取り外しにくい場合や、腐食している場合には、手をけがしないよう手袋を着用するなどの対策も重要です。
小さな部品・鋭利なパーツの取り扱い
おもちゃの中には、ネジやバネ、針金、ビーズなど、小さな部品や鋭利なパーツが含まれていることがあります。こうした部品をそのままゴミ袋に入れると、袋が破けたり、収集作業員がけがをする原因になります。また、小さな部品はペットや小さな子どもが誤って飲み込んでしまう危険もあります。
このような部品は、できるだけおもちゃ本体から取り外して分別し、透明のビニール袋に入れて「危険物あり」と記載する、もしくは自治体の指示に従って可燃ごみまたは不燃ごみとして処理するのが適切です。壊れたおもちゃを解体する際には、カッターやドライバーを使用する場面もあるため、工具の取り扱いにも注意しましょう。
袋詰めの工夫で事故防止
解体したおもちゃや分別した部品は、新聞紙で包んだり、ビニール袋で二重に包むなどして、飛び出しや漏れがないようにすることで安全性が高まります。特にガラガラ音が出るタイプのプラスチック球や鈴などは、袋に穴が空くと散乱してしまうため、密封して捨てることをおすすめします。
安全確認と最終チェック
おもちゃの処分前には、「電池が残っていないか」「壊れていないか」「取り外しが必要なパーツがないか」など、最終チェックを行いましょう。とくに小さな子どもがいる家庭では、処分前に部屋に落ちているおもちゃのパーツがないかも併せて確認すると安心です。
おもちゃの処分方法5選
自治体のごみ分別ルールに従う
おもちゃを処分する際の第一歩は、自分の住んでいる自治体のごみ分別ルールを正確に把握することです。おもちゃの種類によって「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などの分類が異なり、それに応じた正しい出し方を守ることが求められます。
例えば、小型のプラスチック製おもちゃは「燃えるごみ」として扱われることが多いですが、電池を含むものや金属が使われているものは「燃えないごみ」に分類されることがあります。さらに、長さやサイズが一定基準を超えるもの(多くの自治体では30cm以上)は「粗大ごみ」となり、通常のごみ収集では回収されません。
特に木製のおもちゃや大型の乗用玩具などは、家具に近い扱いとなるケースが多く、「粗大ごみ受付センター」や自治体の専用サイトから事前に回収申込みを行い、料金を支払って「粗大ごみ処理券」を貼付のうえ指定日に出す必要があります。処理券はコンビニや郵便局で購入できます。
また、自治体によっては回収日が月に一度など限定されているため、余裕を持って処分の準備を行うことが重要です。ごみの分別ルールは市区町村によって異なるため、公式サイトや「ごみ分別アプリ」などで確認することをおすすめします。
リサイクルショップや中古買取店で売る
まだ使用できる状態のおもちゃは、リサイクルショップや中古買取店に持ち込んで売るという選択肢があります。特に状態が良く、元箱や説明書が揃っているおもちゃは買取対象になりやすく、有名ブランドやキャラクター商品は高額査定が期待できることもあります。
近年では、子どもの知育玩具や教育系おもちゃの需要が高まり、中古市場でも人気が高まっています。たとえば、レゴやトミカ、プラレール、アンパンマンシリーズなどは、多くのリサイクル店で安定した需要があり、年式が新しいほど高値がつきやすい傾向にあります。
店舗によっては「電源が入るか」「パーツが揃っているか」「外装に傷があるか」などを基に査定を行うため、事前の掃除や動作確認をしておくとスムーズです。また、事前に店舗のホームページで「買取不可商品」や「季節ごとの強化買取商品」などをチェックしておくと、買取成立の確率も上がります。
時間がない場合は、宅配買取サービスを利用するのもひとつの方法です。箱に詰めて送るだけで査定してもらえるため、手間がかからず便利です。
フリマアプリや譲渡で再利用する方法
個人間で売買ができるフリマアプリ(例:メルカリ、ラクマなど)やオークションサイト(ヤフオク等)を活用することで、希望の価格でおもちゃを販売できる可能性があります。特に人気のあるおもちゃや、すでに廃盤となった希少品などは、店頭買取よりも高く売れることがあります。
販売にあたっては、商品の状態を正確に伝えることが重要です。傷や汚れ、動作不良の有無、欠品の有無などを、商品説明欄に詳しく書きましょう。また、写真も清潔感があり明るい場所で撮影したものを複数枚掲載することで、購入希望者に信頼感を与えられます。
さらに、家族や友人、近所の知り合いに譲るという手もあります。引っ越しや片付けのタイミングで「使わなくなったけどまだ使えるおもちゃ」が出てきたら、身近な人に声をかけて譲ることで、ゴミにならずに済み、相手にも喜ばれます。
ただし、譲渡の際も「安全性」の確認は怠らずに。小さな部品の欠損がないか、電池の液漏れがないかなど、再利用されることを意識したメンテナンスが大切です。
寄付やチャリティに出す場合
使わなくなったけれどまだ十分使えるおもちゃは、児童養護施設、病院、保育施設、発展途上国支援団体などに寄付する方法もあります。特に教育系の知育玩具、パズル、絵本、ぬいぐるみなどは、多くの施設や団体で喜ばれるアイテムです。
ただし、受け入れ側の団体にはそれぞれ受け入れ条件があり、「未使用に近い状態」「洗浄・除菌済みであること」「電池を抜いていること」「破損・欠品がないこと」などを求められるケースが一般的です。そのため、寄付を希望する際には、必ず事前に団体のホームページや問い合わせ窓口で条件を確認しましょう。
また、郵送での寄付になる場合、送料は自己負担となることが多いため、その点も考慮しておくと良いでしょう。こうした寄付活動は、社会貢献や子どもの笑顔に繋がる喜びを感じられる方法でもあります。
不用品回収業者に依頼する方法
壊れていて売れない、リサイクルや寄付にも出せない大量のおもちゃは、不用品回収業者にまとめて依頼するのが効率的です。特に引っ越しや大掃除の際など、大量におもちゃを処分したい場合には、ドア・ツー・ドアで対応してくれる業者は非常に便利です。
業者によっては、状態の良いものは買取してくれる「回収+買取サービス」を提供しているところもあります。また、当日中の出張回収や、夜間・土日対応など、柔軟なサービス体制が整っている業者も多く、忙しい家庭には助かる存在です。
ただし、利用時には料金体系やサービス内容を事前に確認し、悪質な業者を避けることが重要です。見積もりは複数社に依頼して比較することが推奨されており、口コミサイトや公式サイトで評判をチェックするのも有効です。
おもちゃの処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回はおもちゃの処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
おもちゃを処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!