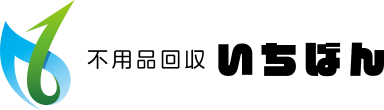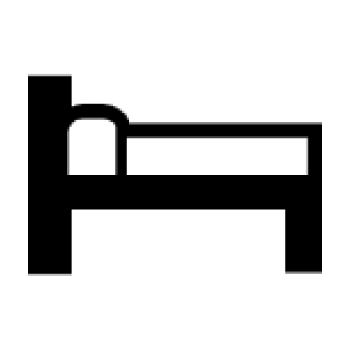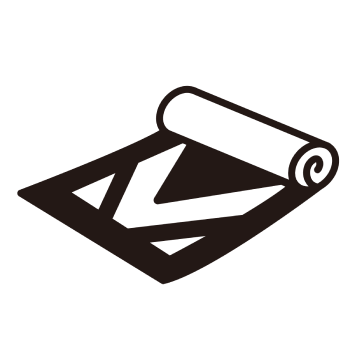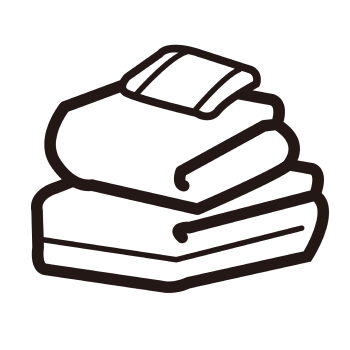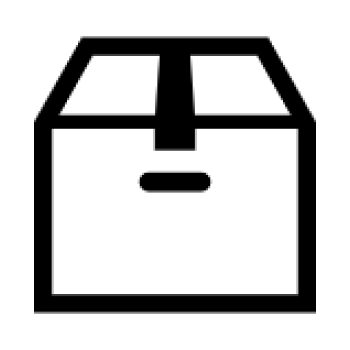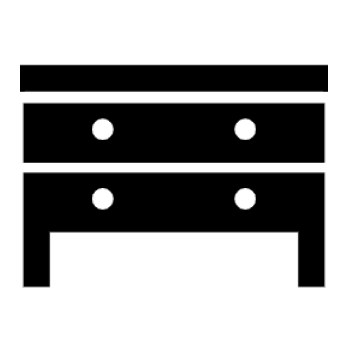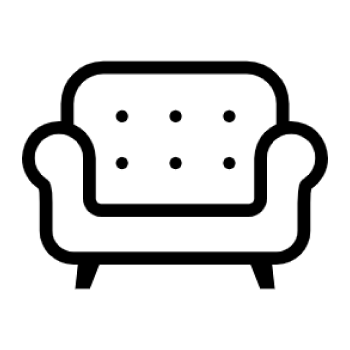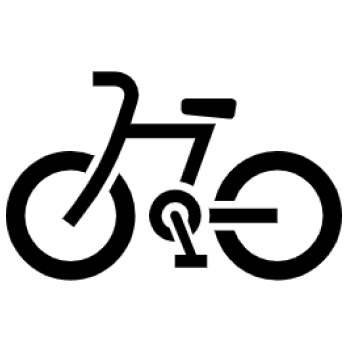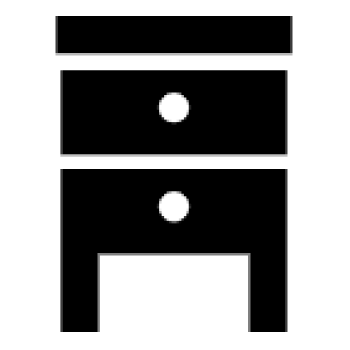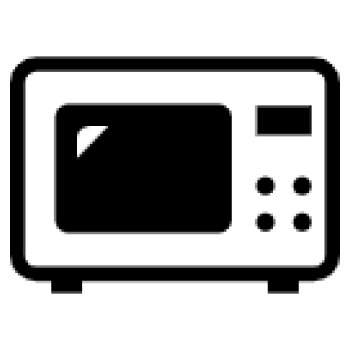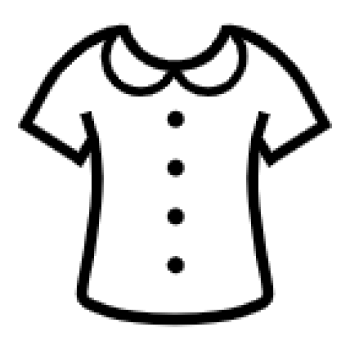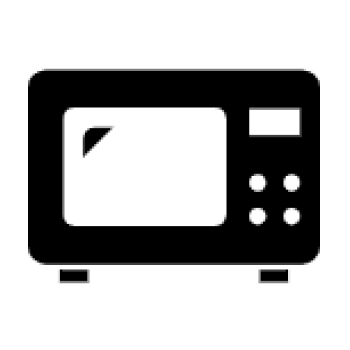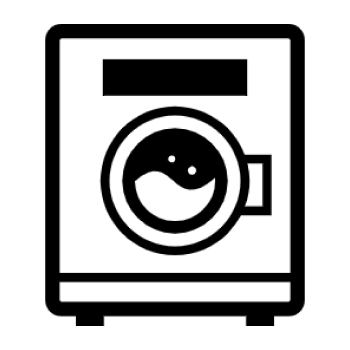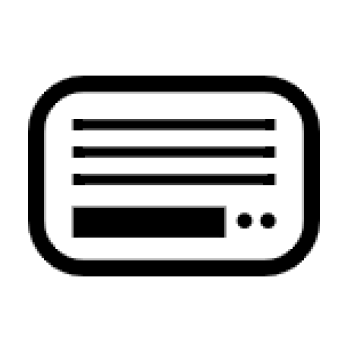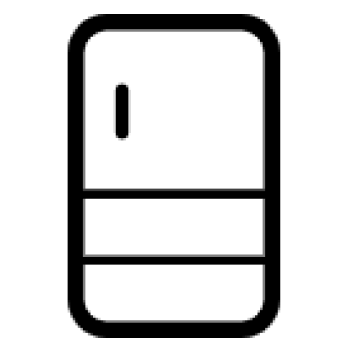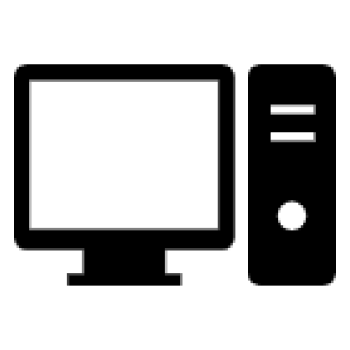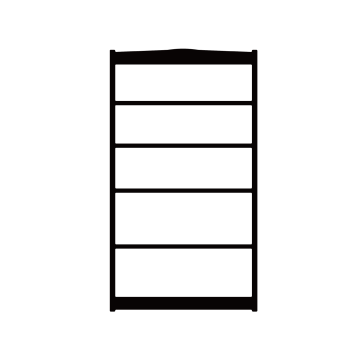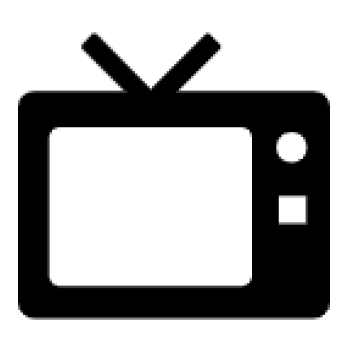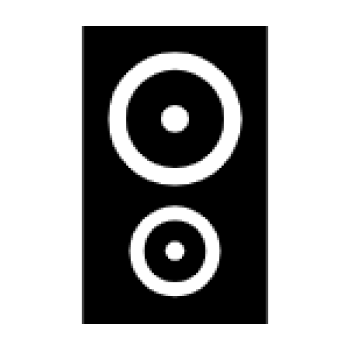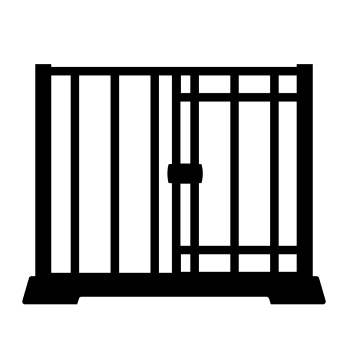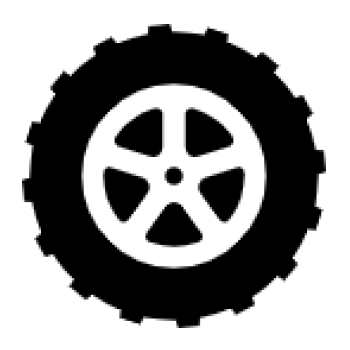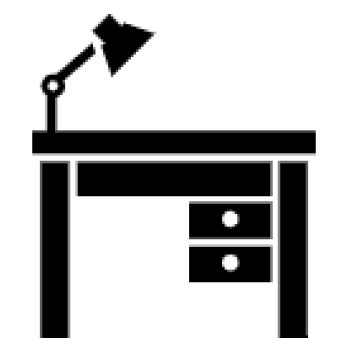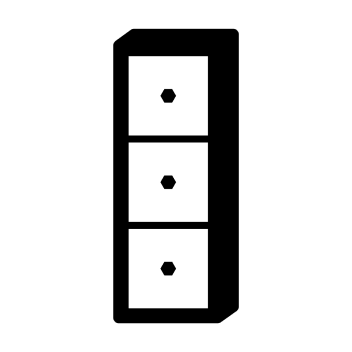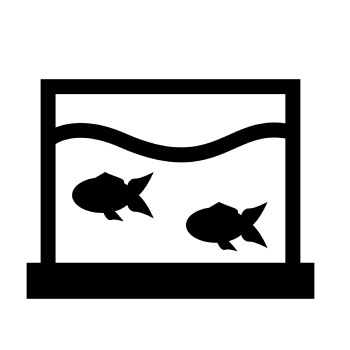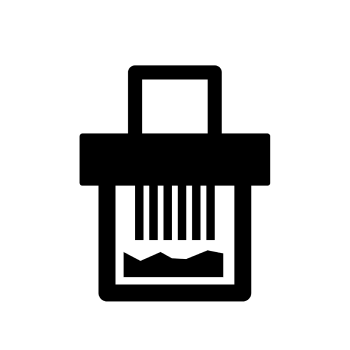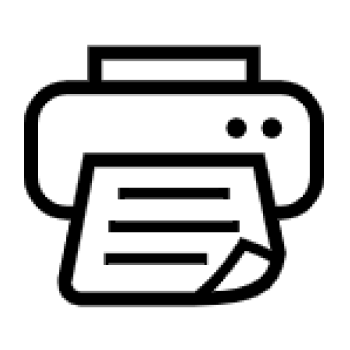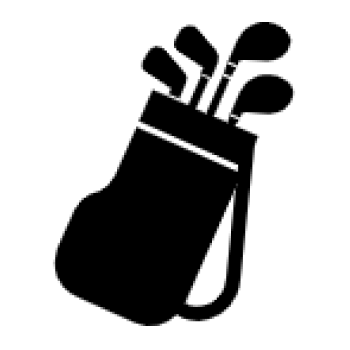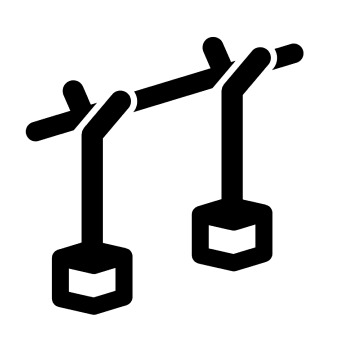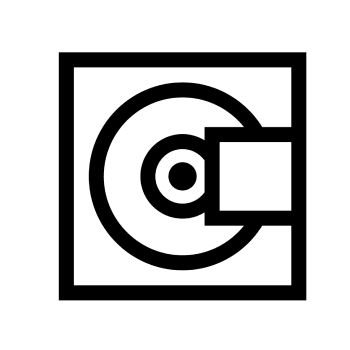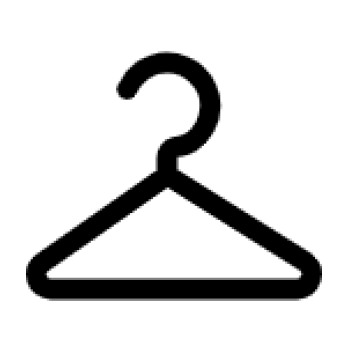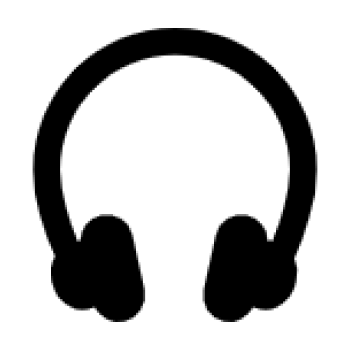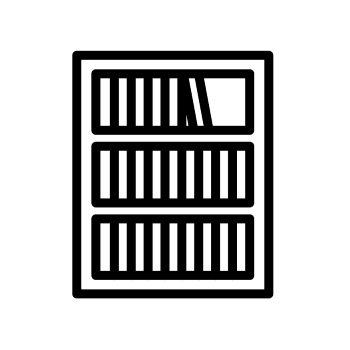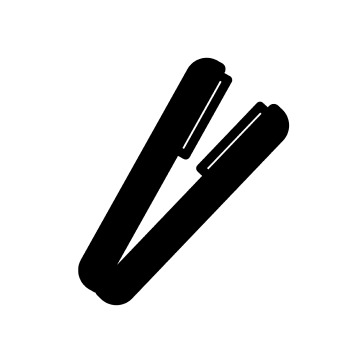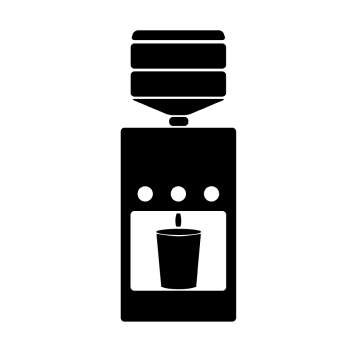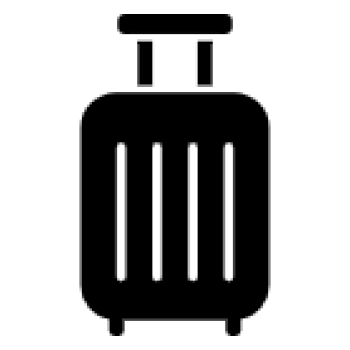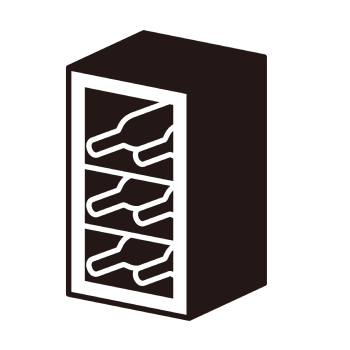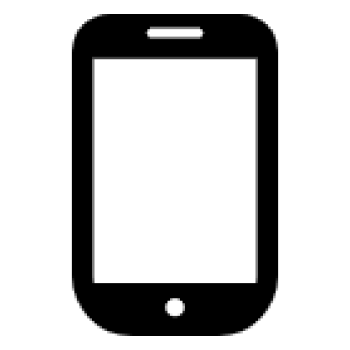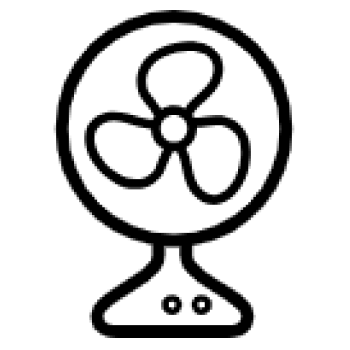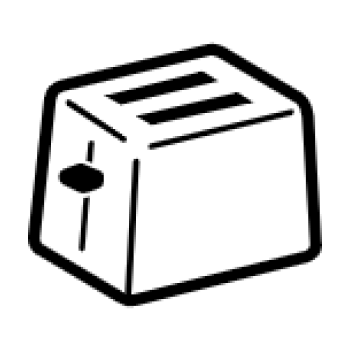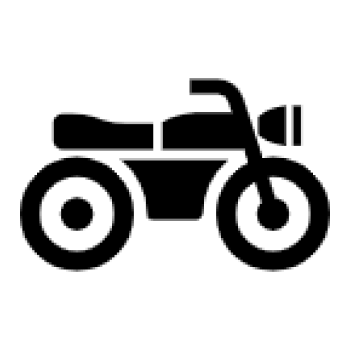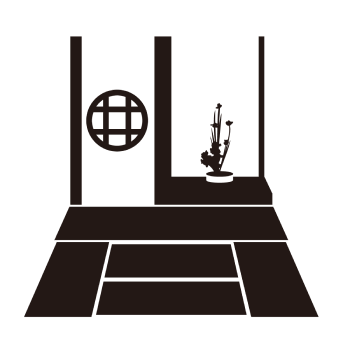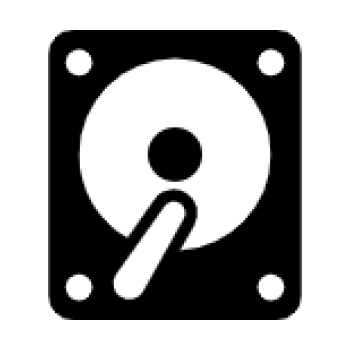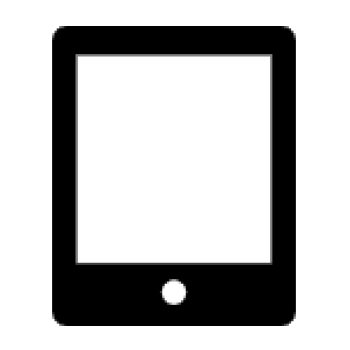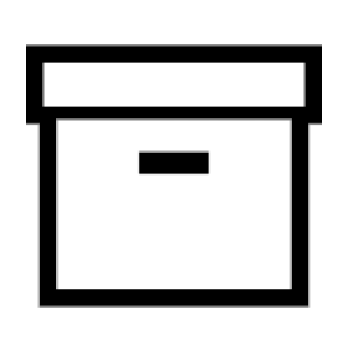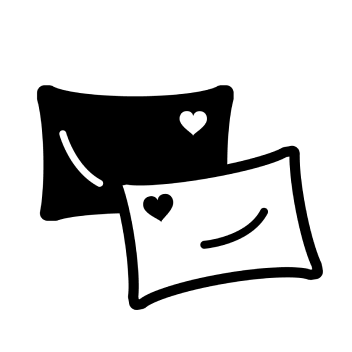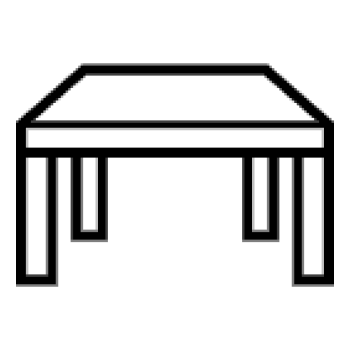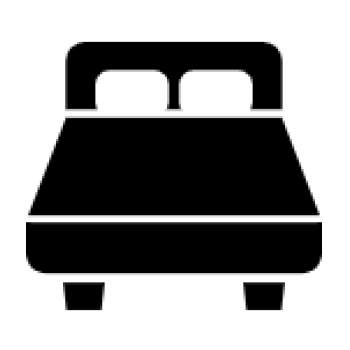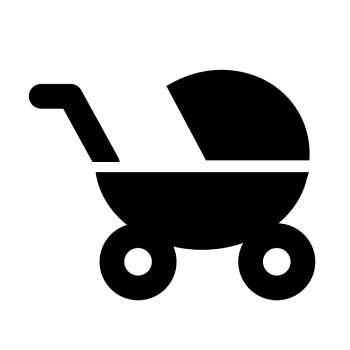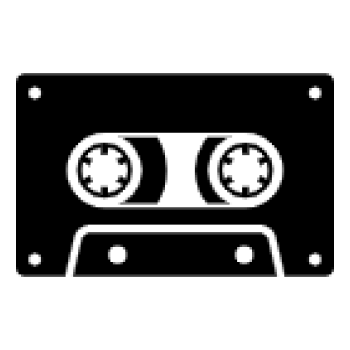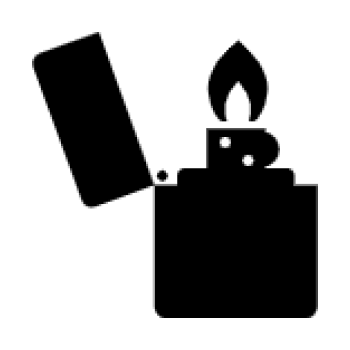蛍光灯は、家庭やオフィスなどで長年使われてきた照明器具の一つです。現在はLED照明への置き換えも進んでいますが、まだまだ多くの場所で使用されており、寿命を迎えた際には適切な処分が必要です。しかし、蛍光灯の内部にはガラス管のほかに微量の水銀が含まれており、一般ごみとしてそのまま捨てることはできません。不用意に破棄すると、割れたガラスによってけがをしたり、場合によっては火災や水銀による健康被害が生じる可能性もあるため、細心の注意が求められます。
特に、水銀は有害物質に指定されており、土壌や水質汚染の原因にもなり得るため、自治体ごとに定められた適正な方法での回収が求められています。また、蛍光灯は見た目では寿命を判断しにくいこともあるため、適切なタイミングで交換し、同時に正しく処分することが大切です。
この記事では、蛍光灯の寿命や交換すべきタイミング、処分する際に注意しておきたいポイント、蛍光灯をできるだけ長く使うためのコツ、さらに具体的な処分方法まで、幅広く丁寧に解説します。ご家庭に不要になった蛍光灯が眠っている方、どうやって捨てたらいいか迷っている方は、ぜひ本記事を参考にして、安全で環境にやさしい処分を心がけましょう。
蛍光灯を処分するタイミングとは?
蛍光灯は、長寿命かつ消費電力が少ない照明として広く使われてきましたが、永久に使えるわけではありません。一般的に蛍光灯の寿命は約6,000〜12,000時間とされています。これは、例えば1日8時間の使用を想定すると、およそ2年〜4年程度で寿命を迎える計算になります。使用時間が長いオフィスや店舗などでは、さらに短いサイクルで交換が必要になる場合もあります。
チカチカと点滅を繰り返す
蛍光灯が頻繁に点滅を繰り返す(フリッカー現象)ようになるのは、明確な寿命のサインです。蛍光灯は寿命が近づくと安定した電流の流れが維持できなくなり、点灯と消灯を短時間で繰り返すようになります。こうした点滅は目に負担をかけるだけでなく、不快感やストレスの原因にもなります。点滅が見られたら早めの交換・処分を検討しましょう。
光が暗くなった、全体的に照度が落ちたと感じる
見た目には点灯していても、以前より明るさが足りないと感じるようになったら、それも寿命が近い兆候です。蛍光灯は劣化とともに発光効率が落ちていき、光の質も低下します。特に高い照度が求められる場所(キッチンや作業スペースなど)では、暗い照明は作業効率や安全性にも影響を与える可能性があります。
両端が黒ずんでいる
蛍光灯の両端が黒くなっている場合も、寿命の典型的なサインのひとつです。この黒ずみは、点灯の際に必要な電極の劣化によって生じるものです。黒ずみが目立つようになった蛍光灯は、近いうちに点灯しなくなる可能性が高いため、早めの交換が賢明です。
寿命を過ぎた蛍光灯はリスクになる
寿命を迎えた蛍光灯を無理に使い続けると、器具本体への負荷がかかって故障の原因になったり、電気代が余計にかかることもあります。また、古い蛍光灯が突然破裂したり、取り扱いの際に破損してガラスが飛び散る危険性もあります。
適切なタイミングで交換・処分を
こうした症状が見られたら、蛍光灯を安全に取り外し、適切な方法で処分することが重要です。蛍光灯の処分は通常の家庭ごみとは異なり、分別や収集方法に注意が必要です。次のセクションでは、処分時に気をつけるべきポイントや安全対策について詳しく解説します。
処分する際の注意点
蛍光灯はその構造上、取り扱いに注意が必要な製品です。ガラス製で非常に割れやすく、内部にはごく微量の水銀が含まれているため、不用意に扱うと怪我や健康被害を引き起こす可能性があります。安全に処分するためには、以下のポイントを必ず守るようにしましょう。
割れないように丁寧に梱包する
蛍光灯を処分する際、まず最初に気をつけたいのが「割れ」への対策です。使用済みの蛍光灯は内部の気圧が低く、非常に壊れやすくなっています。処分時に落としたり、無造作にごみ袋へ入れてしまうと、簡単に破損してしまうおそれがあります。
破損を防ぐには、新聞紙でぐるぐる巻きにするか、緩衝材(いわゆるプチプチ)で包むのが基本です。さらにその上から厚手のビニール袋や段ボール箱に入れると、破損した際の飛散も防げます。中が見える透明な袋に入れると、収集員も中身を認識しやすく、安全性が高まります。
自治体ごとの分別ルールを必ず確認
蛍光灯の処分ルールは自治体ごとに異なる点も重要です。「不燃ごみ」として扱う自治体もあれば、「有害ごみ」や「資源ごみ」として別枠で回収している自治体もあります。ごみ出しルールを誤ると、回収されずに残されてしまうこともあるため、自治体の公式ホームページやごみ分別アプリなどで、必ず事前に確認しましょう。
また、一部の自治体では「蛍光灯は回収所に直接持ち込み」「専用のごみ袋を使用」などの特別なルールが設定されていることもあります。特に事業所やオフィスで使用した蛍光灯は、一般家庭の回収対象外となる場合もあるので注意が必要です。
水銀の飛散リスクに注意する
蛍光灯の内部には、ごく微量ながら水銀が使用されています。通常使用している分には問題ありませんが、万が一破損すると、有害な水銀蒸気が空気中に放出されるリスクがあります。人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、特に小さなお子様やペットがいる家庭では注意が必要です。
もし誤って蛍光灯を割ってしまった場合は、まず窓を開けてしっかり換気を行いましょう。破片や水銀を素手で触ったり、掃除機で吸い込むのは厳禁です。破片は厚紙などで慎重に集め、ガラスや水銀と分かるように分別して処分してください。
蛍光灯を長持ちさせるためのコツ
蛍光灯は消耗品である以上、いつかは交換が必要ですが、使用方法次第でその寿命をできるだけ延ばすことができます。頻繁に交換するのは手間がかかるだけでなく、コストもかさみます。ここでは、家庭やオフィスでできる簡単な工夫で蛍光灯を長持ちさせるコツをご紹介します。
スイッチのオン・オフを控えめに
蛍光灯は点灯時に最も電力を消費し、内部に大きな負荷がかかるため、頻繁なオン・オフ操作は寿命を縮める原因となります。特に、トイレや廊下などで「出入りのたびにスイッチを切る」ような使い方をしていると、意外と早く寿命を迎えてしまうこともあります。
目安として、5分以内に再び点灯する可能性がある場合は、つけっぱなしにしておく方が寿命的には有利です。もちろん、無駄な電力消費にならないよう、使用頻度や環境に応じて適切に判断しましょう。
照明器具や安定器の状態をチェック
蛍光灯そのものが問題ではなく、照明器具の内部にある「安定器(バラスト)」が劣化していることで、寿命が短くなっているケースもあります。安定器が老朽化すると、電流が不安定になり、蛍光灯に過剰な負荷がかかるためです。
蛍光灯を交換してもすぐにチラついたり、点灯しなかったりする場合は、器具そのものの劣化が疑われます。特に築年数の経った建物では、安定器が古い規格のまま使われていることも多く、その場合は器具の交換も視野に入れましょう。
定期的な清掃で放熱効率を維持
蛍光灯の表面や照明カバーにほこりや汚れが溜まると、熱がこもりやすくなり、結果として寿命を縮めてしまうことがあります。蛍光灯は使用中にある程度の熱を発するため、放熱が妨げられると内部の部品が劣化しやすくなるのです。
年に数回で構わないので、乾いた布で軽く拭き取るだけでも効果的です。ただし、掃除の際は必ず電源を切り、蛍光灯が十分に冷えてから行ってください。また、無理に力を入れたり、濡れた布で拭いたりするのは破損や感電の原因になるため避けましょう。
点灯環境を見直すことも大切
蛍光灯は寒さや湿気にも弱い特性があります。屋外や湿気の多い場所で使用している場合、寿命が短くなることがあります。そうした環境では、防湿・防水対応の照明器具に切り替えるか、LED照明への交換も検討すると良いでしょう。
蛍光灯の処分方法4選
蛍光灯を正しく安全に処分するには、以下のような方法があります。お住まいの地域や状況に応じて、最適な方法を選びましょう。
自治体の回収ルールに従って処分する
蛍光灯の最も一般的な処分方法は、自治体のごみ分別ルールに従って家庭ごみとして出す方法です。ただし、蛍光灯は「可燃ごみ」ではなく、「不燃ごみ」「有害ごみ」「資源ごみ」など、自治体ごとに分類が異なる点に注意が必要です。特に水銀を含む蛍光灯は、環境への影響から「有害ごみ」として扱われることが多く、通常の不燃ごみと同様に扱うことはできません。
多くの自治体では、蛍光灯を処分する際には新聞紙や緩衝材で包み、透明または半透明の袋に入れるなど、破損防止の梱包が義務付けられています。ガラス製で割れやすく、割れた場合には破片でけがをする恐れがあるためです。また、自治体によっては「蛍光灯」と明記したシールの貼付を求めるところもあります。
回収日は地域によって異なりますが、月に1〜2回程度と少ないケースが多く、タイミングを逃すと次回まで自宅で保管しなければならない点にも注意しましょう。正確な分別ルールや収集日については、自治体のホームページや「ごみ分別アプリ」「広報誌」などを確認するのが確実です。間違った出し方をすると、回収されないだけでなく、環境や周囲への影響を及ぼす可能性もあるため、必ず事前にルールを確認したうえで出しましょう。
家電量販店やホームセンターに持ち込む
蛍光灯を安全かつスムーズに処分したい場合、家電量販店やホームセンターへの持ち込みも有効な方法の一つです。たとえばヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ケーズデンキ、コーナンなどの一部店舗では、蛍光灯の店頭回収を実施しています。特に電球や蛍光灯の売り場付近に回収ボックスが設置されていることもあります。
ただし、すべての店舗で常時回収を受け付けているわけではありません。多くの場合、「商品購入時のみ回収可」や「回収は1点につき1点購入時に限る」といった条件付きでの対応になるため、持ち込む前に電話などで確認しておくと安心です。また、自治体での処分が月に1回など限られている場合、買い替えのタイミングと合わせて回収してもらえるのは非常に便利です。
一部の店舗では無料で回収してもらえますが、条件によっては有料回収となることもあります。また、事業所などからの持ち込みや大量の廃棄は断られることがあるため、処分する本数や用途も事前に伝えて確認しておくとよいでしょう。
この方法のメリットは、買い物のついでに手軽に処分できることや、梱包の手間が少ない点です。自治体の収集日を待つ必要もなく、自分のタイミングで処分できる点も大きな利点です。
小型家電リサイクルの回収ボックスを活用する
小型家電リサイクル法に基づいて設置されている「小型家電リサイクルボックス」は、蛍光灯を処分する際に活用できる場合があります。これらのボックスは、自治体の役所、図書館、公共施設、スーパーや商業施設の一角などに設置されており、無料で利用できるのが特長です。
ただし、このボックスがすべての蛍光灯を対象としているわけではありません。蛍光灯のサイズが大きすぎたり、形状が特殊だったりする場合、回収対象外になる可能性があります。また、割れた蛍光灯や水銀を含むタイプは回収対象外としているボックスも多く、利用前には設置場所に記載された「対象品目一覧」や自治体の案内を必ず確認してください。
さらに、リサイクルボックスはあくまで「家庭用の少量廃棄物」を対象としたものであるため、大量に処分することはできません。引越しやオフィスの整理で多くの蛍光灯を一度に廃棄するようなケースでは、他の手段を検討する必要があります。
とはいえ、この方法は「使い終わった蛍光灯を1~2本だけ手軽に処分したい」といった場合には非常に便利です。特に日常の買い物や役所の手続きのついでに処分できるため、利便性の高さが魅力です。
不用品回収業者に依頼する
大量の蛍光灯を一度に処分したい、あるいは割れた蛍光灯などで自分での持ち運びや梱包が不安な場合には、不用品回収業者への依頼が現実的な選択肢となります。不用品回収業者は、自宅まで訪問して回収してくれるため、体力的・時間的な負担を大きく軽減できます。
料金は業者や地域によって異なりますが、蛍光灯の本数やサイズに応じて数百円〜数千円程度が相場です。もちろん、他の不用品(家具や家電など)とまとめて回収を依頼すれば、単品よりもコストパフォーマンスがよくなることもあります。
業者選びの際は、必ず「一般廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っているかを確認しましょう。無許可業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。また、見積もり時に料金体系を明確に提示してくれる業者を選ぶことで、後から高額請求される心配も避けられます。
さらに、最近ではLINEやWebから簡単に回収依頼ができる業者も増えており、スピーディーな対応が可能です。処分だけでなく、運び出しや分別作業まで依頼できるため、蛍光灯以外にも処分したいものがある場合には非常に便利です。
蛍光灯の処分は不用品回収業者の利用がおすすめ
今回は蛍光灯の処分方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
蛍光灯を処分するにあたり、他にも不要になった品を大量に処分したい場合は、不用品回収業者を利用することを検討してみてください。不用品回収業者は、大型小型問わず他の不用品をまとめて引き取ってくれるため、処分方法を考えずにまとめて処分することが可能です。
優良不用品回収業者の選び方は?
不用品回収業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに処分が進みます。
- 対応エリアの確認
希望する地域に対応しているかを確認しましょう。全国対応の業者や地域密着型の業者があります。 - 料金の透明性
事前に見積もりを取って料金体系を確認し、追加料金が発生しないか確認しておくことが重要です。 - 口コミや評判
インターネット上のレビューや口コミを参考にし、信頼できる業者を選びましょう。実績や評判が良い業者は安心して依頼できます。 - 対応スピード
急いで処分したい場合は、即日対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。対応の速さは重要なポイントです。 - 保険の有無
万が一の事故やトラブルに備えて、損害補償保険に加入している業者を選ぶと安心です。
『不用品回収いちばん』は、他社と変わらないサービス内容が充実しているうえで、料金が圧倒的に安価であることが一番の特徴です。
| 不用品回収いちばん | エコピット | 粗大ゴミ回収隊 | GO!GO!!クリーン | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | SSパック 8,000円(税込)~ | SSパック 9,900円(税込)~ | Sパック 9,800円(税込)~ | SSパック 13,200円~(税込) |
| 見積り費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
| 即日対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い | 現金・事前振込・クレジットカード | 現金・クレジットカード・銀行振込 | 現金払い・事前振込・クレジットカード |
| 買取サービス | あり | なし | あり | なし |
『不用品回収いちばん』は、顧客満足度が非常に高く、多くの利用者から高い評価を受けている不用品回収業者です。また、警察OB監修のもと、お客様の安心安全を第一に作業をさせていただいております。
不用品回収いちばんの基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 不用品回収・ごみ屋敷片付け・遺品整理・ハウスクリーニング |
| 料金目安 | SSパック:8,000円〜 |
| 対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 受付時間 | 年中無休、24時間対応 |
| 電話番号 | 0120-429-660 |
| 支払い方法 | 現金払い、クレジットカード、請求書払い(後払い)、分割払い |
| その他 | 「WEB割を見た」とお伝えいただければ割引サービス |
『不用品回収いちばん』では、お電話で簡単なお見積もりを提供しております。お見積もりは完全無料です。また、出張見積もりも無料で行っており、料金にご満足いただけない場合はキャンセルも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
『不用品回収いちばん』は出張費用、搬出作業費用、車両費用、階段費用などがお得なプラン料金になっており、処分もスピーディーに行います。また、警察OB監修による安心安全第一のサービスを提供させて頂いております!
また、お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けております。事前見積もり・出張見積もりも無料なので、まずはお見積りだけという方も、ぜひお気軽にご相談ください。
不用品回収いちばんのサービス詳細はこちら!